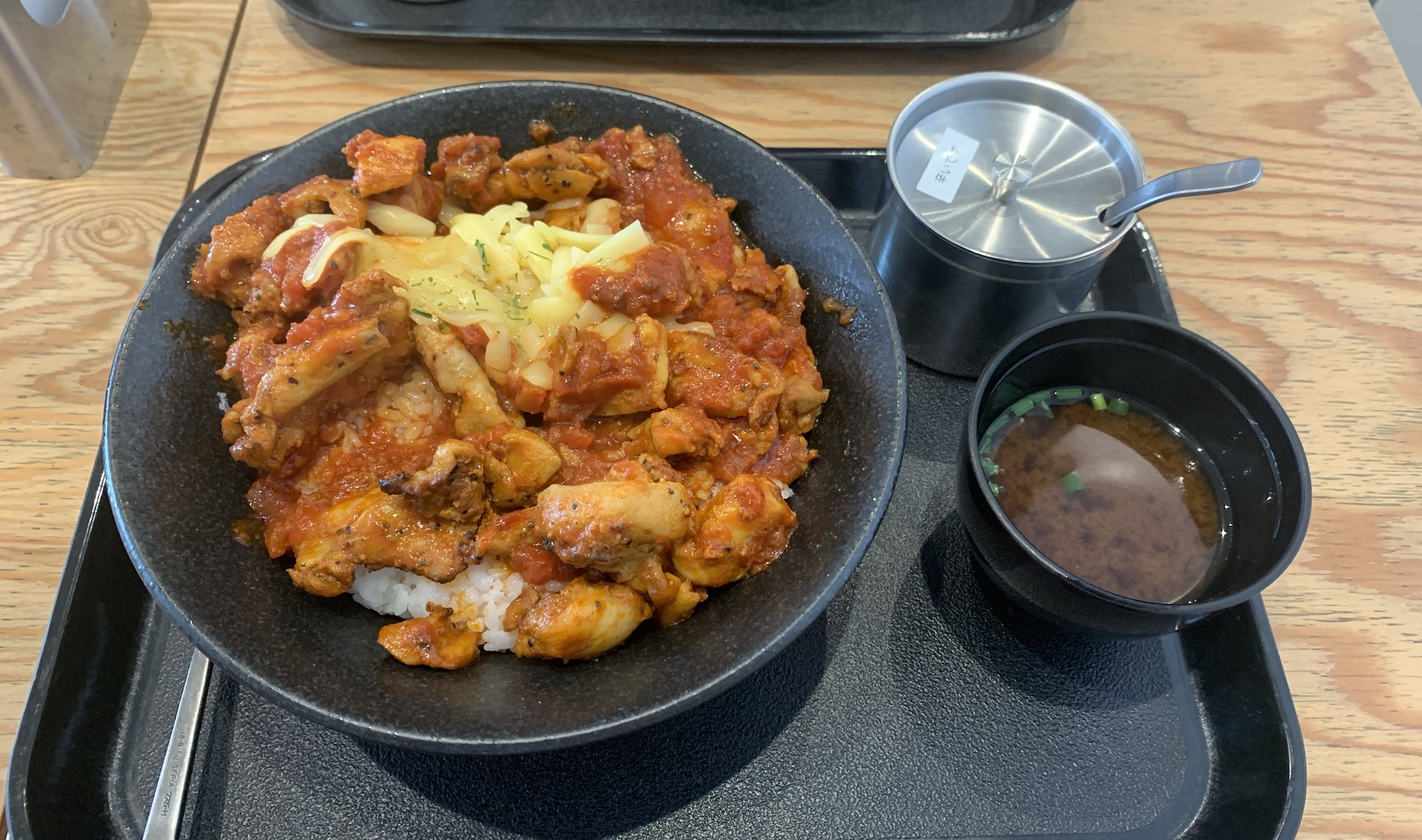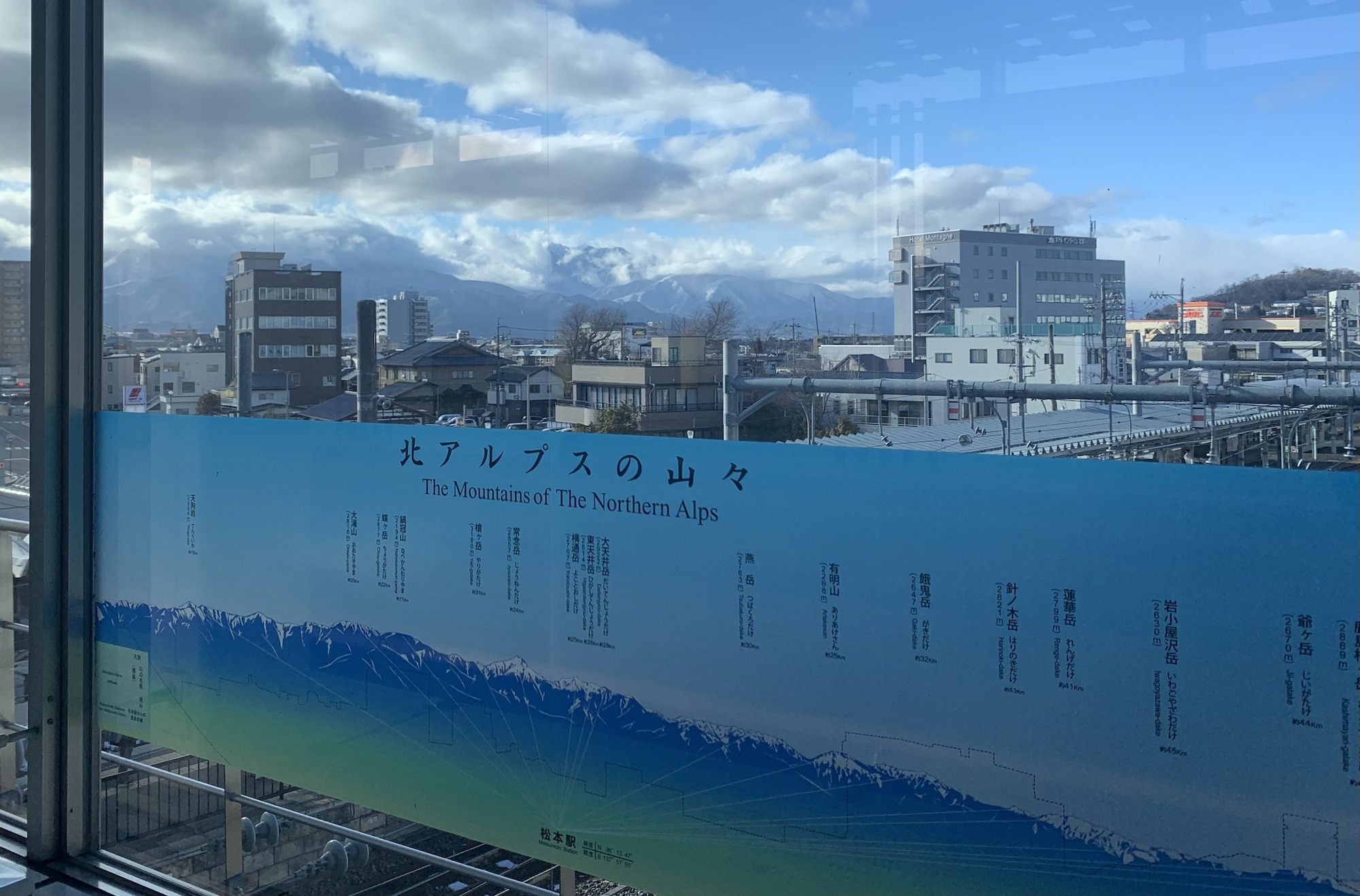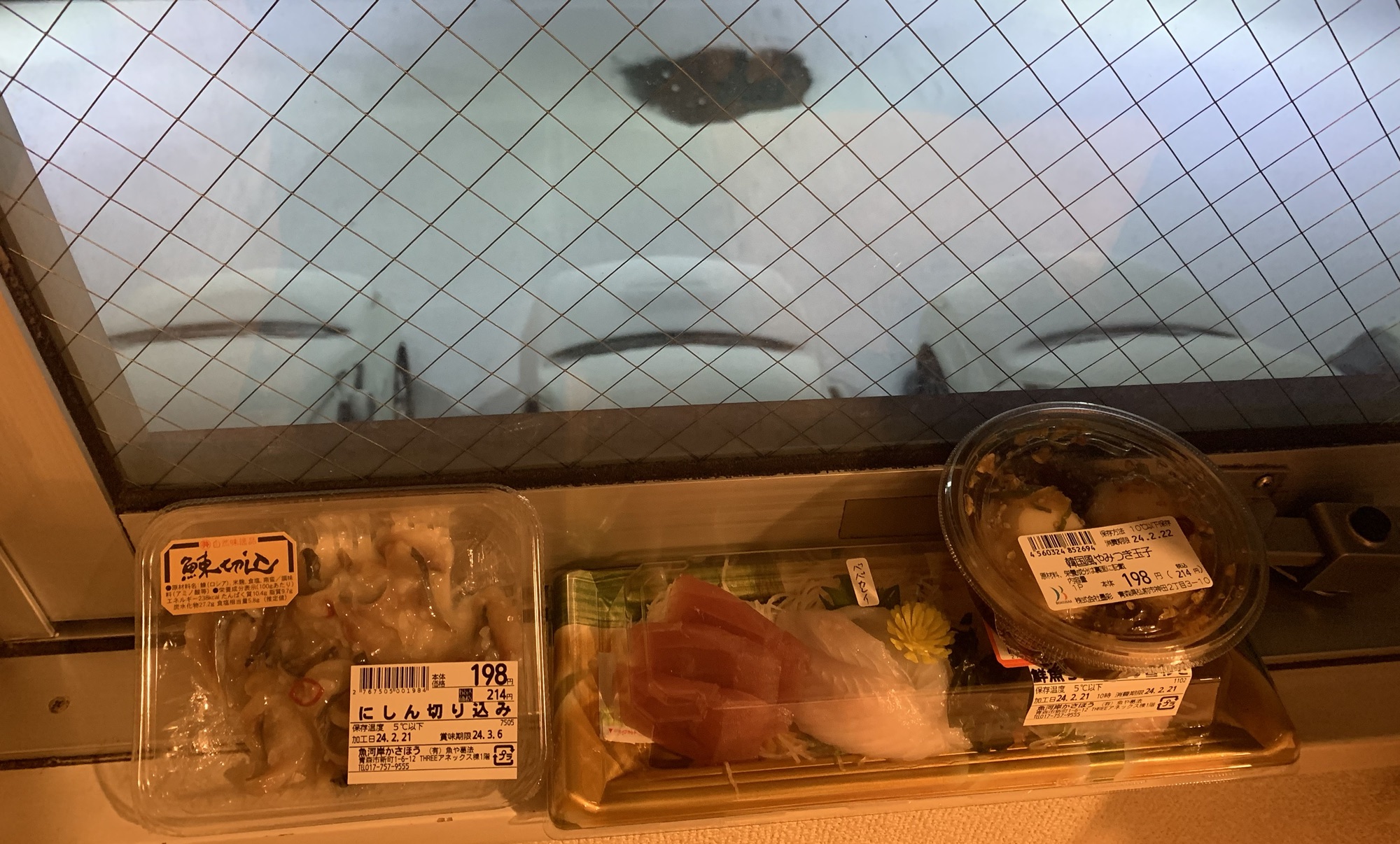今日は水道橋宝生能楽堂に用事があり、時間に余裕があったので三ノ輪から歩いていこうと思い立ちました。
・
自宅から能楽堂へはしばしば歩くので、いつもコースを変えています。
今回は日暮里繊維街から谷中墓地を抜けて、東京芸大の手前で右折して不忍通りに降りていきました。
・
・
そこでふと、「東大本郷キャンパスを通っていこうか」と思いました。
不忍通りから少し入った所に小さい門があり、芸大にいた頃東大病院に用事があり、何度か通っていたのです。
・
・
久しぶりにその「池之端門」をくぐろうとして、目の端に「弁慶」という文字が入ってきて思わず立ち止まりました。

なんとこの井戸はその昔義経一行が奥州へ落ち延びる途中で、武蔵坊弁慶が発見したという「弁慶鏡ヶ井戸」だそうなのです。
・
・
まさか東京の真ん中、東大キャンパスのすぐ横に弁慶に纏わる史蹟があるとは驚きでした。
芸大の頃は全く気がつきませんでした。
・
キャンパスに入って本郷通り方面に坂を登っていきます。

途中「東大剣道部」「東大柔道部」の看板のある、とても味わいの深い重厚な建物などがありました。
・
・
更に行くとまた下り坂になり、坂を下りたところにはかの有名な「三四郎池」があります。

この池、元々は加賀藩ゆかりの庭園の一部で正式名称は「育徳園心字池」というそうです。
加賀藩と言えば能楽宝生流とは深い繋がりがあり、その後に能楽愛好家でもあった夏目漱石の小説から「三四郎池」と呼ばれるようになった訳で、この池は能楽と実は浅からぬ縁があったのですね。
・

三四郎池の周囲は木々の中の遊歩道になっていて、これは京大における「吉田山」に近い存在感だと思いました。
・
・
そして安田講堂に向かっていくと、途中で見慣れない格好で写真を撮っている人達を見かけました。

どうも大学院の卒業生のようです。
・
・

よく見ると安田講堂の入り口に「学位記授与式」とあり、どうやら明後日が大学院卒業式のようでした。
さっきの人達は前もって記念写真を撮っていたのでしょう。
・
・
そして赤門から本郷通りに出て、壱岐坂を下って宝生能楽堂に向かいました。
・
今日も色々と新しい発見があり、良い散歩道でした。
もう少し後の桜の時期にも歩いてみたいと思いました。