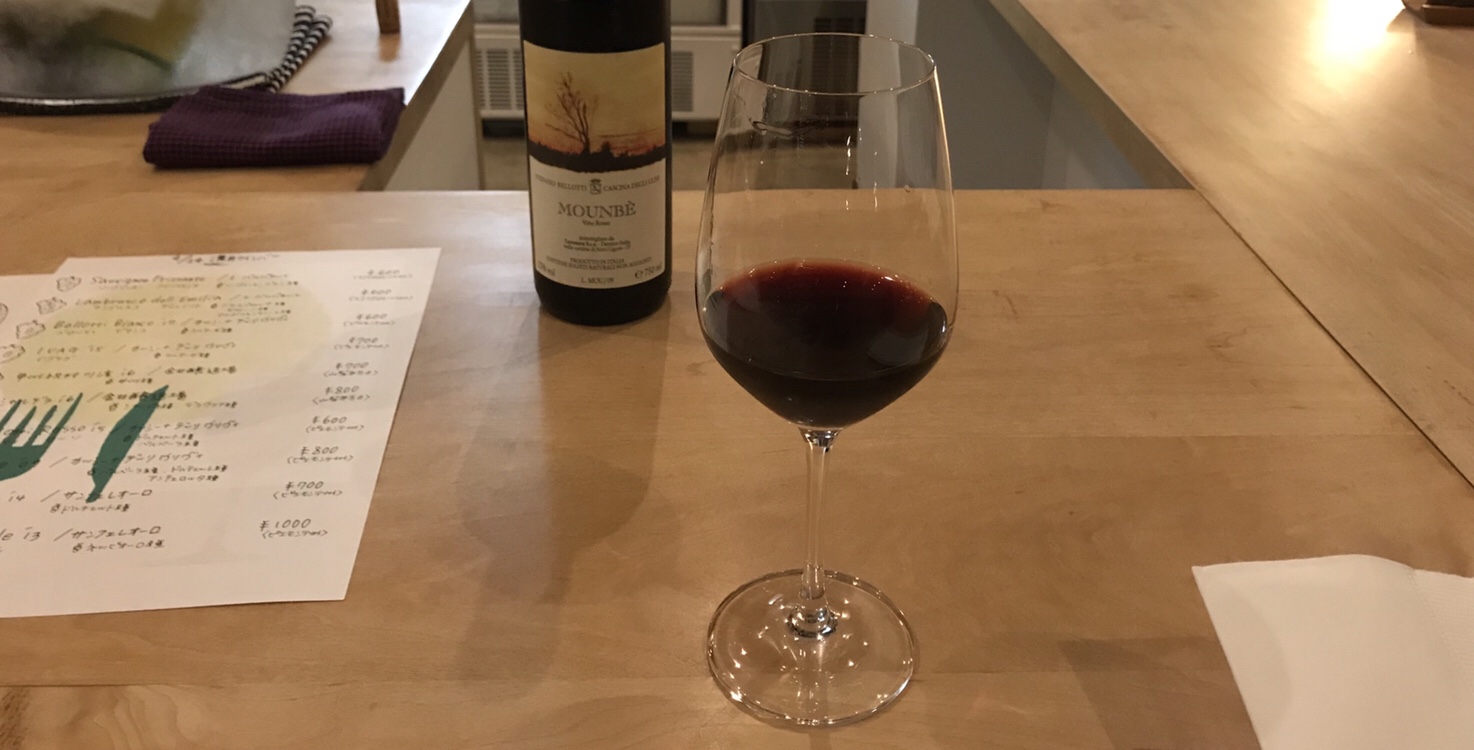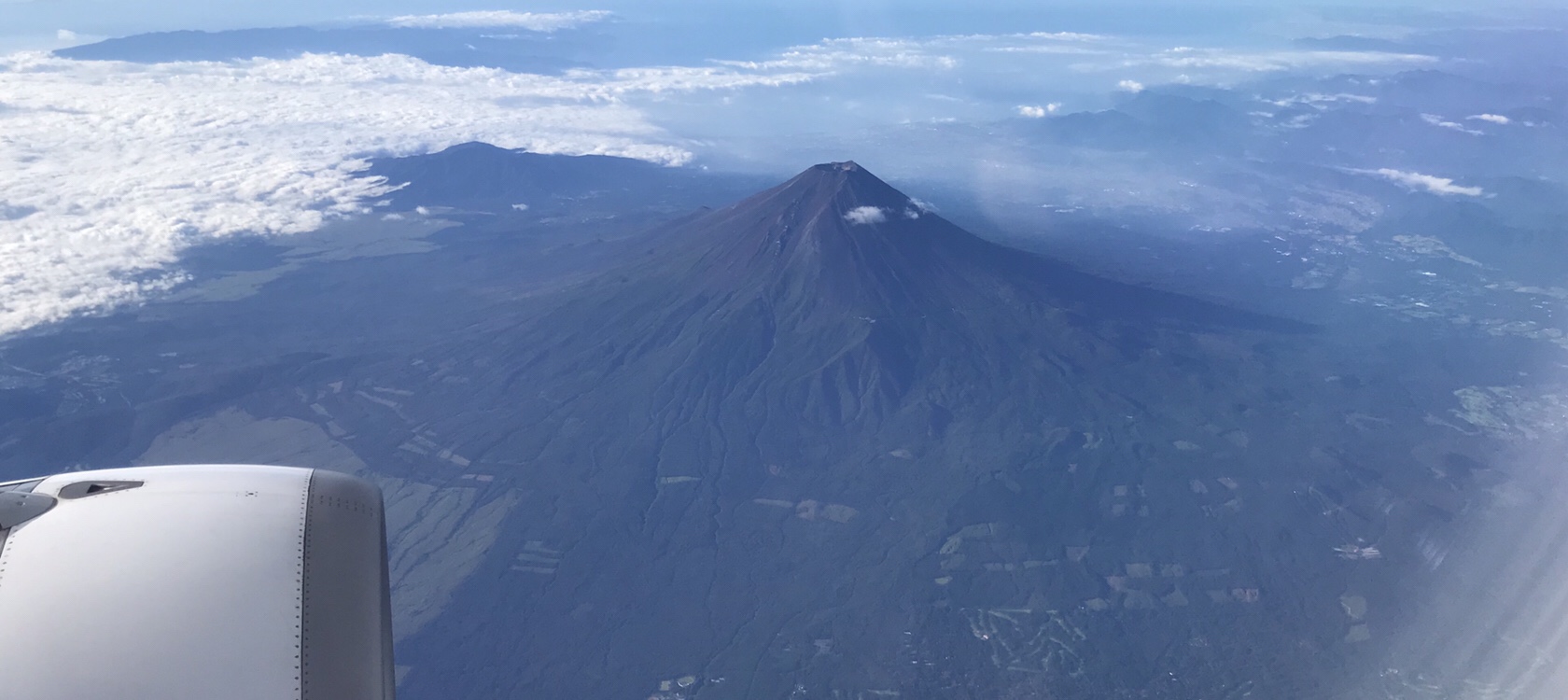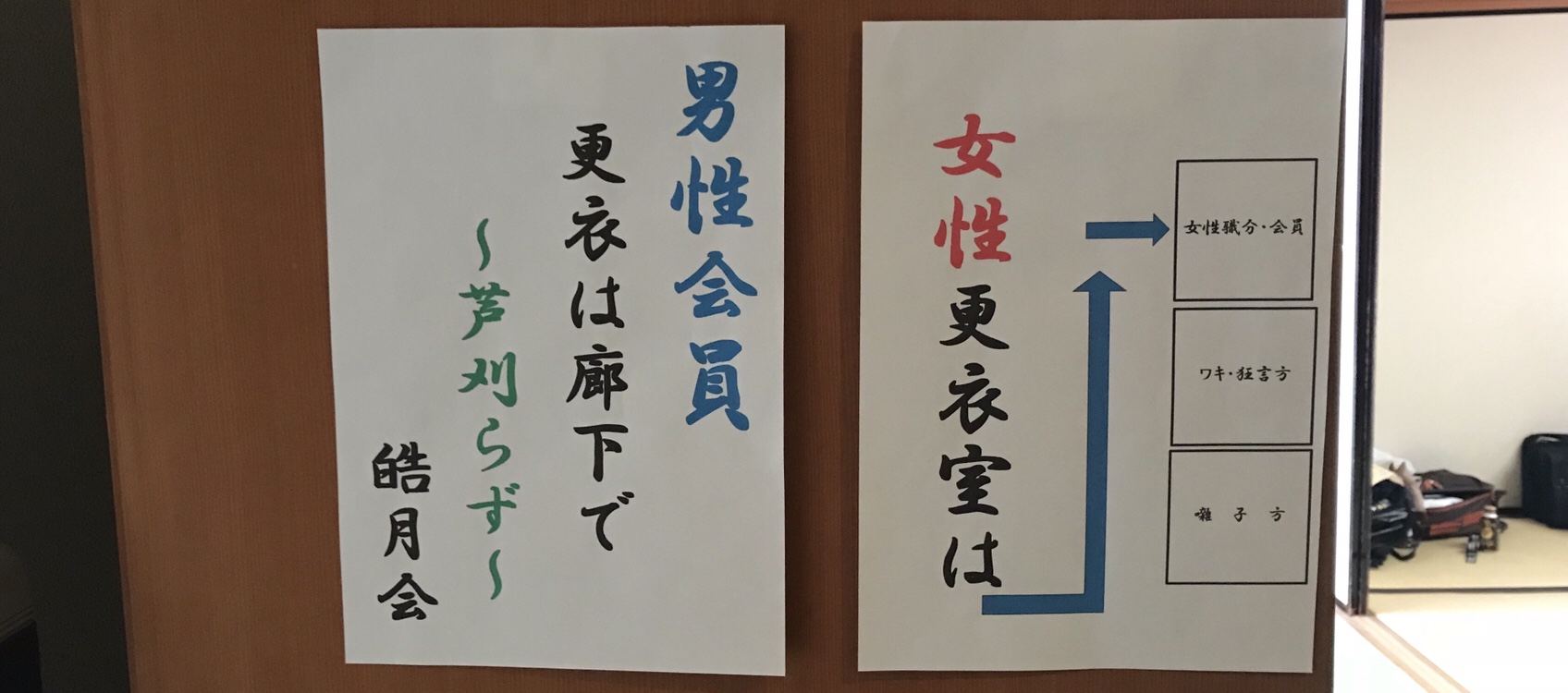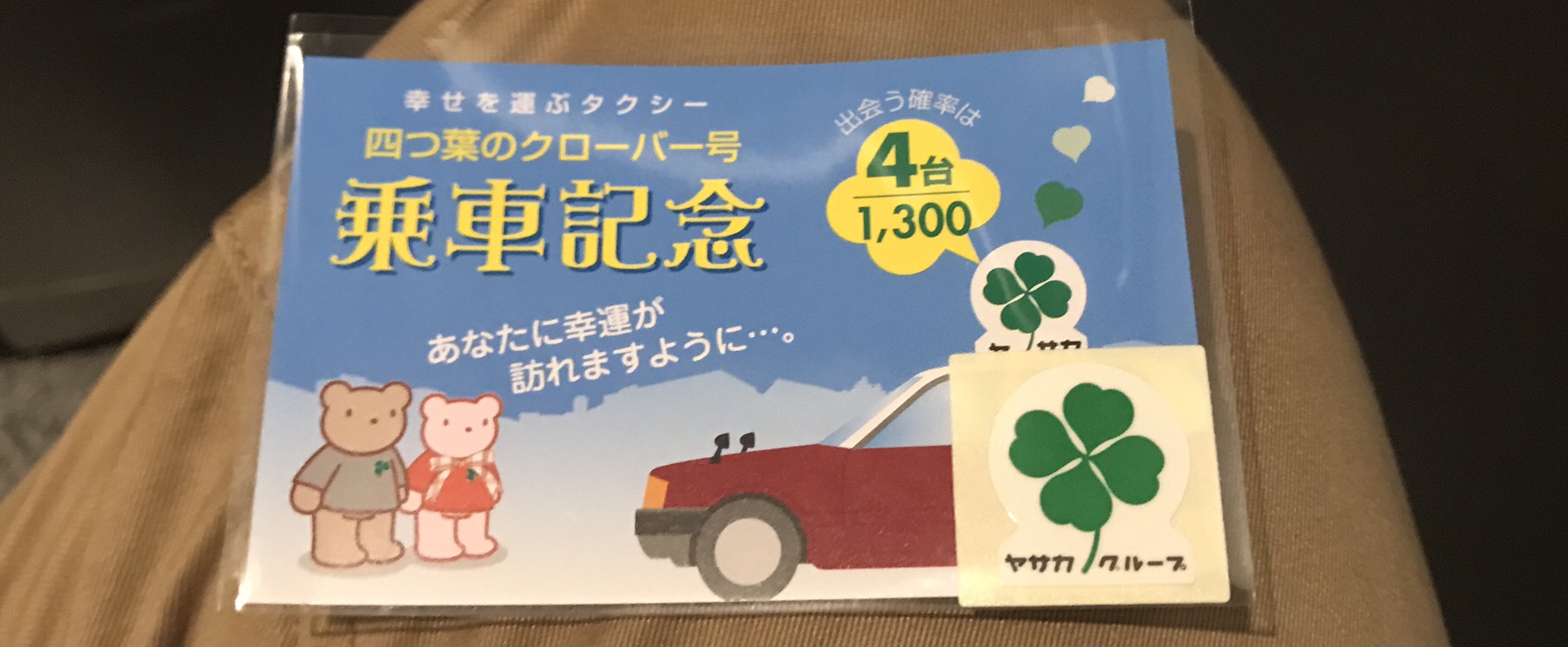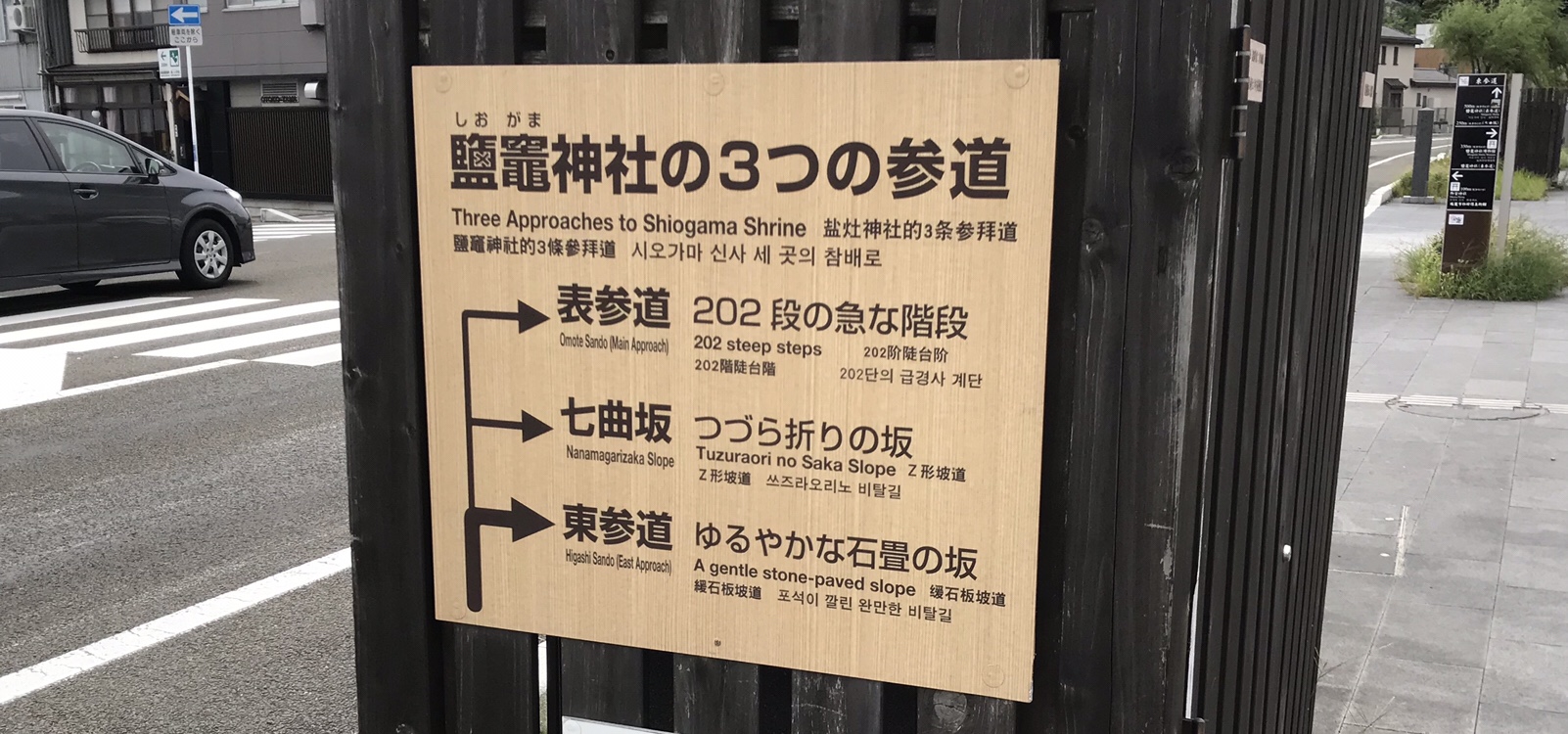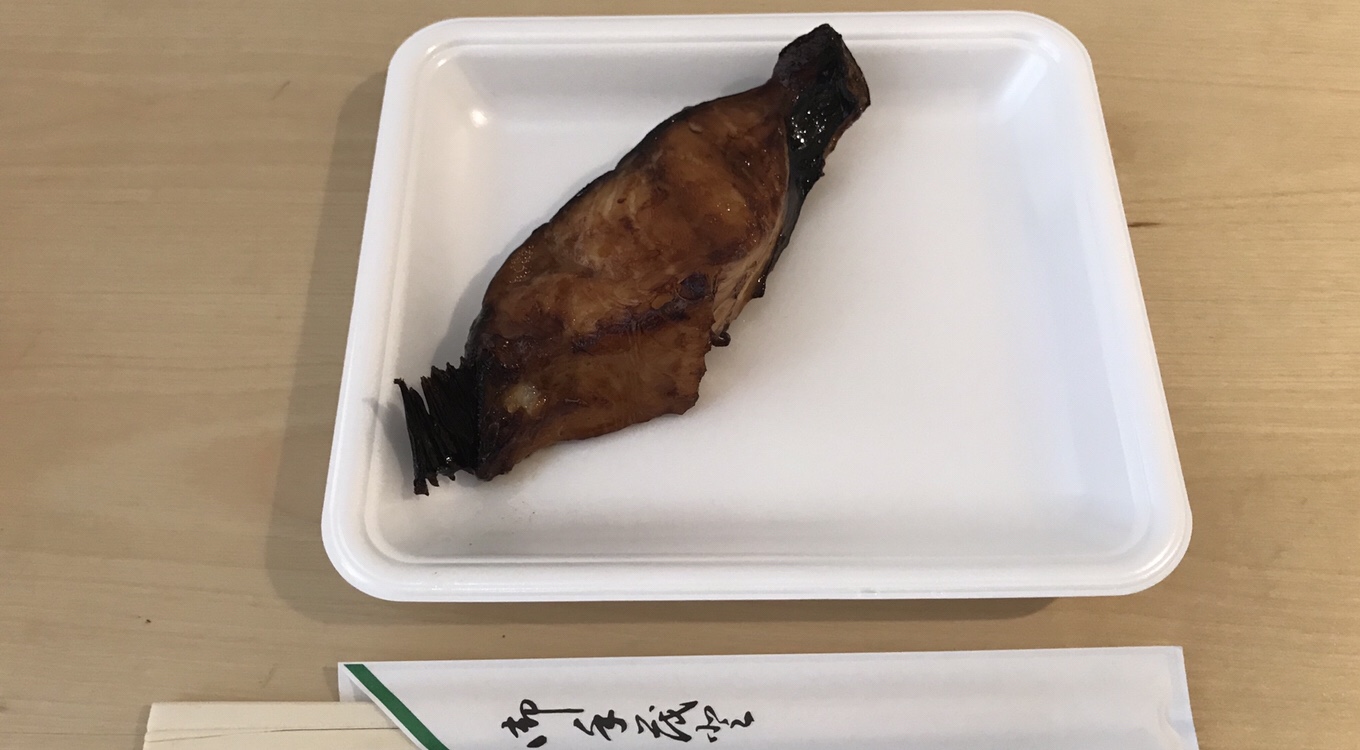昨日の夕方、私は京都大山崎から移動して松本駅に何とか辿り着きました。
.
駅から稽古場に向かう途中に”四柱神社”という大きな神社があります。
その前を通り過ぎようとしたら、境内に提灯が下がっていて、そしてとても沢山の屋台が並んでいます。
境内の方からは演歌歌手の歌声で、何故か「コーヒールンバ」が聴こえて来ました。(昨日10月1日は”コーヒーの日”だったようです)
.
稽古時間は迫っていたのですが、ちょっとだけ覗いてみたい!という誘惑に抗えずフラフラと神社に足が向いてしまいました。。
.
.
境内にはノスタルジックな夜店が軒を連ね、ステージの上では演歌歌手が今度は自分の持ち歌を歌い始めて、小ぢんまりした客席には近所のおじいさんやおばあさんが集まっていました。
.
なんだか子供の頃にタイムスリップしたような昔ながらのお祭りです。
しみじみと「良いなあ…」と思いつつも、写真を撮る間も無く、お祭りの名前も聞かずに稽古場へと急ぎました。
.
.
そして稽古を始めてすぐに扉が開き、中学生の女の子が元気良くやって来ました。いつもはお母さんと一緒に来る筈が、何故か後ろからもう1人同級生らしい女の子が入って来ます。
「もしかして見学かな?」と思ったら、
「先生!今日は早めに稽古をお願いします!終わって友達と四柱神社のお祭りに行くんです!」
…成る程。さっきのお祭りですね。
地元の子供達もこぞって集まるお祭り。ますます魅力的です。
会員さん達にお祭りの名前を聞いてみました。
四柱神社の”神道祭”という昔から続くお祭りで、松本に秋の訪れを告げる風物詩的なお祭りだそうです。
.
小学1年生の男の子も、稽古を終えて一旦「さよなら〜」と帰ってからしばし経って、「金魚獲れた〜❗️」と嬉しそうに戻って来ました。
手にしたビニール袋の中には、小指ほどの金魚が数匹ヒラヒラしています。
.
.
稽古を終えて、もうやっていないだろうと思いながら四柱神社の方に歩いて行くと、なんとまだまだお祭りは続いていました。
しかも夕方よりも遥かに多い人集りです。
.

金魚掬いの夜店。さっきの男の子はここで金魚を獲ったのでしょう。
他にも…
.

射程や、
.

ヨーヨー釣り。
そして…
.

昨日も載せたお面屋さん。
お面の中には…

現代風のキャラに混じって、昔ながらの狐のお面や、なんと「般若」と「小面」の姿も!
.
.
松本に何年も通いながら、今回初めて知った”神道祭”。
また松本での毎年の楽しみが増えてしまいました。