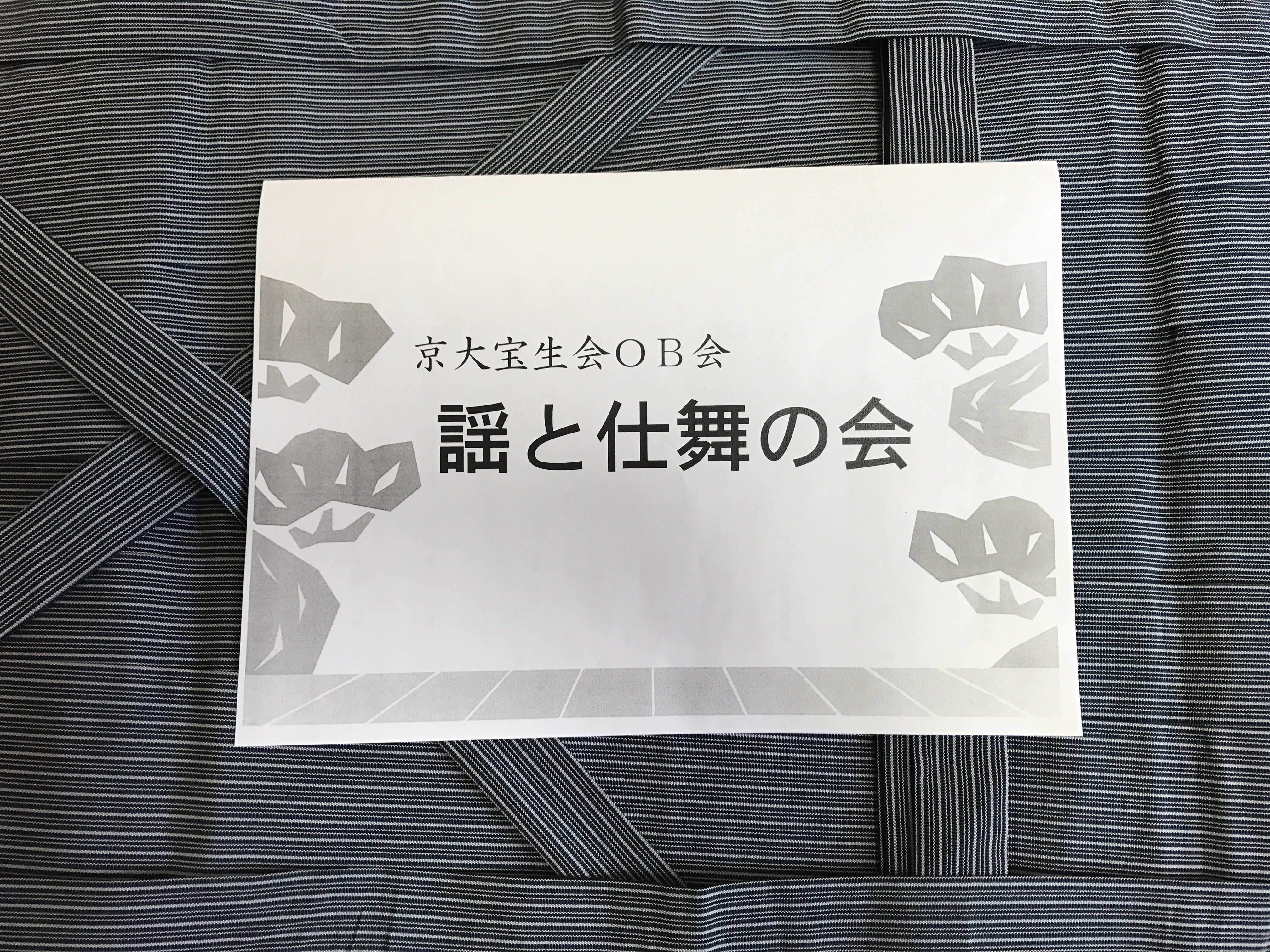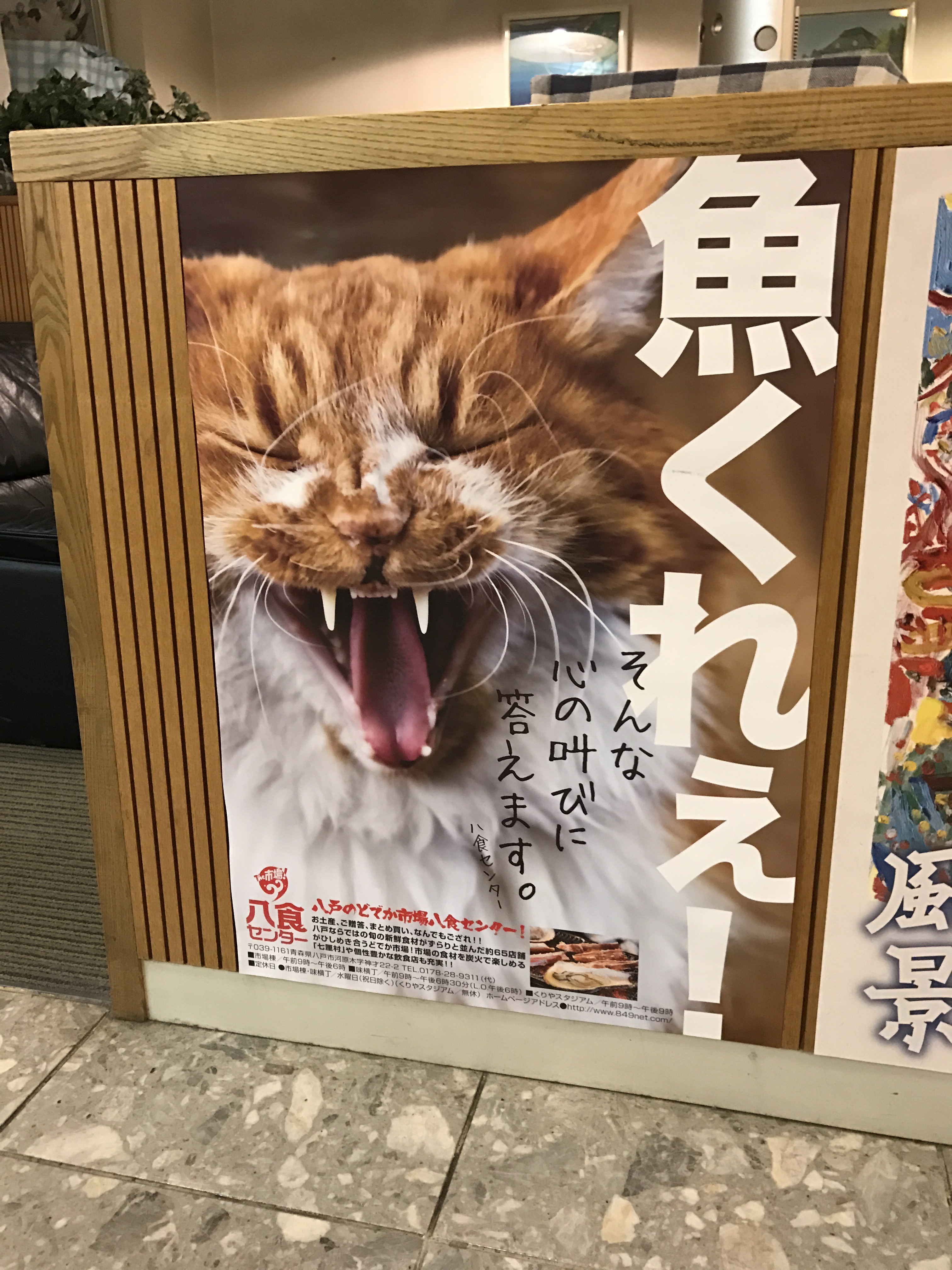昨日の京大OB会十和田大会では、「錦木」「遊行柳」「善知鳥」といった素謡が出ました。
これは東北地方の「ご当地ソング」とでも言える曲目で、秋田、福島、青森などが曲の舞台になっています。
ある場所が舞台の曲を、その土地に行って謡うのは、その曲への理解が一層深まる気がします。
また東北地方を旅する前にこれらの曲を勉強することで、東北地方の風土を理解する助けになる気もするのです。
「東北」の素謡が出たのはちょっと笑いましたが。。
「善知鳥」の素謡では、最後の仕舞の部分を謡わずにとっておいて、今日の観光で青森市内の「善知鳥神社」に行った時に境内で謡って奉納するということでした。
私は水道橋の月並能に出演する為に観光には参加しませんでしたが、善知鳥神社で謡う善知鳥は、また思い出に残るものだったろうと思います。
「ある曲の舞台に行って、その曲を謡って楽しむ」というのは、交通機関が発達した現代における「謡十徳」のひとつだと言えるのではないでしょうか。