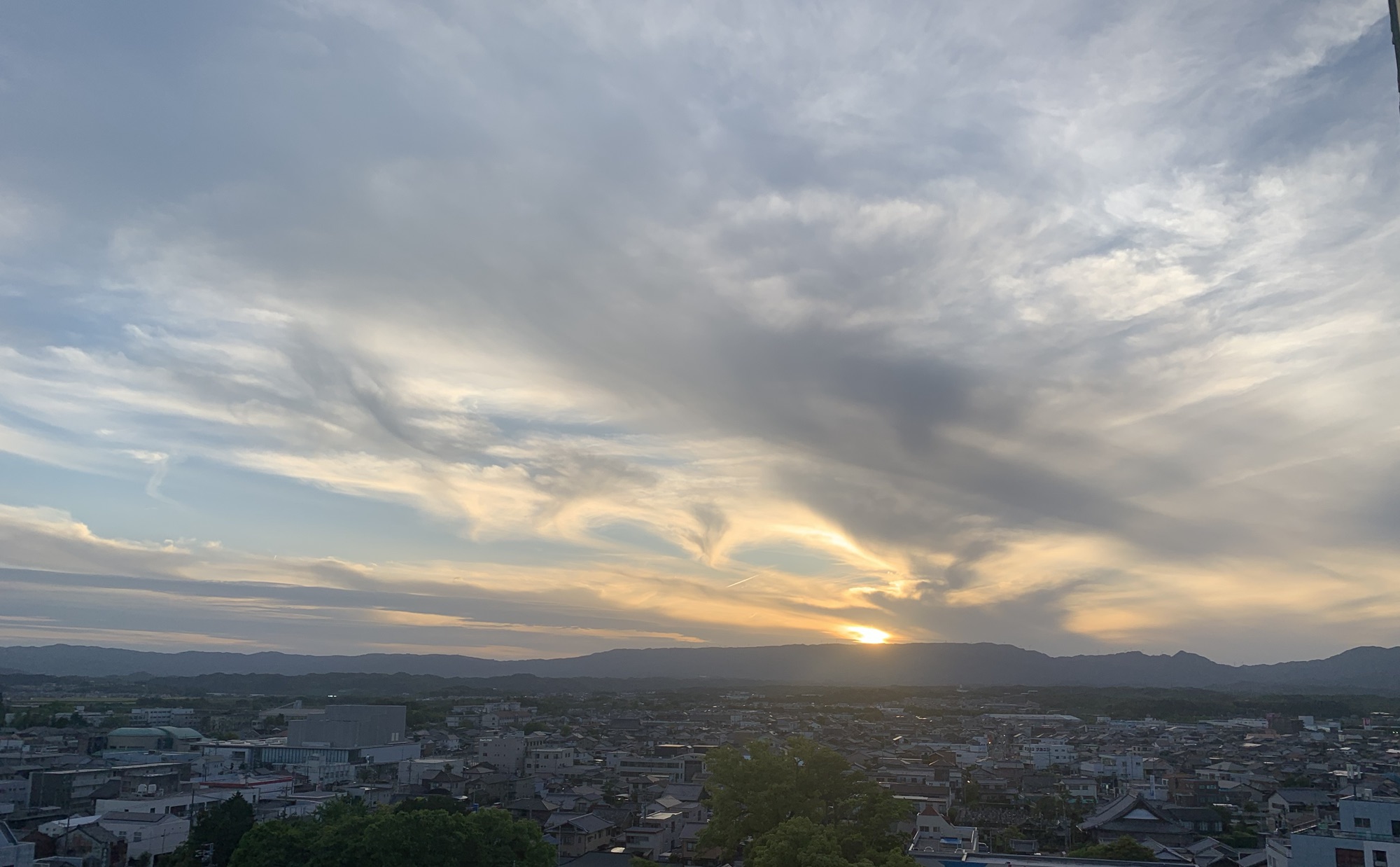私が京大宝生OB会の集まり(主に宴会)に参加する時には、たいていが舞台を終えてからの途中参加になりました。
そんな時、会場に到着すると真っ先に声を掛けてくださるのが佐藤孝靖先輩でした。
・
「オウッ!澤田クンッ、こっちこっち!」
そして私が席に落ち着くと、
「それじゃあ澤田君よ、ひとつ次の舞台の宣伝も兼ねて、一言お願いしますよ!」
と自然に宣伝の機会を作ってくださいました。
・
・
私だけでなく、久しぶりにOB会に来られた方などにも、
「オイッ、○○君!久しぶりに謡ったにしては中々に味のあるワキだったよ!何か感想を一言!」
という風に、チャキチャキとした中にも細やかな心配りと親愛の情が感じられる独特の口調が大変魅力的でした。
佐藤先輩の軽妙な仕切りで、京大宝生OB会の宴会はいつも笑いの絶えない楽しいものになりました。
・
・
私の舞台や澤風会大会の折には、毎回佐藤先輩が京大宝生OB会の皆様の参加の取りまとめをしてくださいました。
またコロナ禍で能楽師の仕事が激減した時には、「zoomでの団体稽古を試験的にしてみませんか?」と何人かのOBの皆さんを集めてzoom稽古を設定してくださり、おかげ様で何とか生活を維持する事が出来ました。
・
・
この1月に私が「翁」を勤めた時にも、これまでと変わらずにチケットの取りまとめから後席まで全てを取り仕切っていただき、久々に大勢のOBの皆さんとの楽しい後席になりました。
・
そのすぐ後に、入院手術をされることになったと伺いました。
それでも3月末には、退院が決まったというお元気そうなメールを拝読して、また次のOB会でお会いするのを楽しみにしておりました。
・
・
しかし一昨日のこと、佐藤先輩が御自宅で眠るように息を引き取られたとの報せを受け取り、未だ信じられない思いでおります。
・
4月半ばに退院された後は、6月のOB会での復帰に向けて、気合を込めてリハビリに励んでおられたという事です。
京大宝生会の精神を正に体現されたようなお人柄と人生を、最後の最後まで全うされた偉大な先輩でした。
・
きっと今頃は、
「イヤァどうも!お久しぶりです!」
と小川先生や植田竜二先輩などと、あの軽妙な口調で楽しくお話しされている事でしょう。
・
心よりご冥福をお祈りいたします。
また誠にありがとうございました。