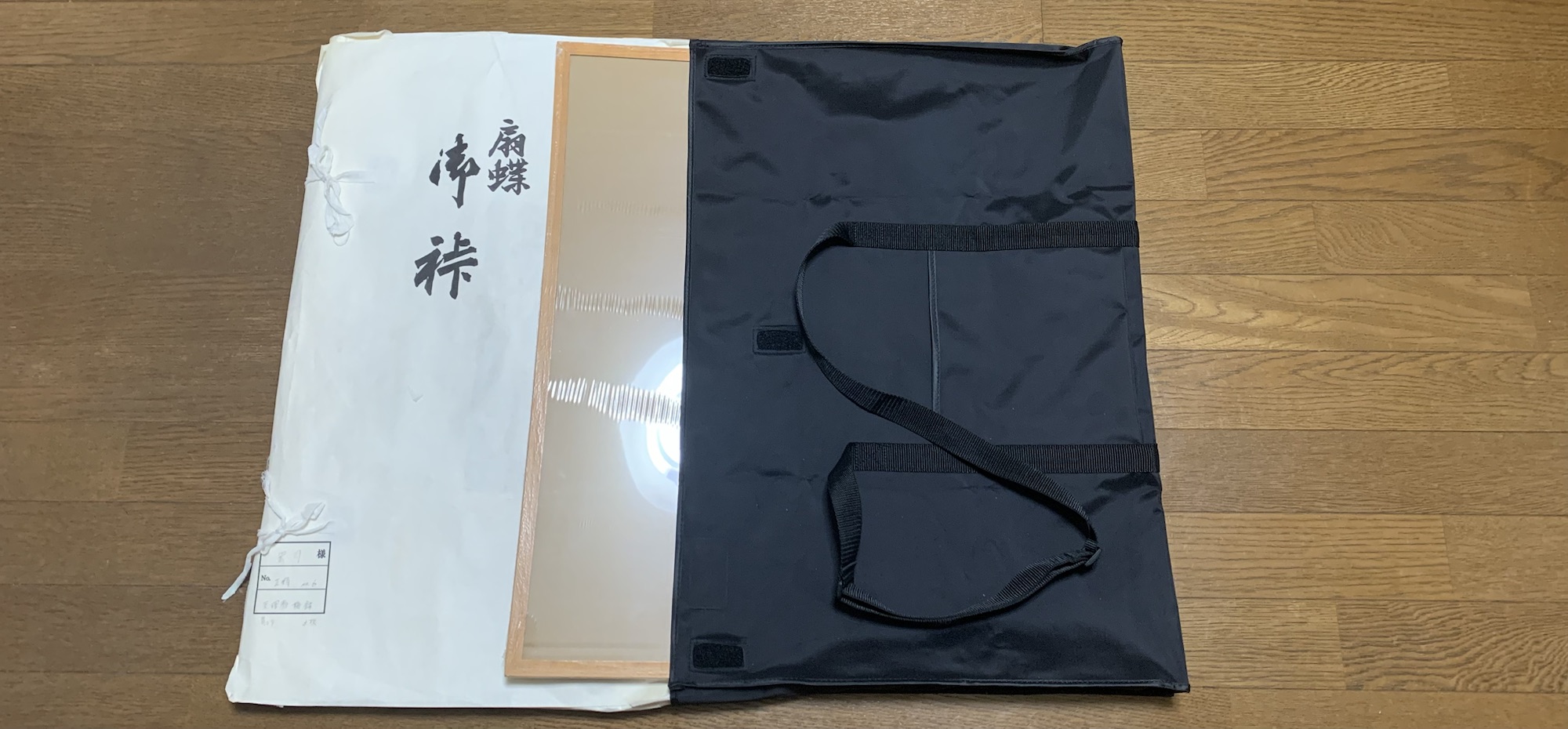1月16日にこのブログを再開してから1か月が経ちました。
なんとか途切れずに書き続けております。
・
今回ブログ再開の告知などは全くしていないにも関わらず、何人かの方に、
「ブログ再開されたのですね、いつも読んでいます」
と温かいお言葉をいただきました。
何よりの励みになります。ありがとうございます。
・
・
今後も私の小さな日常の出来事をポツポツと書いて参りたいと思います。
またいくつかあった”シリーズ”もぼちぼち再開するつもりです。
・
「亀岡の花々」シリーズは、間もなく春の花が咲き始めたら再開します。
「隙間花壇」は実はコロナ禍の間に雰囲気が大分変わって、洋風のお洒落な花壇になっております。私としては以前の自然な感じが良かったのですが、こちらも一度今の姿をご紹介したいと思います。
・
「読んだ本の話」も書いていきたいです。
相変わらず”遅読”で”並行読み”です。
今は、
①戸川幸夫(イリオモテヤマネコを発見した動物文学作家)著のシートンの伝記
②新田次郎著「孤高の人」
③椎名誠の「怪しい雑魚釣り隊シリーズ」
などを読んでおります。
中でも新田次郎「孤高の人」は久しぶりに本にグイグイと引き込まれていく感覚を味わっております。
・
・
このように、能楽には全然関わらない内容も多いブログではありますが、頑張って書いて参りますのでどうか今後ともよろしくお願いいたします。