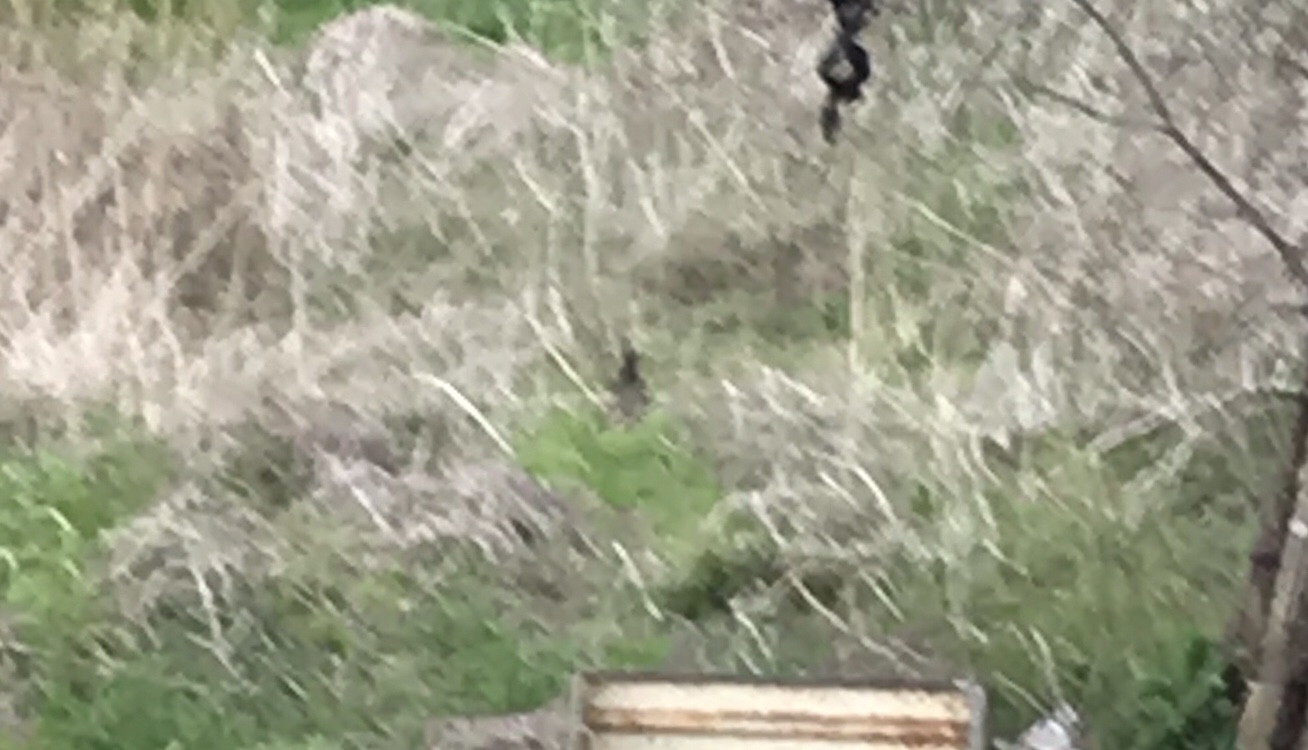昨日の古本市で購入した「曽我物語・物語の舞台を歩く」を早速パラパラと読んでみました。
.
能「夜討曽我」において、曽我五郎・十郎兄弟は遂に念願の仇討ちを果たしますが、それは建久4年(1193年)5月28日の深夜の事でした。
私が夜能で「夜討曽我」のシテを勤めるのが5月25日。とても近い日どりです。
.
.
本によると、この夜討があった「5月28日」に合わせて、曽我兄弟ゆかりの地では色々な行事が行われるようです。
.
.
JR御殿場線の下曽我駅で降りると、その一帯がその昔「曽我の里」と呼ばれたそうで、曽我氏の菩提寺である「城前寺」があります。
この城前寺で、毎年5月28日に「曽我の傘焼き祭」が行われてきました。
.
「傘焼き」とは、曽我兄弟の夜討の時に、兄弟に斬りつけられた人達が火のついた蓑や笠を投げ出して辺りを明るく照らしたというエピソードに因んだ行事だそうです。
前夜祭の27日には奉納謡曲大会も催されるとのこと。きっと「曽我物」シリーズが謡われるのでしょう。
.
.
またJR身延線の入山瀬駅の周辺は古くは「駿河国小林郷」と呼ばれ、実は曽我兄弟が神として祀られている土地なのです。「曽我八幡宮」がその社で、近くには曽我兄弟を供養する「曽我寺」もあります。.この曽我寺を中心にして、5月下旬には「曽我まつり」が行われます。境内にある「曽我兄弟の墓」の前などで供養会があった後、「曽我八幡宮」、「五郎の首洗い井戸」、「虎御前(十郎の恋人)の腰掛石」などを巡る巡回供養があるそうです。.
.
ともに5月25日の夜能が終わった後の行事なのが残念ですが、「曽我の里」がある下曽我や、「小林郷」がある入山瀬を、何とか本番までに一度訪ねてみたいと思っております。