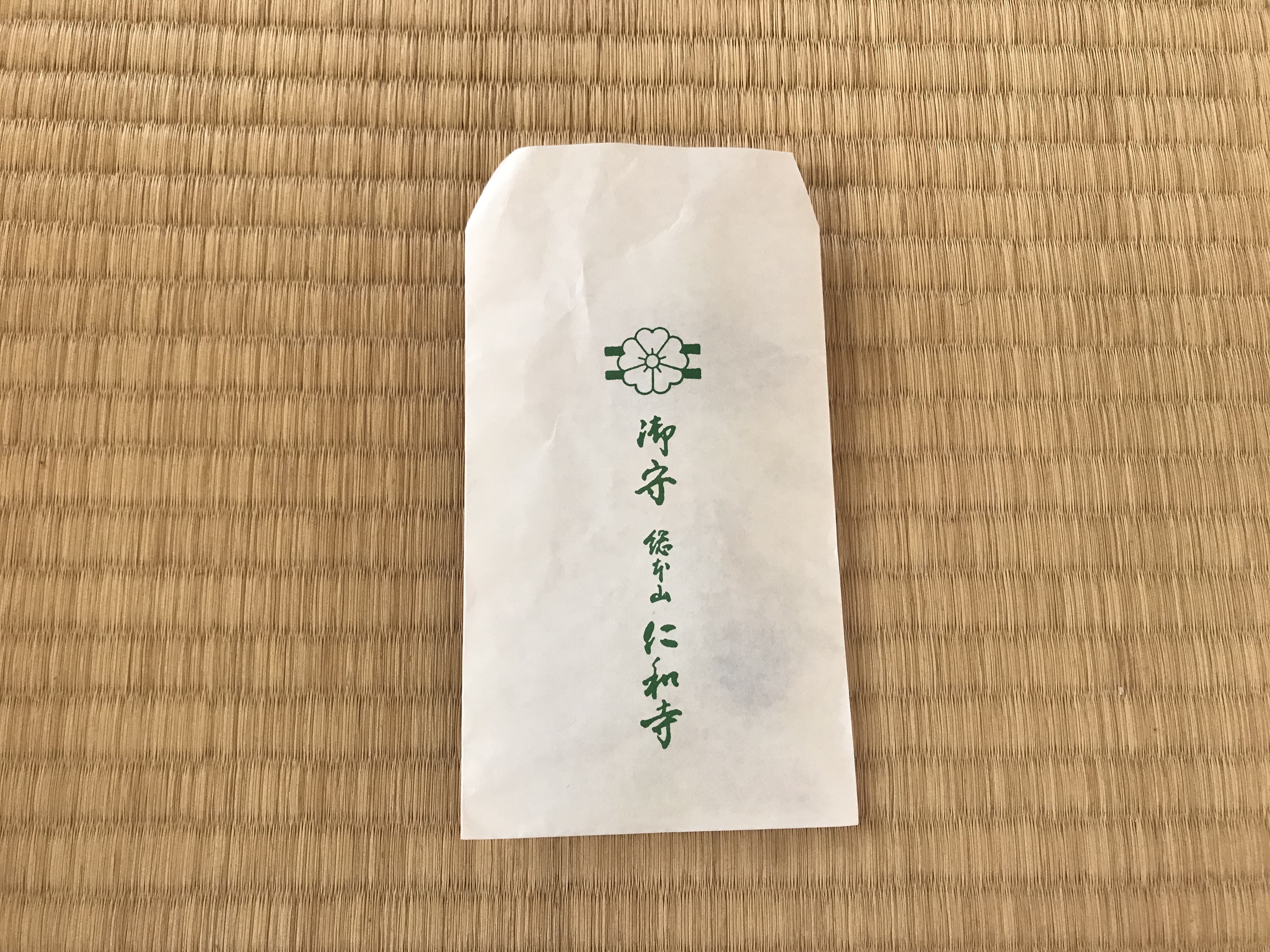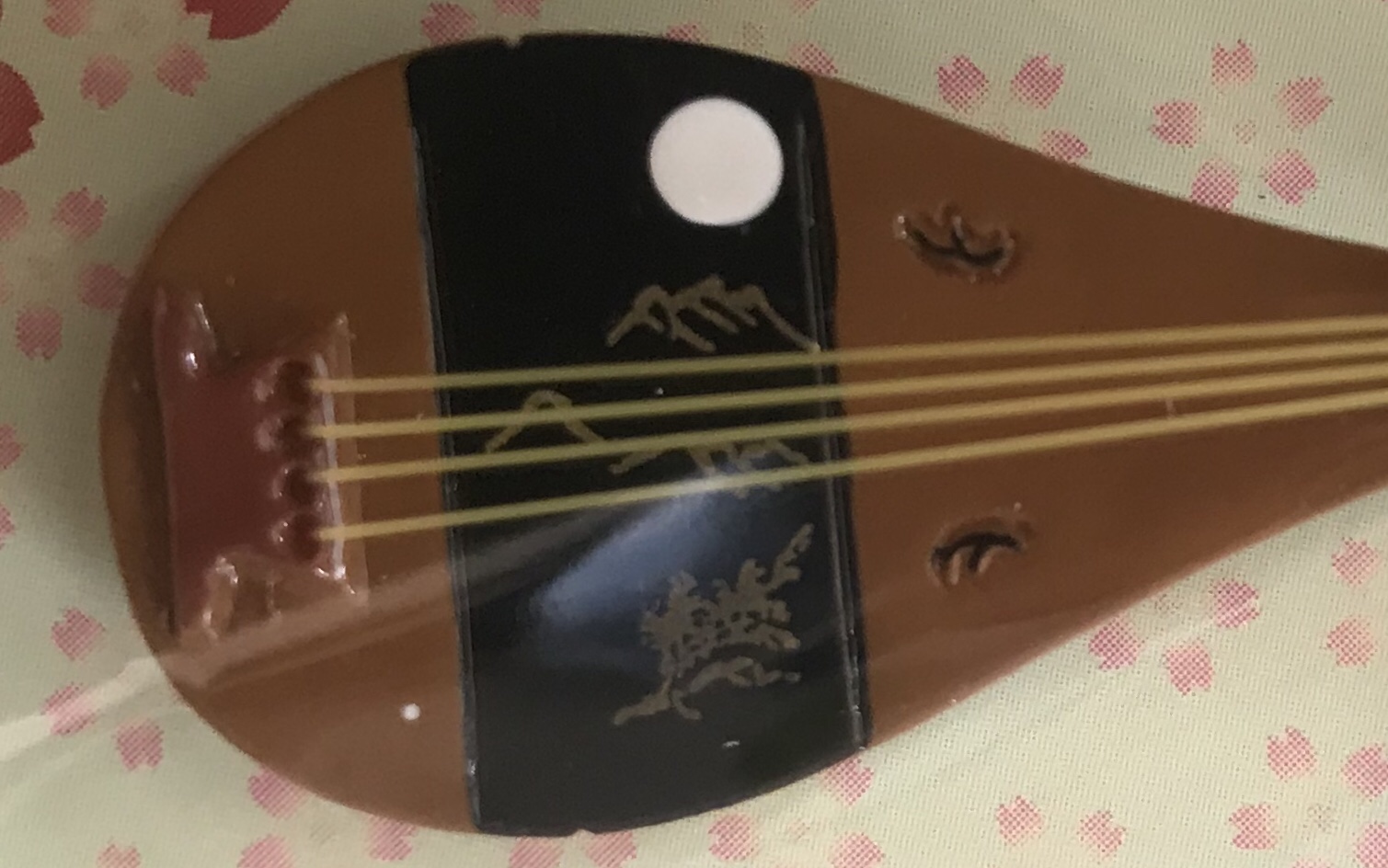年末には「今年最後の〜」というのを色々書きましたが、今度は「今年最初の…」という番です。
.
今日は「今年最初の新幹線」に乗りました。
と言っても珍しく仕事ではなく、三重県の実家に久しぶりに日帰りで帰郷するために乗ったのです。
.
私が生まれたのは、当時は三重県久居市と呼ばれていて、今は三重県津市久居となった場所です。
名古屋で新幹線を降りて近鉄電車に乗り換え、1時間ほどで久居駅に到着します。

.
.
駅から徒歩10分の所にあるもう築80年にもなる実家をリフォームして、今は父親が住んでいます。
会うのは去年春の「郁雲会澤風会」以来となる父親は、幸い元気でした。
暫し話をして、私が「ちょっと散歩に行きたい」と言うと「じゃあ一緒に行こうか」
.
.
父親と2人で散歩するなど本当に珍しいのですが、実家の近くには特に有名な観光名所があるわけでもありません。
しかし私が行ってみたい場所は決まっていました。
.
ぶらぶらと歩き出して3分ほどで「久居農林高校」の横を抜けると、急に視界が開けてきます。

この先は、とにかくだだっ広い田んぼとその向こうに見える山々だけの風景なのです。
.
.

ずっとこんな感じ。
.
.

山々も雄大で急峻な山脈、とは正反対の、低くてなだらかな山並みです。
上の写真奥に薄っすら見える山などは、布を広げて置いたように真っ平らに広がる低い稜線を持つために「布引山」と言われています。
.
しかしこの「特に強い印象は受けないけれど何となく長閑な風景」というのが私はとても好きなのです。
他の土地でも、広い田んぼの向こうになだらかな山が見えるところがあると「ああ、久居みたいで良いなあ」と思ってしまいます。
そして久居に帰るとこの風景を見ずにはいられなくて、ついその方向に散歩に行ってしまうわけです。
.
.
それにしても父親は年の割に非常に元気で、結局万歩計アプリで1万歩近くを一緒に歩いてしまいました。
.
その後も今度は車に乗って久居名物「野辺の里」という昔ながらの和菓子を買いに行ったりして、すっかり日が暮れるまで動き回ってからまた歩いて晩御飯を食べに行きました。
.
実家のすぐ斜め向かいには久居市役所があったのですが、その大きな建物を壊して大規模な工事が始まっていました。
私「ここは何になるの?」
父親「新しく多目的ホールを作るらしいね」
横を通ると完成予想図が貼ってあり、かなり大きなホールになるようです。
.
完成すると実家の目の前が多目的大ホールになるわけで、「なんとかそのホールで能楽公演をしたいなあ」
というのが新しい目標の一つになりました。
.
まだまだ元気な父親に、今年の私の舞台を見てもらう、というのも小さな目標でしょうか。
晩御飯をご馳走になった後に、私は父親と別れて東京への帰途に着きました。
しみじみと良い里帰りでした。