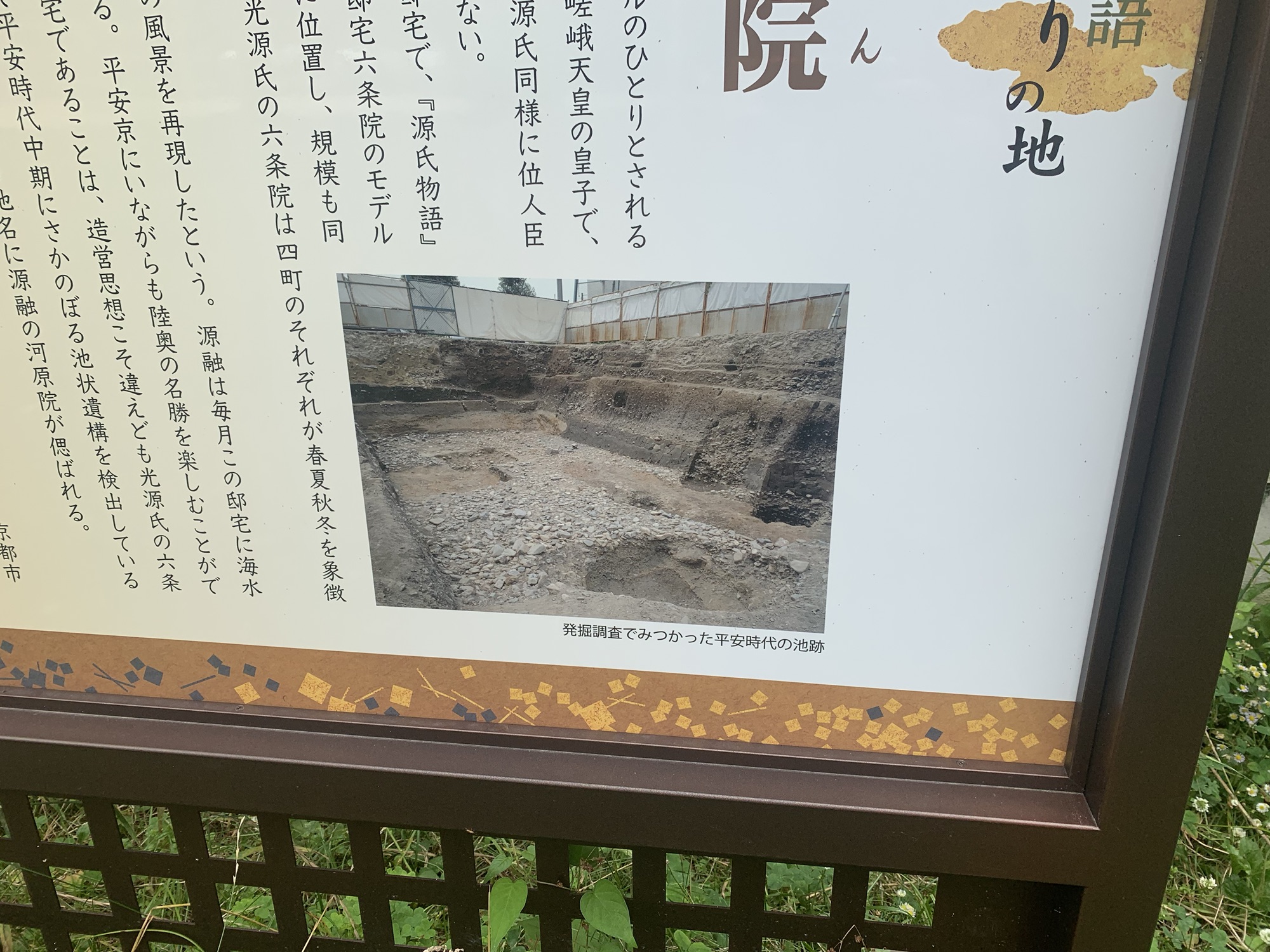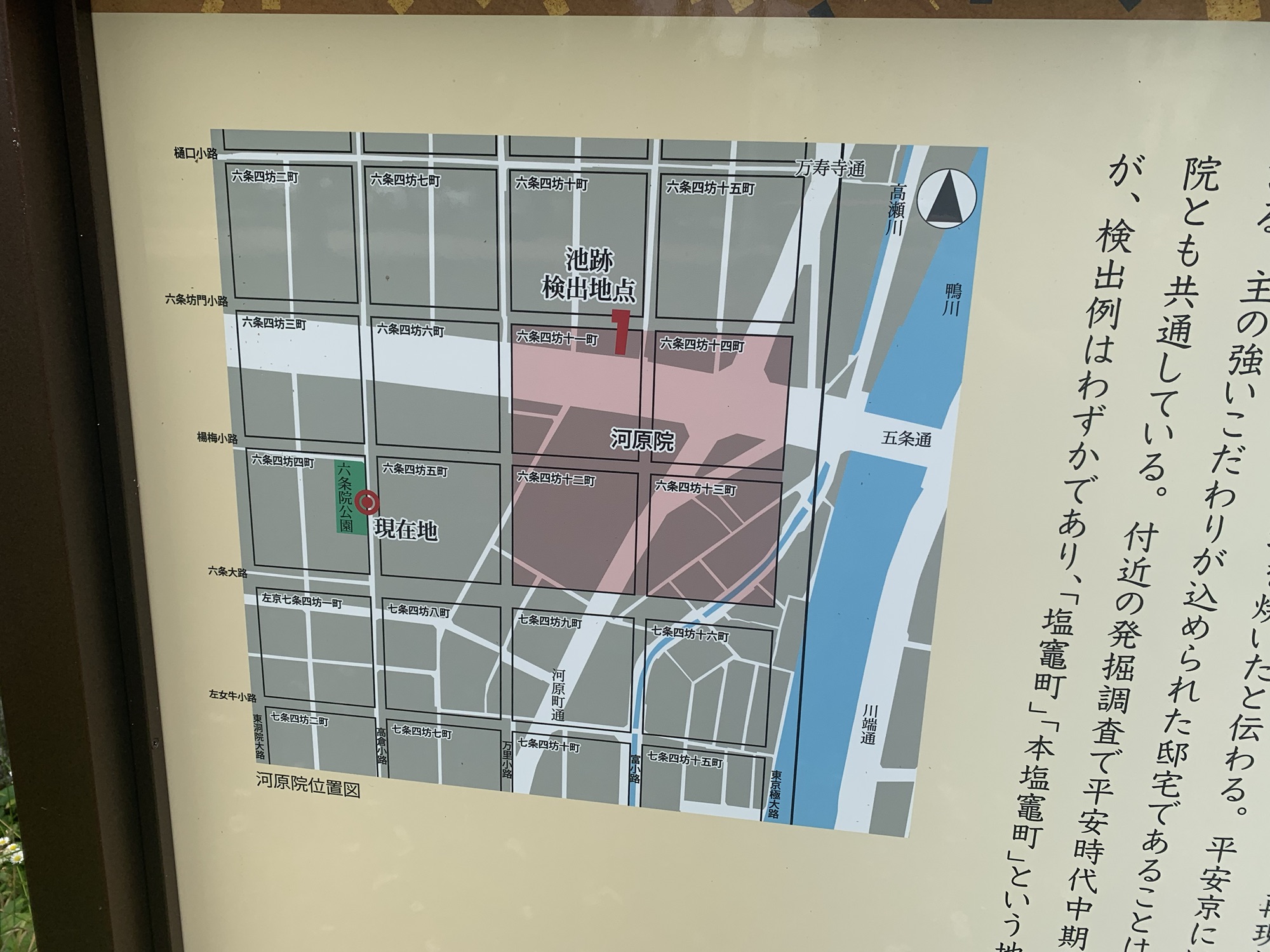先週、登山靴とザックの試運転で福島県の「信夫山」に行ってまいりました。
・
山を選んだ基準は、
「雨が降っていない山」
「駅から登山口へのアプローチが容易な山」
「東京から日帰りできる山」
というもので、
「能に関わりがある山」
という要素は全く考えておりませんでした。
・
・
そして東北新幹線の福島駅からほど近い「信夫山」に決めた訳です。
しかし、「信夫山」を登っている途中で何故か頭の中に
「いつまでとてか忍ぶ山 忍ぶ甲斐なき世の人の…」
という謡が浮かんで来ました。
・
何の曲だったかな…と少し考えて、能「藤戸」の初同(最初の地謡)だったと思い出しました。
とは言え「忍ぶ山」と「信夫山」は字が違います。
おそらく違う土地に「忍ぶ山」があるのだろうと思いながらも、登山の間中ぐるぐると「いつまでとてか忍ぶ山…」
という謡が脳内を回っておりました。
・
・
そして帰宅してから
「いつまでとてか しのぶやま」
という語句で念のため検索してみたのです。
・
・
結果は驚くべきものでした。
「いつまでとてか しのぶやま」
は紀貫之の和歌の一節で、陸奥の「信夫山」を詠んだものだというのです。
・
・
更に調べると、「信夫山」は90首もの和歌に詠まれた有名な歌枕だったようです。
不勉強で全く知りませんでした。。
・
・
またあの源融の和歌
「陸奥の しのぶもぢずり誰故に…」
は、信夫山がある辺りの「信夫」という地名を詠んだものだそうです。
・
もっと調べると、能「錦木」の冒頭のワキの次第に「信夫山」そのものが謡われておりました。
・
能楽とは全然関わりの無い基準で選んだ山が、結果的に能に最も縁の深い山のひとつだった訳です。
知っていて登れば、何か能楽と関わる史跡などが見つかったかもしれません。
いつか是非とも「信夫山」を再訪したいと思います。