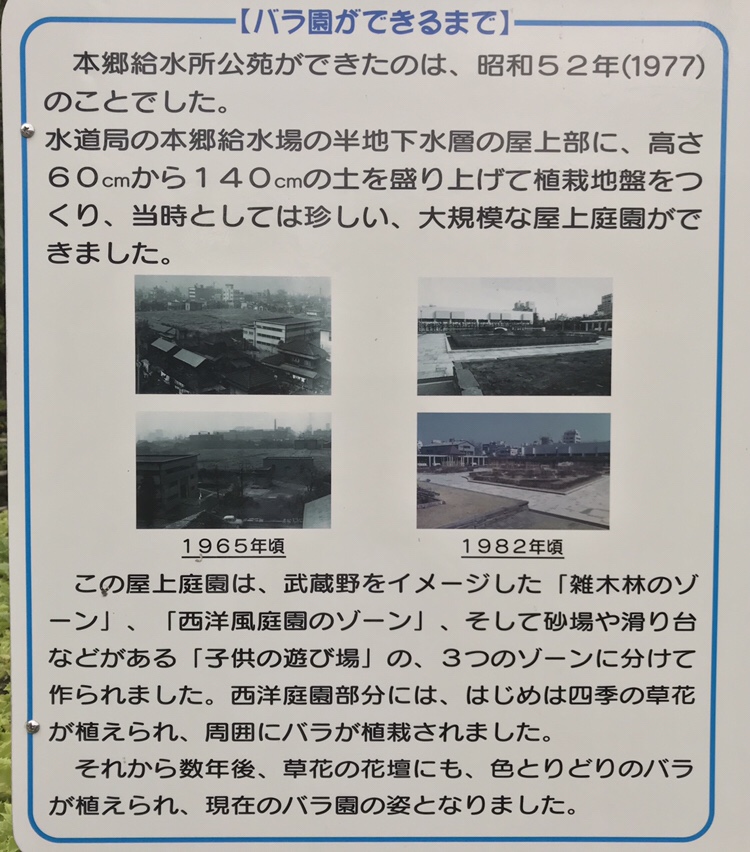「能舞台」は他の舞台とは異なる独特の構造をしています。
.
「橋掛り」と呼ばれる廊下のような構造が舞台から延びていて、その突き当たりには「揚げ幕」が垂れています。
.
.
この「揚げ幕」は、基本的には幕の下端に結び付けられた2本の長い竹によって上げ下げをしますが、実は幕の開け方にはいくつかの種類があります。
.
①2本の竹を垂直に立てて、幕を全開にする。
②竹ではなく幕の片側の布を持って、人間が1人通れるだけの隙間を開ける…「片幕」と呼ばれる。
③竹を少しだけ持ち上げて、半分くらい揚がった幕の下をくぐるようにして、後見が作り物などを舞台に出す…「半幕」と呼ばれる。
④2本の竹を交差させて束ね、それをクルクルと巻き上げて幕を半分ほど揚げ、シテの姿を少しだけ見せる…これも「半幕」と呼ばれる。
.
.
先ずシテ、ワキ、ツレは①の開け方で舞台に登場します。
狂言も大半は①で出ますが、間狂言では②の「片幕」で登場することがあります。
囃子方は、能の時は②の「片幕」で、舞囃子の時は切戸から舞台に出ます。
③は例えば能「黒塚」の「枠かせ輪」や、能「松風」の「汐汲み車」などの作り物を舞台に出す時に用いられる開け方です。この「半幕」で舞台に出した作り物は、必ず切戸から引く決まりです。
また極めて例外的に、能「錦戸」のツレはこの「半幕」を使って舞台から退場します。
.
.
.
…そして見所のお客様が最も注目するべきは④の「半幕」なのです。
この④の開け方をするのは、数ある能の中でもほんの数曲に限られています。
.
実は昨日の五雲会で演じられた能「石橋」も、この④が用いられる曲のひとつでした。
.
能「石橋」で、前ツレが①の開け方で静かに舞台から退場した途端に、囃子方が「乱序」という激しい囃子を打ち出します。
この掛け声がまるで「獅子の咆哮」のようで大変に迫力があり、お客様の視線は一瞬囃子方に集中します。
.
しかしながら、この瞬間に幕の内側では大きな動きが行われているのです。
.
ツレが退場して幕が閉まった直後に、後見は瞬時に竹を交差させて束ね、シテ「獅子」が幕の際ギリギリまで素早く歩み出ます。
そして「乱序」の囃子が始まった瞬間、2人の後見が幕をクルクルと巻き上げ、シテの首の下までが見えるようにするのです。
.
この「半幕」が上がっているのは、笛の「ヒシギ」の間の僅か数秒だけで、ヒシギが終わるとまたクルクルと幕が下されます。
.
お客様の大半、特に「脇正面」のお客様は、昨日も殆どがこの「半幕」を見逃されていたと思われます。。
.
.
他の曲では、能「船弁慶 後ノ出留ノ伝」や能「小鍛冶 白頭」、また能「望月」の後シテなどが、この④の「半幕」で一瞬だけそのシルエットを見せるのです。
.
.
能楽は知れば知るほど面白いと言われますが、この幕の揚げ方のバリエーションもやはり、知ってからご覧になった方がより舞台を楽しめると思われます。