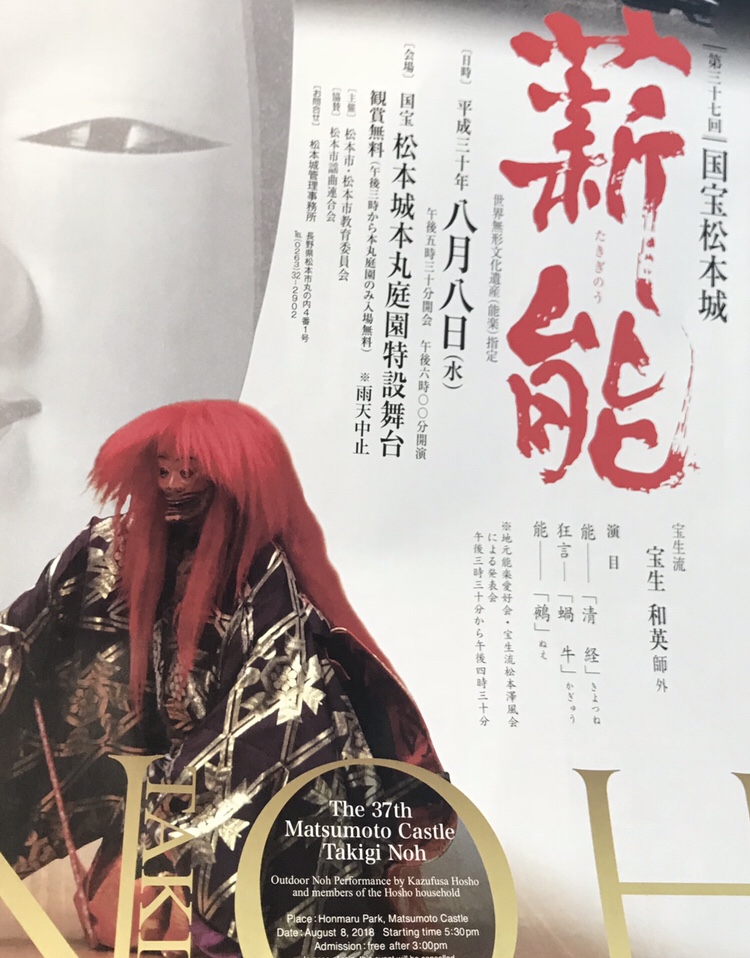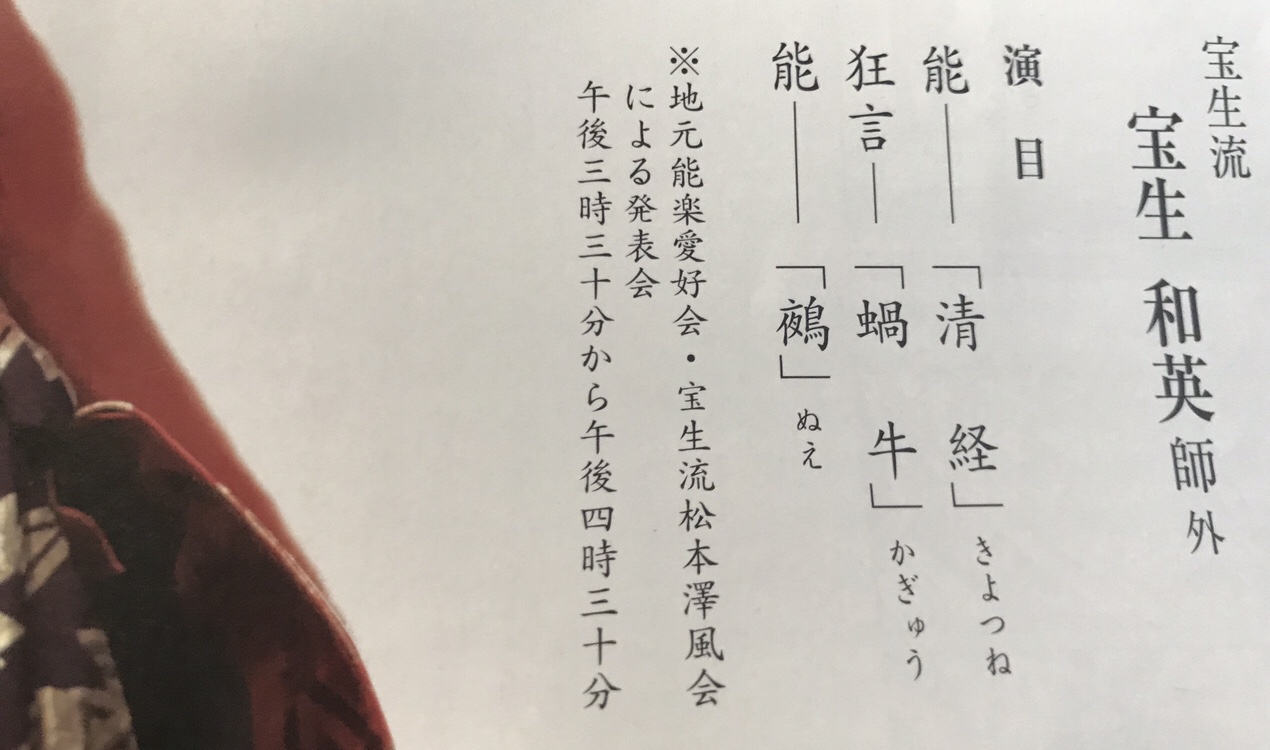連日猛暑が続いております。。
能楽が生まれた室町時代の頃には、きっとこんな猛暑は無かったのだろうと思って、ちょっと調べてみました。
.
すると、確かに室町時代から昭和に入るくらいまでの期間は現代よりも気温の低い状態だったようです。
しかし意外なことに、それより以前の平安時代や鎌倉時代は、今よりもむしろ平均気温が高かったらしいのです。
.
能楽は主に平安時代や鎌倉時代のエピソードを題材にして作られています。
そういえば、能の曲の中には頻繁に「雷」や「稲光」、「にわかに振り来る雨」といった表現が出て来ます。
.
昨日謡った能「舎利」では、今まで晴天だった空が急に掻き曇り、泉涌寺舎利殿の辺りが稲光に包まれます。
そして前シテ「足疾鬼の化身」は、その稲妻の光に紛れて牙舎利を奪って逃走するのです。
.
これは現代で言う「ゲリラ豪雨」のような天気の急変を表現しているのかもしれません。
能「舎利」の典拠となった「太平記」が出来た時代は、意外に現代と似たような「猛暑」や「台風」、「ゲリラ豪雨」などがあった可能性もあるのです。
.
.
だからといってここ数日の猛烈な暑さが和らぐ訳ではありません。。
しかし、エアコンも冷蔵庫も無い時代に暑さに耐えていたであろう平安時代や鎌倉時代の人々を思って、この暑さをなんとか乗り切って参りたいと思います。