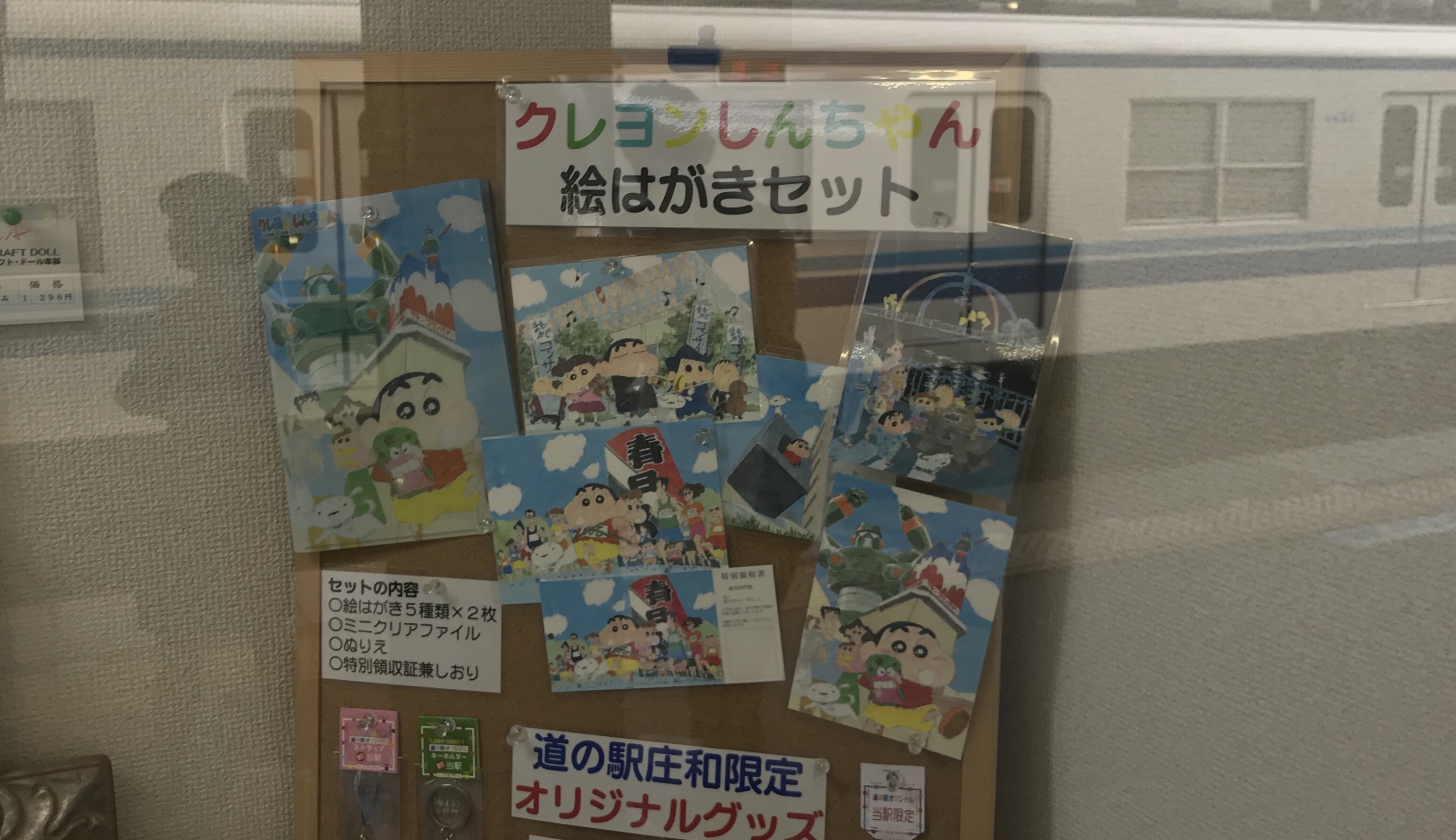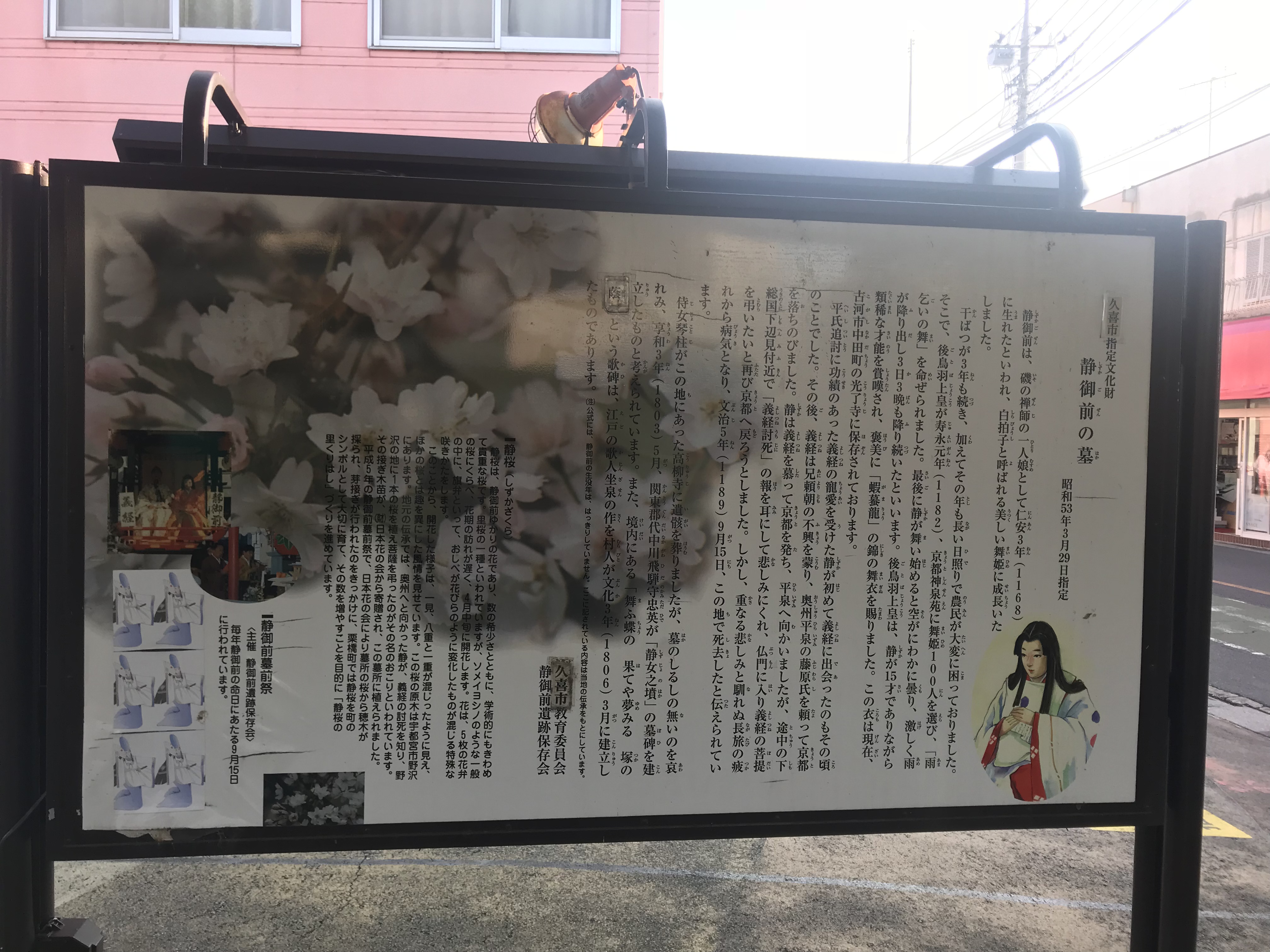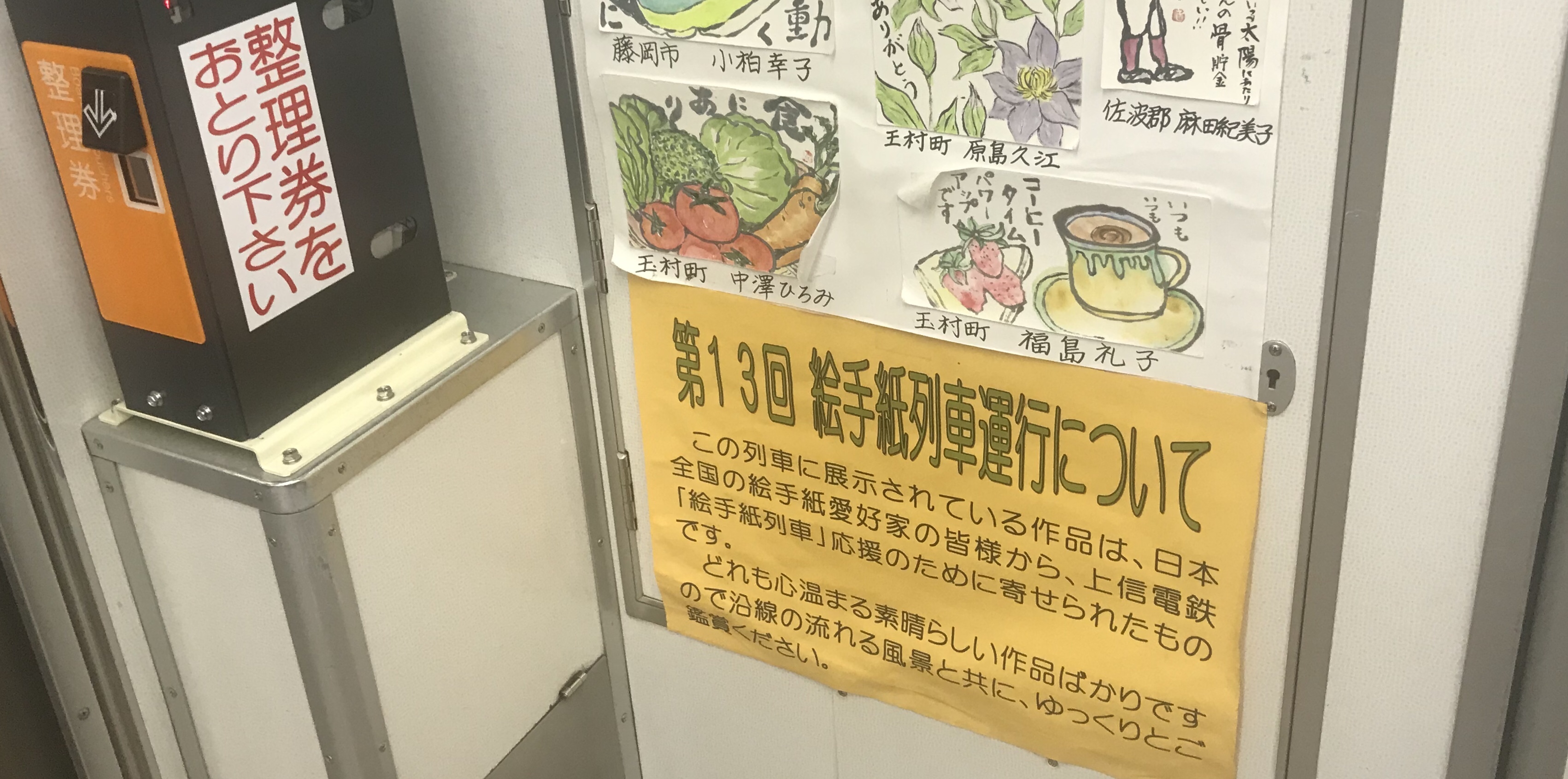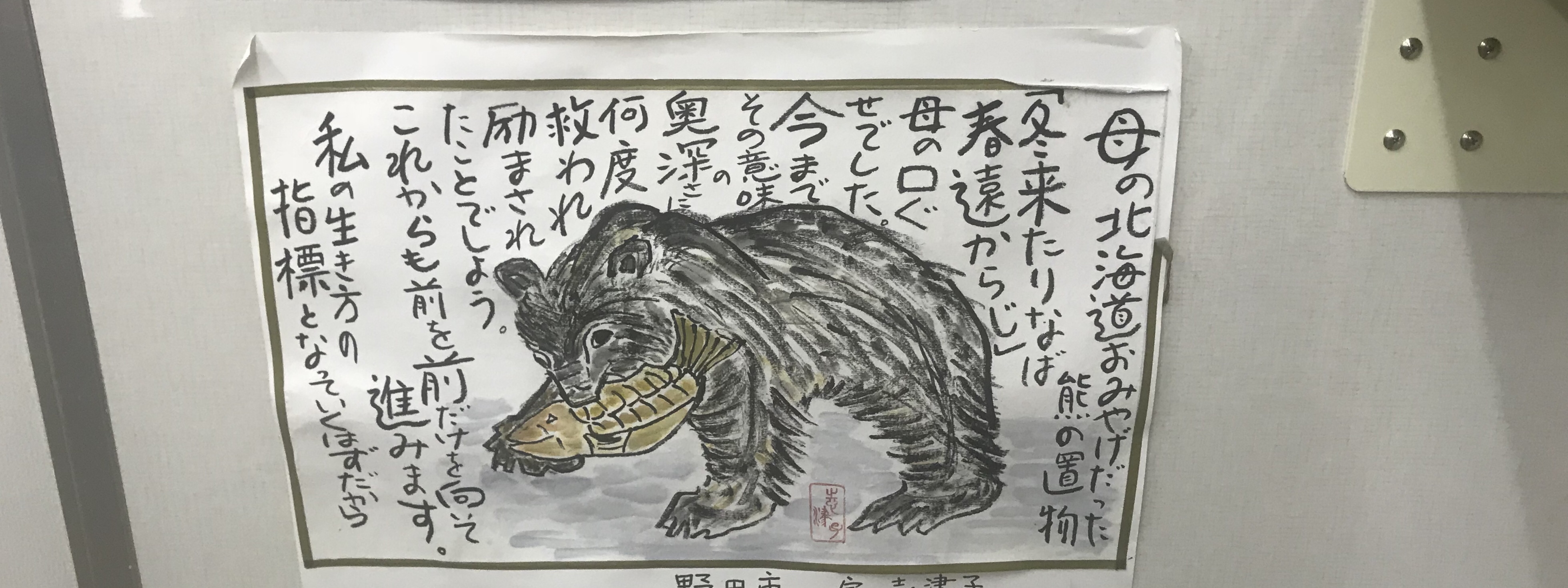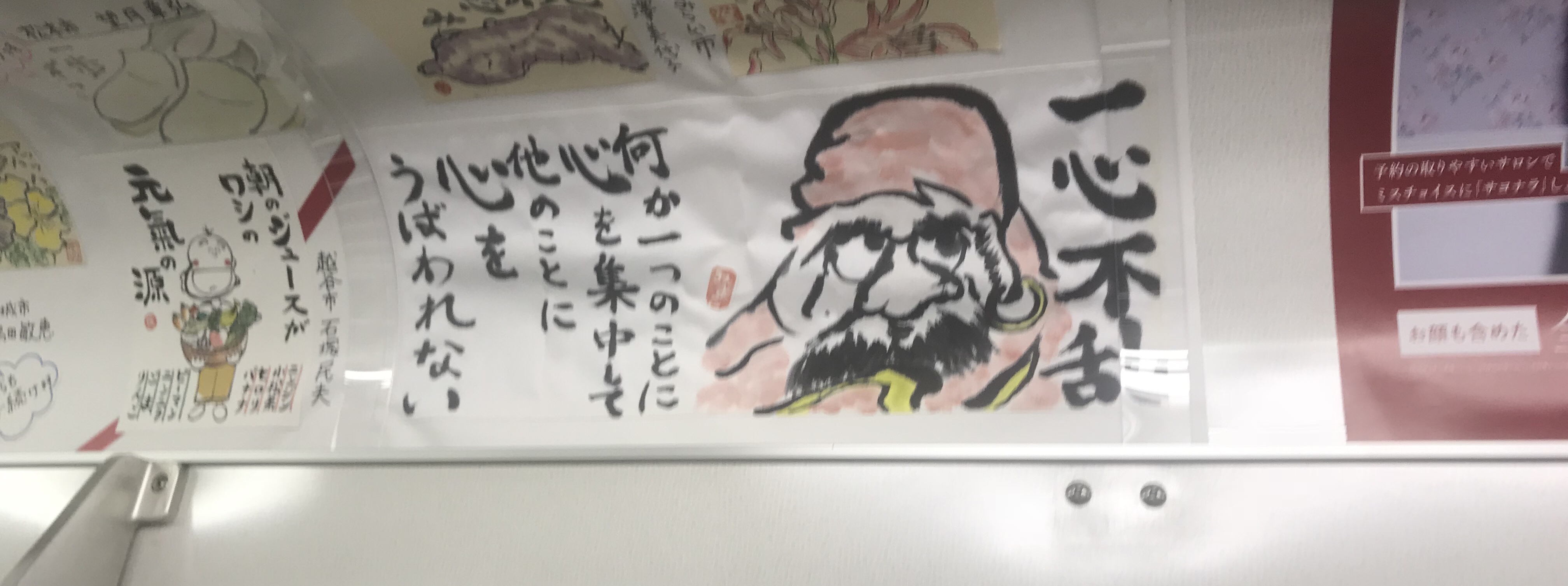昨日は春日部の小学校で能「黒塚」のシテを勤めた後に、最寄りの東武線の駅まで20分ほど歩きました。
車でも帰れたのですが、何となく「クーリングダウン」をしたいと思ったのです。
.
ゆっくり歩いて、電車で三ノ輪に帰ると早めに休みました。
.
今朝6時前に目がさめると、クーリングダウンの効果か昨日の疲れはそれほど残っていませんでした。
新幹線→近鉄→京阪電車と乗り継いで、香里能楽堂の「七宝会」へ向かいました。
.
七宝会では舞囃子「井筒」地謡、能「枕慈童」後見、能「玉葛」地謡を勤めました。
.
.
夕方に舞台は無事に終わりました。
.
しかし今日はまだ終わりません。
これから北大路にある公共施設の和室で京大宝生会の稽古をするのです。
.
そして更にその後には、永平寺での修行を無事に終えて先日下山した若手OBと、久しぶりに会って食事をする約束をしています。
.
.
ちょっと詰め込み過ぎの盛りだくさんな1日ですが、あとひと頑張りしたいと思います。