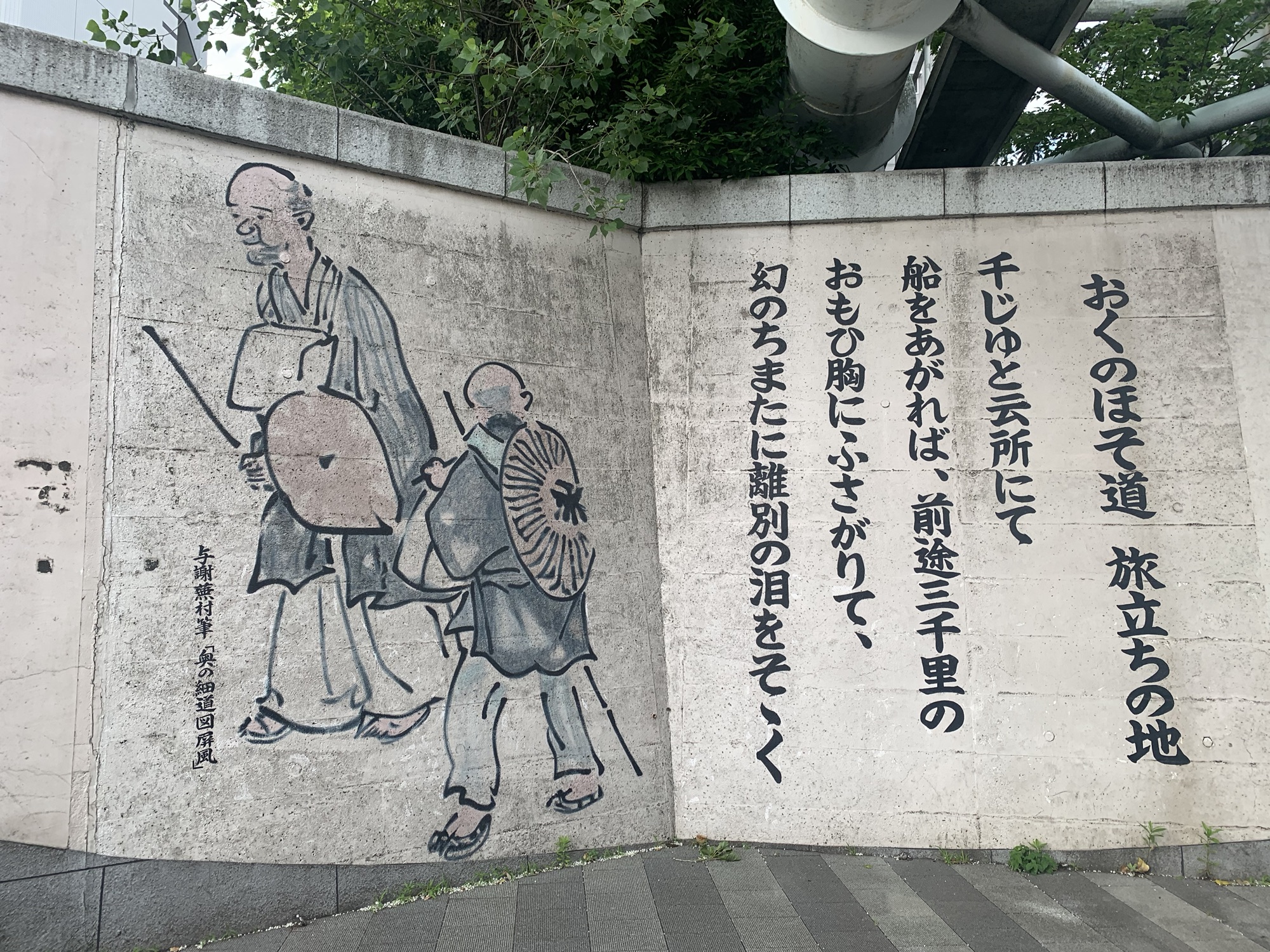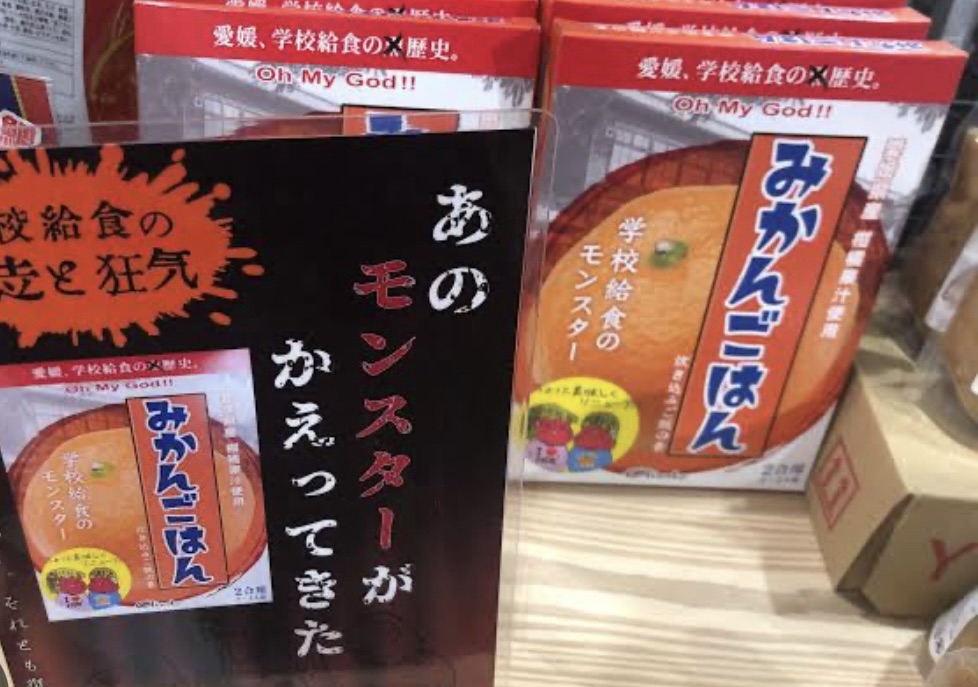今日は久々に仕事で伊勢神宮に行って参りました。
・
実はこの書き出しは、丁度6年前の2018年4月29日の「伊勢神宮の舞女さん」というブログの書き出しと全く同じなのです。
・
・
その時は、神楽の時に「舞女」さん達が三宝などを神前に御供えする動きに感銘を受けたという事がブログに書いてありました。
・
今回も同じように神楽を拝見しました。
やはり「舞女」さん達の作法や、「倭舞」という4人での舞は見事でした。
・
・
しかし今回の神楽で特に「これはすごい!」と思ったのは、男性が面をつけて舞う「舞楽」でした。
・
緑色の面に、黄色を基調にした装束だったと思います。
舞楽の知識は何も無いのですが、舞人の足運びや、浮き沈みする動き、面をかけているのを感じさせないスムーズな移動などを見て、この舞人は名手だろうと確信しました。
・
・
後で調べると、今日の舞楽は「高麗楽(こまがく)」を伴奏とする「納曽利」という舞楽だったようです。
動画もいくつか見つけたのでまた見てみようと思います。
・
・
そして今日改めて気がついた事がありました。
「倭舞」も「納曽利」も、神様に向けて奉納されるので我々参拝者は舞の大半を”後ろ姿”しか見られない事になるのです。
それでも演者の力量によって、後ろ姿だけで「上手いなぁ」と感じさせる事ができるのです。
・
能楽もその昔は同じように、見所は横と後ろにしか無かったそうです。
その時代の観客は、今日の私のように”後ろ姿”に感銘を受けたのでしょう。
・
・
またもう一つ、「倭舞」も「舞楽」も、参拝者がどんなに感動しても”拍手”をする事はありません。
もちろん神様も拍手はされないわけで、あれだけの技芸を見せた舞人達が、喝采を受ける事なく静かに退場していくのもまた神楽の潔さ、美しさだと感じ入ったのでした。
・
・
拝見する度に違うところに感銘を受ける伊勢神宮の御神楽です。
またいつか拝見するのを楽しみにしたいと思います。