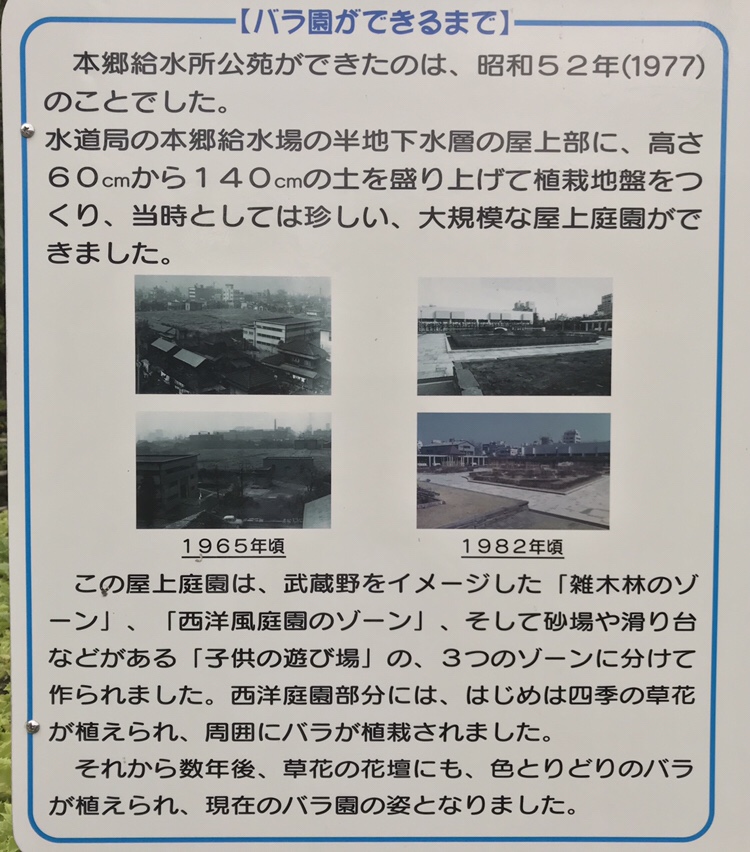今朝のニュースで「長良川の鵜飼が今日から始まる」というのを知りました。
.
能にも「鵜飼」という曲があるのは周知の事ですが、私は「鵜飼」という単語にはまた特別な感慨を覚えるのです。
何故なら能「鵜飼」は、私が京大宝生会の指導を引き継いでから初めて学生に教えた能で、大変思い出深い曲だからです。
.
.
もう10数年も前のことです。
当時能「鵜飼」のシテを勤めた金沢出身の部員の実家のお寺で「能合宿」をしたり、また彼がその実家のお寺から「僧衣」を借りて来て稽古用の装束にしたり、金沢の土産物屋で安く買ったいいかげんな能面を彫り直して稽古面に仕立てたり、前シテの持つ「松明」を私が手作りしたり…。
とにかくあらゆる点で試行錯誤を重ねて舞台を作り上げました。
私はまだ内弟子の頃で、型付や囃子の手付を見ながら危なっかしくあしらったりしたものです。
当日の装束付けや楽屋の仕事など、慣れないことばかりでとにかく必死でしたが、その分舞台が成功した時の達成感は格別のものがありました。
またその後数年にわたって出た何番かの能に繋がる「勢い」のようなものが、あの舞台で生まれた気がします。
.
その時のシテと地謡のメンバーには、今の若手OBOGの稽古会の中心メンバーが揃っています。
思えばあの時「鵜飼」という一曲の能が成功したことで、私も含めた何人かの人生と、その後の京大宝生会の針路が大きく影響を受けたのだと思います。
.
.
今日の鵜飼のニュースであの時の事を懐かしく思い出しました。
…しかし考えてみれば、私はまだ実際の「鵜飼」を見たことがありません。
当時何人かの部員が宇治川の鵜飼を見に行ったのですが、私は予定が合わなかったのでした。
.
今年の鵜飼は今日から10月15日まで行われるそうです。
そして現在では、中秋の名月の日を除けば満月の夜にも鵜飼が行われるとのこと。
.
今朝のニュースに気づいたのも何かの御縁。
機会を見つけて、何とか今シーズンに一度鵜飼を見に行きたいものです。