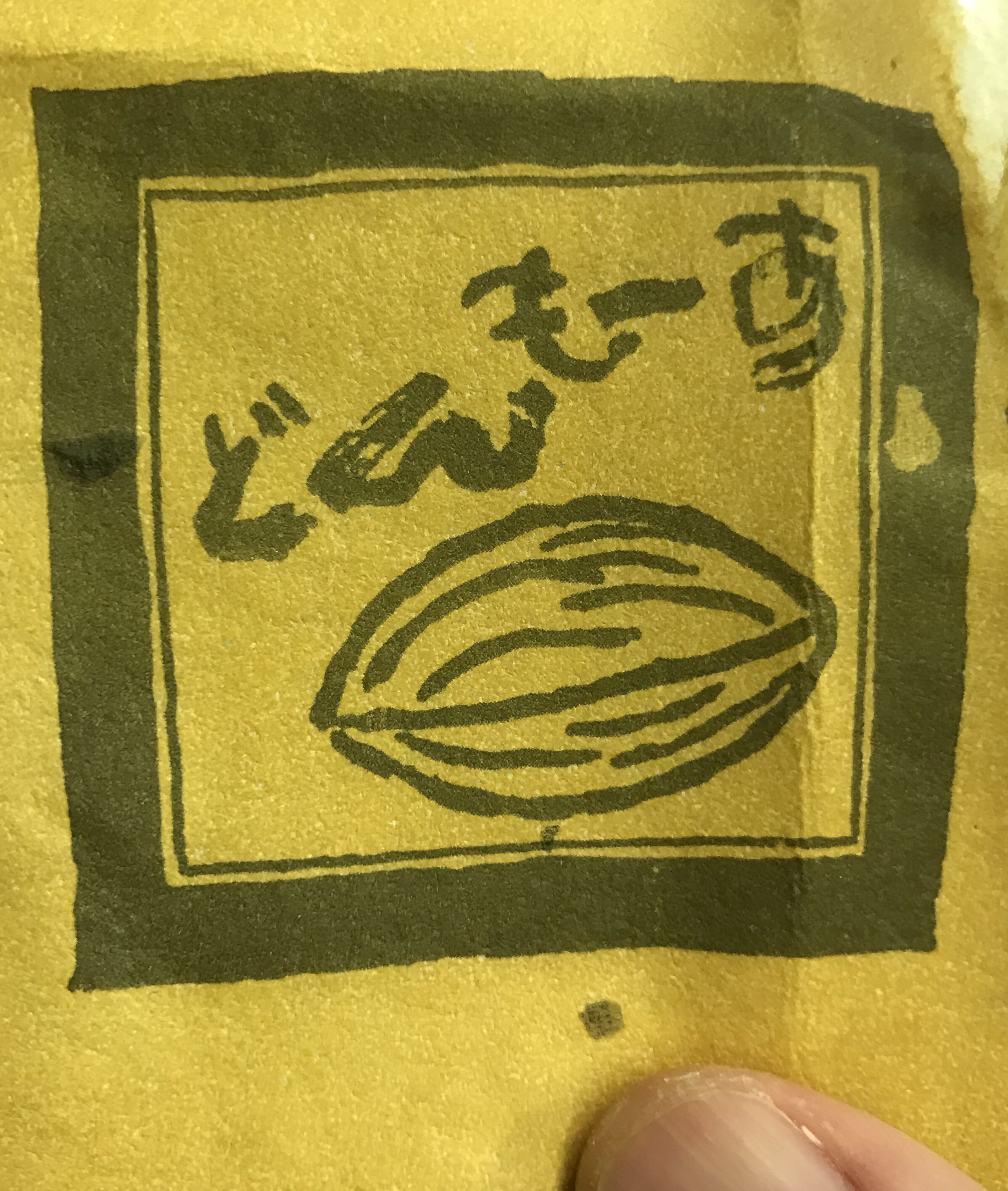五雲会の能百万の申合がいよいよ明日になりました。
百万は舞も謡も、その解釈と味付けが難しく、苦労しております。
謡は突き詰めれば「高い」「低い」「早い」「遅い」の組み合わせだ、と聞いたことがあります。
しかしやはりもう少し細かい要素もある気がします。
「年齢」「性別」「職業」「住所」「家族構成」…なんだかアンケートみたいですが。これらも加味して考えないと、その曲の位が理解出来ないと思うのです。
百万で言うと…
・氏名:百万
・年齢:40歳前後
・性別:女
・職業:女芸人
・家族構成:夫(死別)、長男(行方不明)
・住所:本籍地…大和国 西大寺辺り、現在…住所不定(行方不明の長男を探して、奈良から京都へ移動し、嵯峨清涼寺に至る)
こんな感じでしょうか。書いてみると、相当苦労している人ですね。
しかし曲調には不思議と深刻な暗さはありません。むしろ「強さ」や「希望」を感じる場面もあります。
これは彼女が曲舞の名手であったり、大念仏の音頭取りをしたりと言うように、芸人として優れており、その自信と誇りのようなものが現れているからかもしれません。
…このような様々なことを考慮しながら、私なりの百万を頑張って舞わせていただきたいと思います。