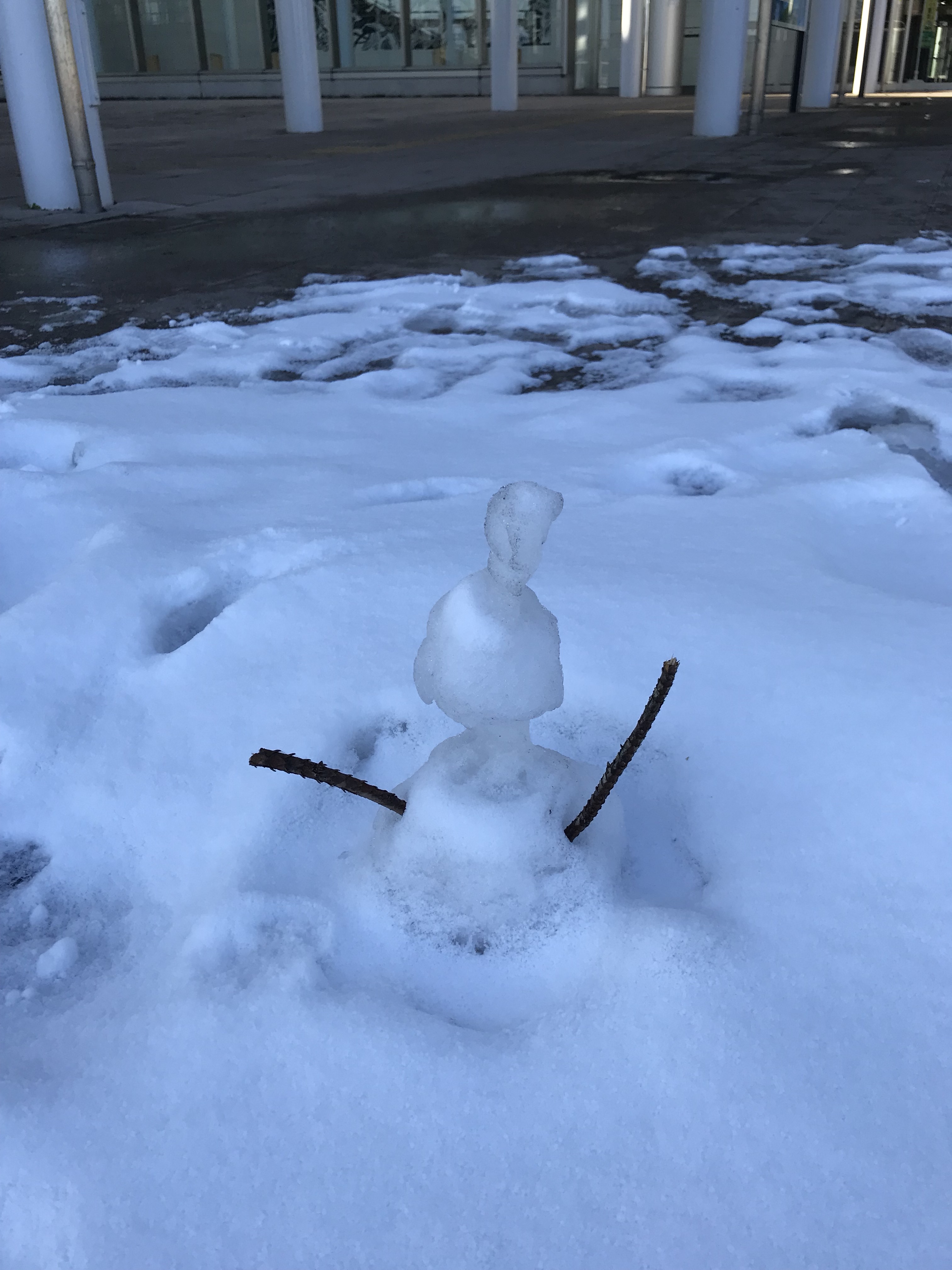今日は香里能楽堂にて、宝門会大会に出演して参りました。
.
いつも澤風会の舞台を観に来ていただき、このブログも読んでくださっている宝門会のお弟子さんが、今回は初シテとして能「巴」を舞われました。
.
.
水曜日の申合でお会いして、お声をおかけした時の話。
.
私「今回はおめでとうございます!」
お弟子さん「全然おめでたくないです〜!まだ何もしてないです〜!」
.
いえいえ、この「おめでとうございます」は、初シテを舞われるという事に対してのお祝いなのです。
本番が無事に終わったら、また盛大に「おめでとうございます!」とお祝いさせていただきます。
お弟子さん「え〜、そうなんですか〜!」
.
.
そして今日、能「巴」の本番は大変素晴らしい舞台になりました。
.
私「いや〜、本当におめでとうございます!」
お弟子さん「ありがとうございます〜‼️」
.
晴れ晴れとしたお顔です。
.
面をかけて能を一番舞うということは、我々でも大変なことです。
ましてや初シテならば、稽古段階からの御苦労は想像を絶するものがあったことと思います。
.
.
しかしながら、その「初シテ」を無事に勤められたということは、実は稽古100回にも倍する貴重な経験を積まれたことなのだと思うのです。
.
この次の稽古からはたとえ難しい仕舞でも、「何だか身体が軽いし、足元が普通に見えるし、呼吸が楽で謡いやすい!」という喜びを感じられるはずです。
.
.
次回の舞台では、何段階もステップアップされたお姿を拝見するのを楽しみにしております。
.
重ねて本日は初シテおめでとうございました!