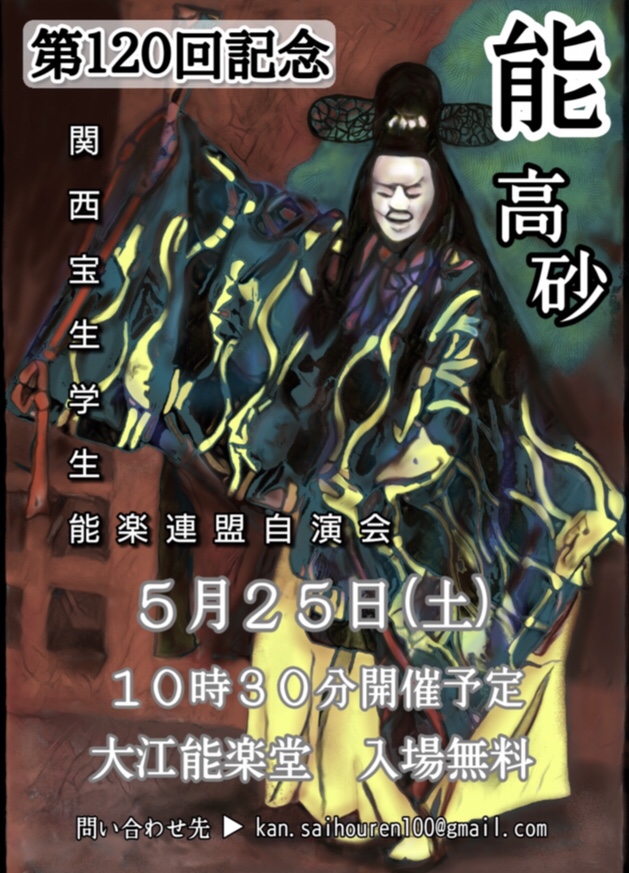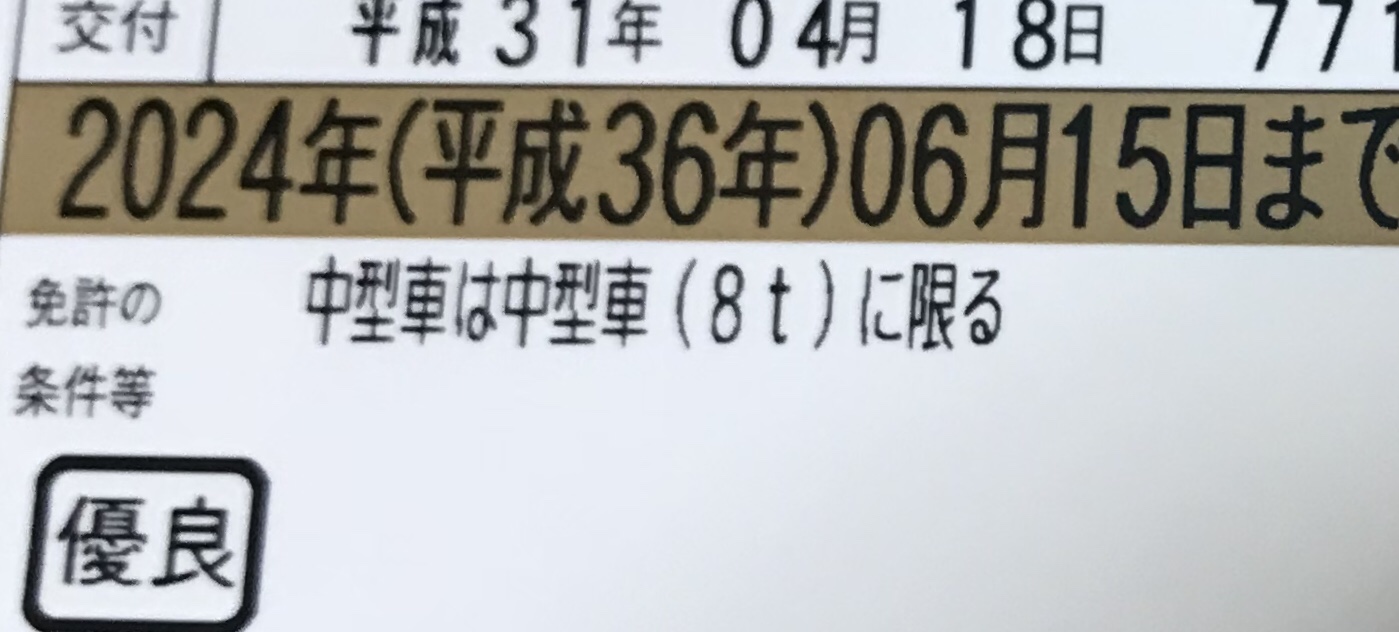今日は亀岡稽古でした。
朝に三ノ輪の自宅を出て、いつものように「隙間花壇」の前を通りかかると…
.

見落としてしまいそうな程に小さな「虞美人草(ヒナゲシ)」が一輪だけ咲いているのに気がつきました。
例年はもっとたくさん咲くのですが、今年はマンション改修工事の影響で植物達が育ちにくいようです。。
.
それでも頑張って咲いてくれたこの花は立派です。応援したくなります。
今年を乗り切って、来年からはまた思う存分に咲き誇ってほしいものです。
.
.
.
そして亀岡に移動すると、こちらは春の花が無数に咲き乱れていました。
撮影が追いつかない程で、目についた数種類を紹介させていただきます。
.

これは「ヒキノカサ」という変わった名前の植物です。
花を「蛙(ひき)の傘」に見立てた名前だそうですが、1〜2㎝ほどの小さな花で、傘にしても蛙は雨に濡れてしまいそうに見えました。
京都府内では一時”絶滅種”とされていた貴重な植物だそうです。
.
.

これはおそらくマムシグサの一種かと思い調べてみると、「ユキモチソウ」という植物でした。
.
花の真ん中から真っ白いお餅のようなものがニョキッと顔を出しています。

これが「雪のように白いお餅」に見えるので「雪餅草」と名付けられたそうです。
.
また筒状の花に見えるのは花ではなく葉の変化した”苞(ほう)”というもので、サトイモ科の植物では仏像の光背になぞらえて「仏炎苞」という有り難い名前で呼ばれるそうです。
.
.

群青色の星のような花を見つけました。
これは「ホタルカズラ」と言い、草叢に点々と咲く花を蛍に例えた名前だそうです。
美しい名前のこの植物も、やはり多くの府県で絶滅危惧種に指定されているということです。
.
.
初めて見る花に加えて、毎年会えるのを楽しみにしている花もありました。

「ムレスズメ」です。
今回はいつかの”返り咲き”ではなく、ちゃんとスズメの大群のようになって咲いていました。
.
.

そして「コノハナザクラ」です。
ヤマザクラの八重咲き品種であるこの桜は、野生種は日本に僅か4本しか存在しないとか。
見頃は過ぎていましたが、何とか花に間に合いました。
.
.
.
マンション工事の影響に負けずに咲いた隙間花壇の「虞美人草」。
そして絶滅の危機を乗り越えて咲き続ける亀岡の花々。
.
今日東西で出会ったそれらの花々からは、いずれも「強い生命力」を感じて印象に残りました。