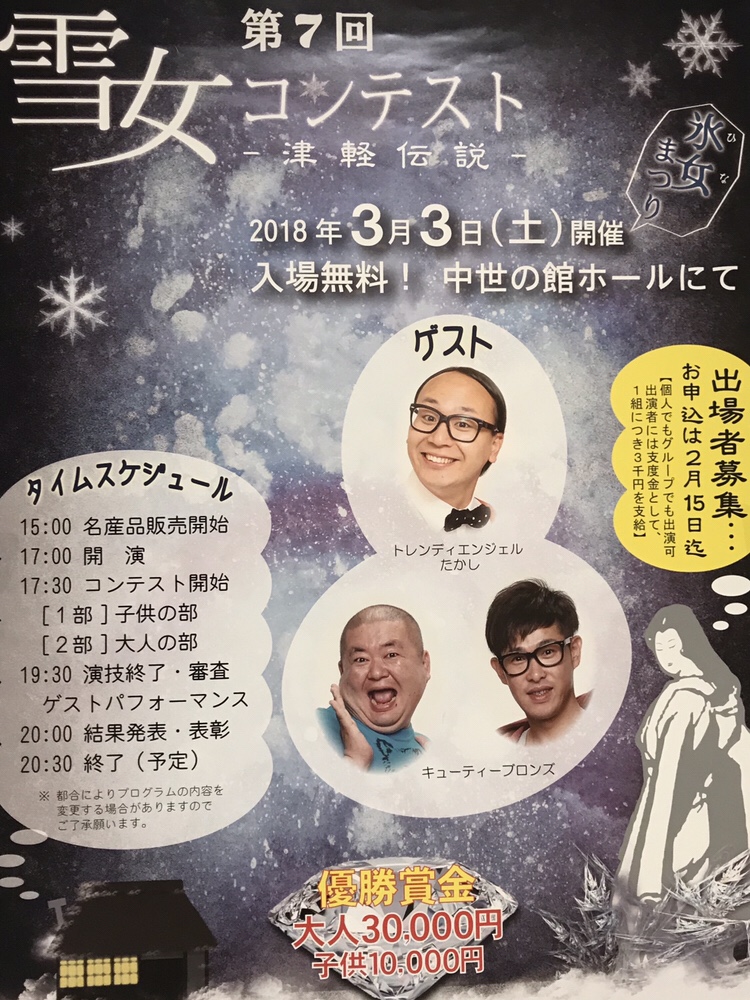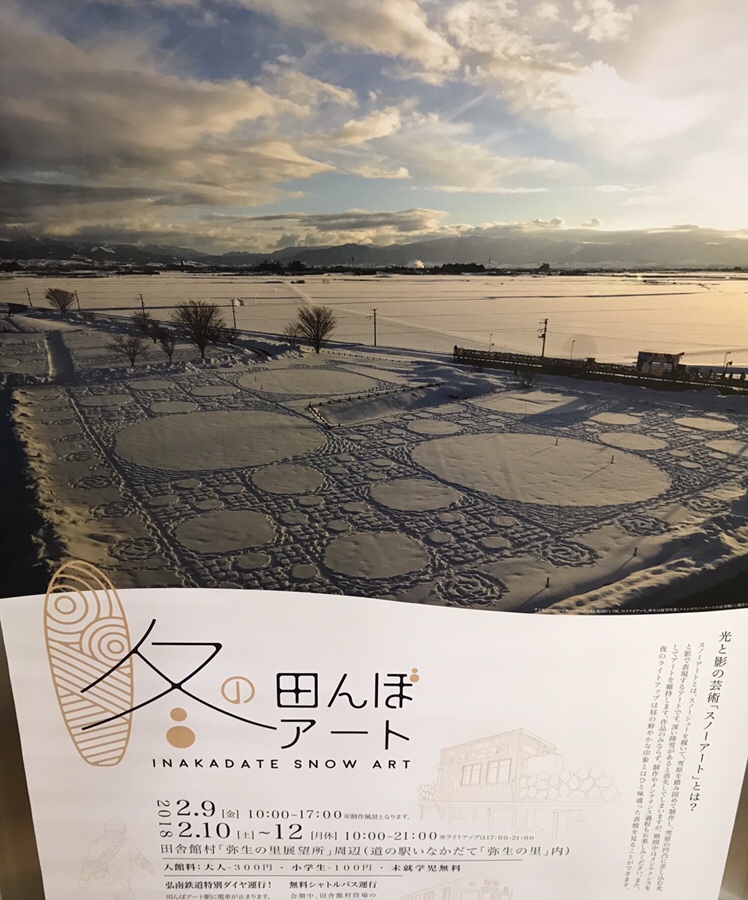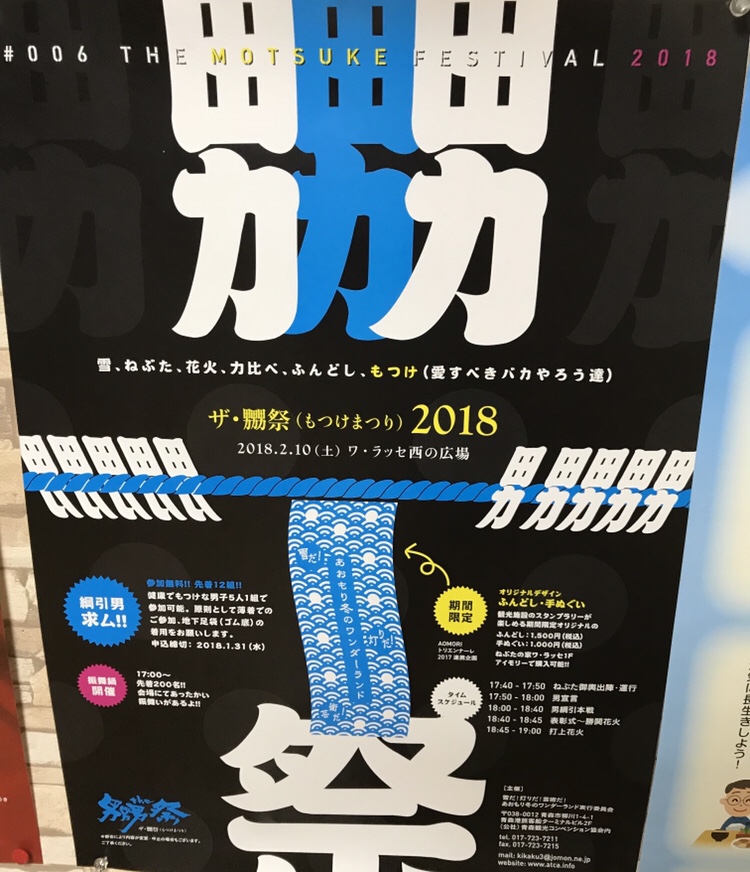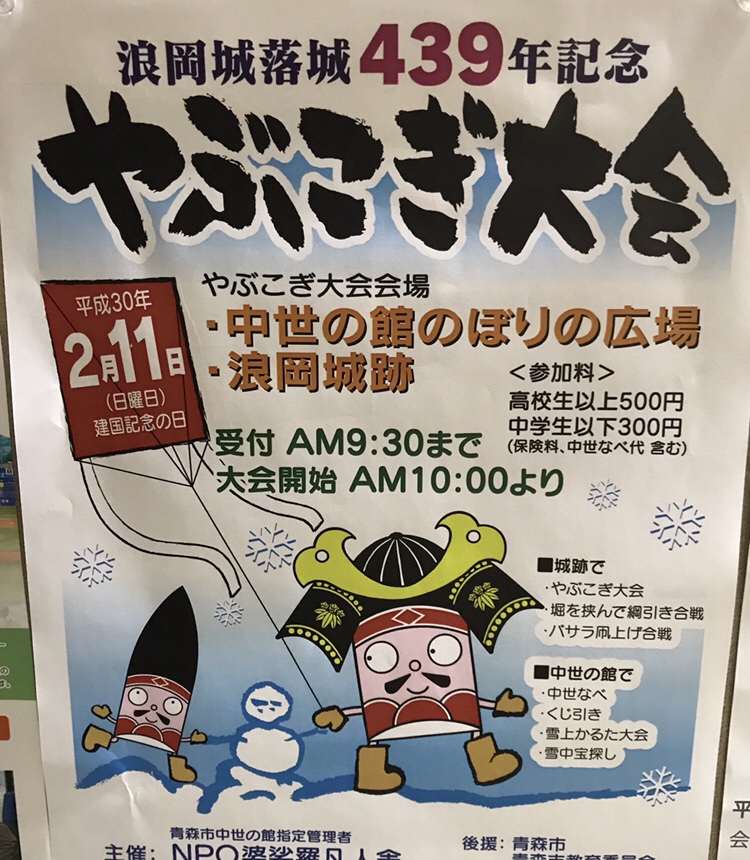今日は「皆既月食」が見られる日です。
.
携帯ニュースでは今回の皆既月食を「スーパー・ブルー・ブラッドムーン」という、何かの必殺技みたいな名前で呼んでいました。
また大袈裟な呼び方を…と思ったら、これは正式に使われている呼称だそうです。
.
ただし、3つの呼称が重なっているのです。
・スーパームーン:地球に接近して大きく見える月。
・ブルームーン:満月のこと。
・ブラッドムーン:皆既月食で赤くなった月。
そして今日の皆既月食は、実に35年ぶりにこの3つの条件を全て満たしているそうなのです。
.
東京は夜には雲が出るという予報でしたが、先ほど田町稽古を終えて外に出てぐるりと夜空を見渡すと、見事な満月が輝いていました。
時間は20時45分。まさにこれから月食が始まる時間です。
.
一旦地下鉄に乗り、三ノ輪で皆既月食を見ようと思いました。
雲が出ないように祈って三ノ輪で地上に出ると…
.
見えました!三ノ輪は雲ひとつない夜空でした。

写真には上手く写りませんが、左下から欠けて来ています。
しばし寒さに耐えて見ていると、ついに21時50分過ぎに皆既月食になりました。
これまたわかりづらい写真ですが…

先程の写真よりも赤っぽいのはおわかりかと思います。
.
能楽に「月」はよく出て来ます。
というより、「月」という単語が一切出てこない曲を探す方が難しいくらい、頻繁に出てくるのです。
.
現代のように明かりに溢れた夜ではなく、中世の夜は真っ暗闇だった筈で、月の明かりはとても貴重なものだったのでしょう。
それが、満月の夜に1時間足らずで急に月が暗赤色になって、辺りが暗くなるなどという現象は、当時はおそらく非常に恐ろしい事件だったと思われます。
.
これだけ「月」がよく出てくる能楽に、「月食」を示すような内容が無いのは、おそらく月食は不吉な現象と見られていて能楽の題材には適さないと思われたからではないでしょうか?
.
現代の私はと言えば、35年ぶりという天体ショーを見られて大満足で、「自分は今、太陽と月を結んだ直線上に丁度いるのだなあ」などと感慨にふけっているのでした。