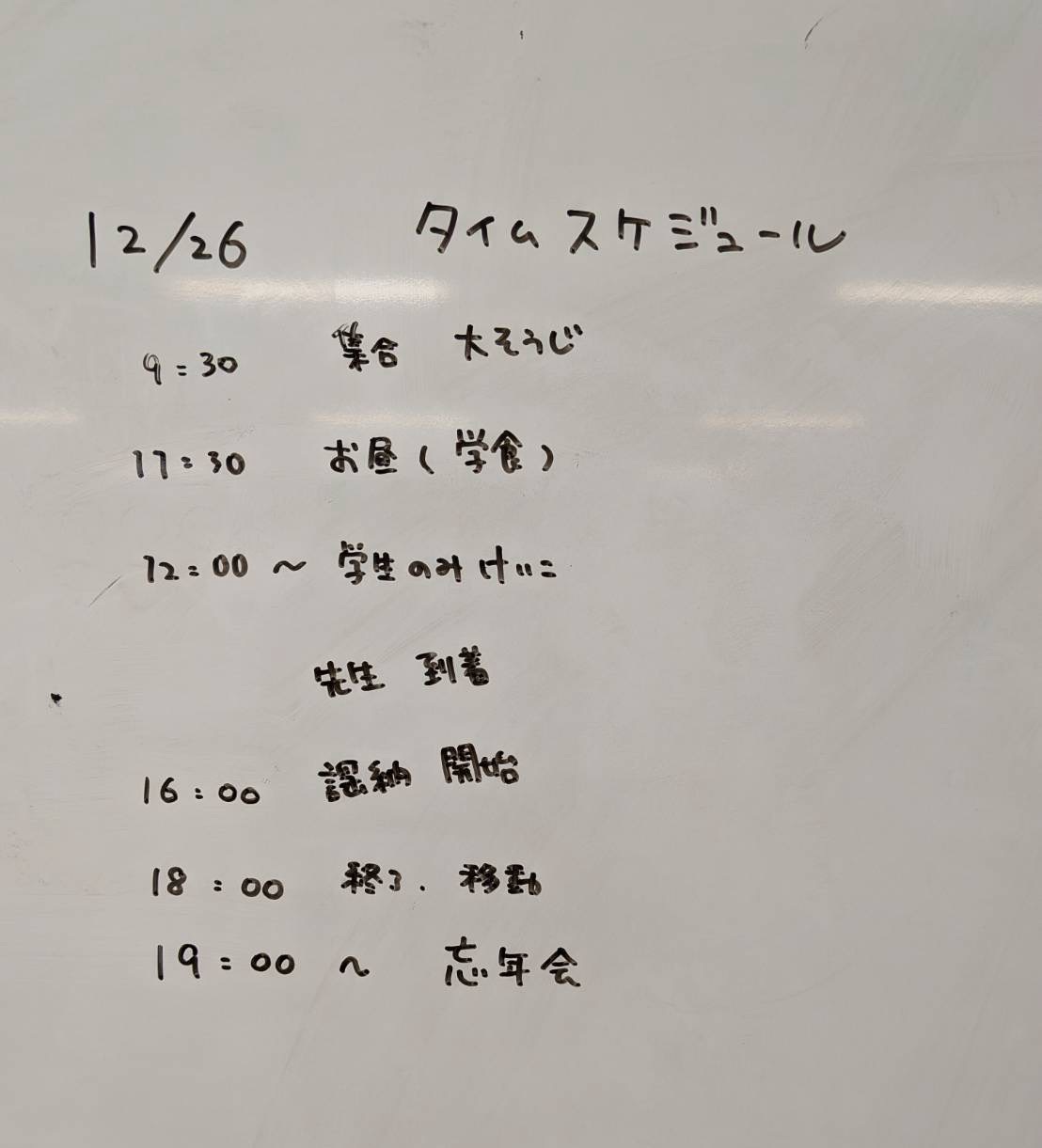夏にスマホを新しくしたところ、ブログに写真がアップできなくなってしまいました。
何度か試行錯誤してもどうにもならず、困ったなあと思っているうちにカレンダーは早くも12月…。
・
このままブログが滞ってしまうのも心苦しいので、当面は写真なしの文章だけのブログにさせていただきたく思います。
・
・
今年も実に盛りだくさんの出来事がありました。
思いつくままにいくつか書いて参ります。
・
・
先ず今年は、「遠くに離れても稽古を続けてくれる人」が多い年でした。
・
春に自治医科大学宝生会から3人の学生が卒業して、それぞれ秋田、群馬、鳥取で研修医としての多忙な新生活を始めました。
普通に考えれば、全国に散らばった3人が稽古を続けるのは非常に困難です。
それでも、彼らは何とか稽古を続けたいと言ってくれました。
・
そこで「zoom」を使ってのリモート稽古を提案してみました。
3人の予定が合いそうな週末の夜に、月に一度、1時間ほどzoomに集まって謡の稽古をするのです。
4月から早速始めて、全員揃わない月もありますが今のところ月1回のペースを維持して稽古できています。
仕舞も自治医大宝生会の合宿の時などに集中して稽古して、来年3月の澤風会郁雲会を目指してくれています。
・
リモート画面上ではありますが、3人が全国から集まって少し近況なども話しながら稽古するのはとても楽しい時間です。
・
・
また東京神保町稽古場で稽古していた国家公務員の京大若手OGさんは、夏に青森に転勤になりました。
やはり稽古は難しいと思われましたが、私は一応青森に月に一度稽古に行っておりました。
また青森には私の同期の京大ベテランOGさんもいて、その人が色々手配してくれたおかげでこちらも月1回のペースで稽古が継続できそうです。
・
・
更に、神保町稽古場で昨年まで稽古していて、今はオランダで暮らしている京大若手OBさんがいます。
京大宝生会同士で結婚して、奥さんと一緒にオランダにいるのです。
その彼がこの9月に一時帰国した際に、1人の見学者を連れてきてくれました。
・
何と奥さんの高校時代の同級生だというのです。
驚いて奥さんの方にメールして聞いてみたところ、オランダから早速返信が来ました。
「彼女は中学生の時に”古典芸能への招待”を見ていたそうで、また元弓道部員で体幹も強いので是非にと稽古に誘ってみたのです」
・
なるほど。
オランダの若手OBOG夫婦は来春帰国予定だそうで、帰国したら一緒に稽古したり舞台で共演するのを楽しみにしているとの事でした。
・
・
秋田、群馬、鳥取、青森、さらにオランダ。
これだけ広範囲に散らばった人達と、縁が切れずに稽古を続けていけるのは本当に嬉しくありがたいことです。
こういった縁の繋がりを大切にしていきたいと思います。