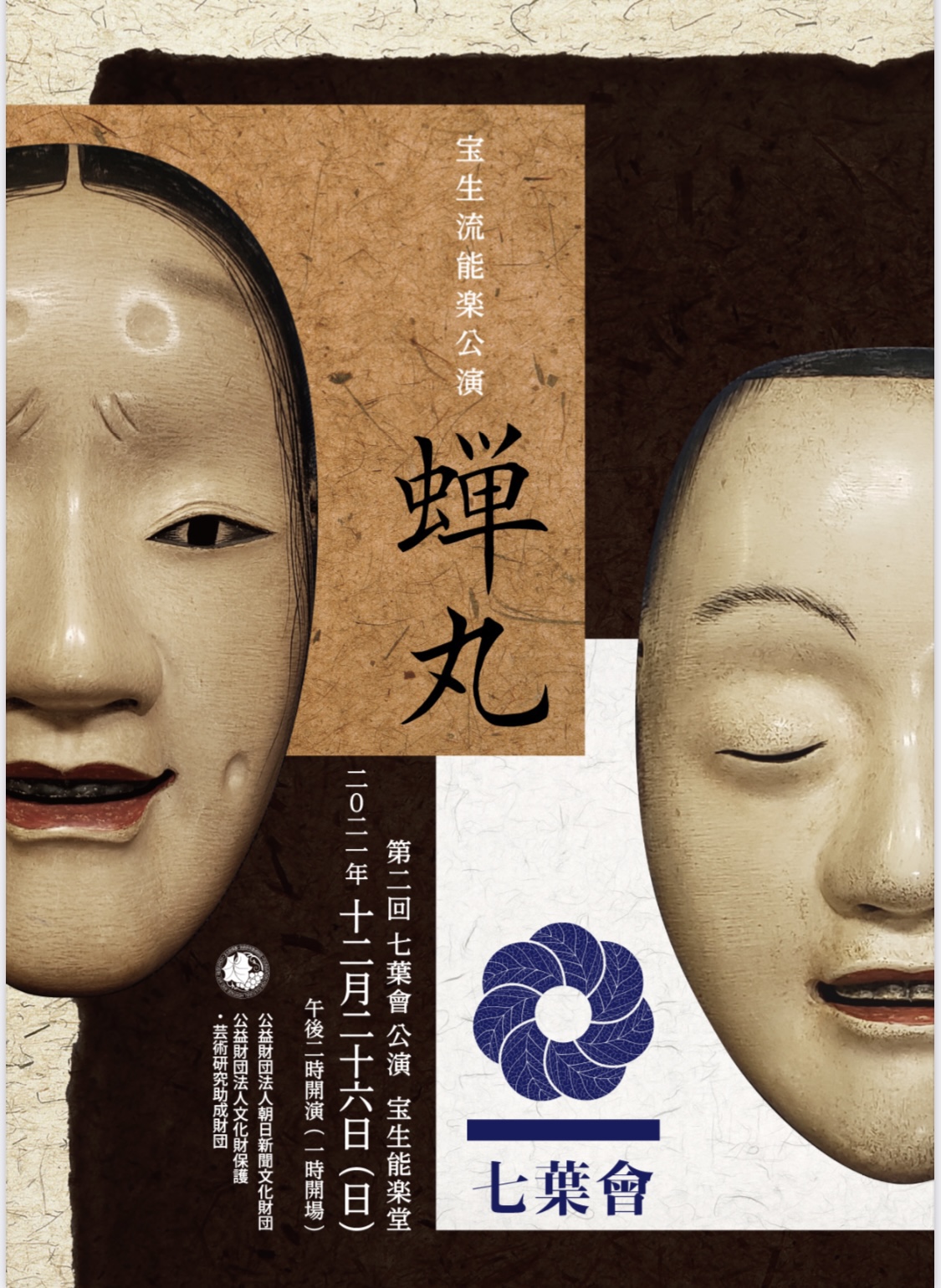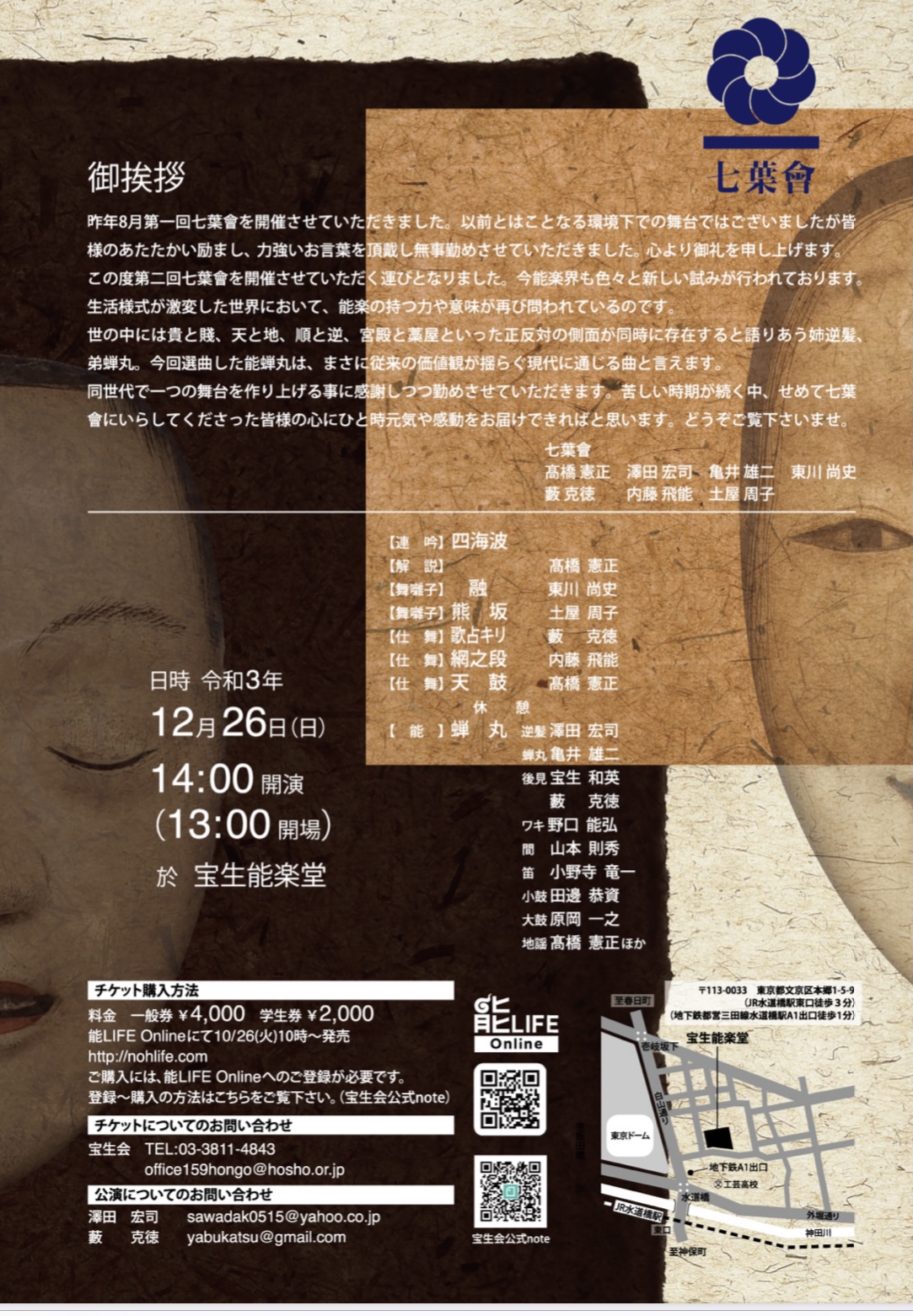今週土曜日の「五雲能」にて、私は能「巴」のシテを勤めます。
.
なので今日の午前中の隙間時間に滋賀県膳所にある「義仲寺」を訪ねてみました。
ここには木曽義仲のお墓と、巴御前の供養塔があるのです。
.
.
JRに乗って雨模様の京都を出発。
大津のひとつ先の「膳所(ぜぜ)」で下車します。

.
難読駅名のひとつ「膳所」。
昔琵琶湖の新鮮な魚を宮中に献上した場所で、それが名前の由来になったそうです。
.
.
膳所駅から「ときめき坂」というやや照れ臭い名前の坂道を琵琶湖の方へ降りていきます。
10分ほどで旧東海道に行き当たり、左折してすぐに「義仲寺」はあります。

周りには、昔ここで激しい戦があったとは思えないような、平和な住宅街が広がっています。
.
.
境内には義仲の大きなお墓があり、

.
その横にひっそりと寄り添うように巴の供養塔「巴塚」がありました。

説明書きには、巴はこの場所で義仲の菩提を弔った後に木曽で90歳まで生きたとあります。
.
.
しかし能「巴」では巴は若い姿で現れるのです。
.
私は想像しました。
…巴は長生きして死んだ後も、義仲と一緒に戦いたかったのではなかろうか。
そして若い姿で修羅道に落ち、そこで再び義仲と出会って永遠に戦い続けている。
そういう幸せもあるのかもしれない…。
そう考えると、なんだか無性に切なくなってしまいました。
.
.
義仲寺の入り口横には、「巴地蔵」という地蔵堂がありました。

その中にいらっしゃる「巴地蔵」はとても優しい顔をしています。

おそらく義仲と共にいる時の顔なのだろうな…と思いつつ、お参りして膳所駅への帰路につきました。