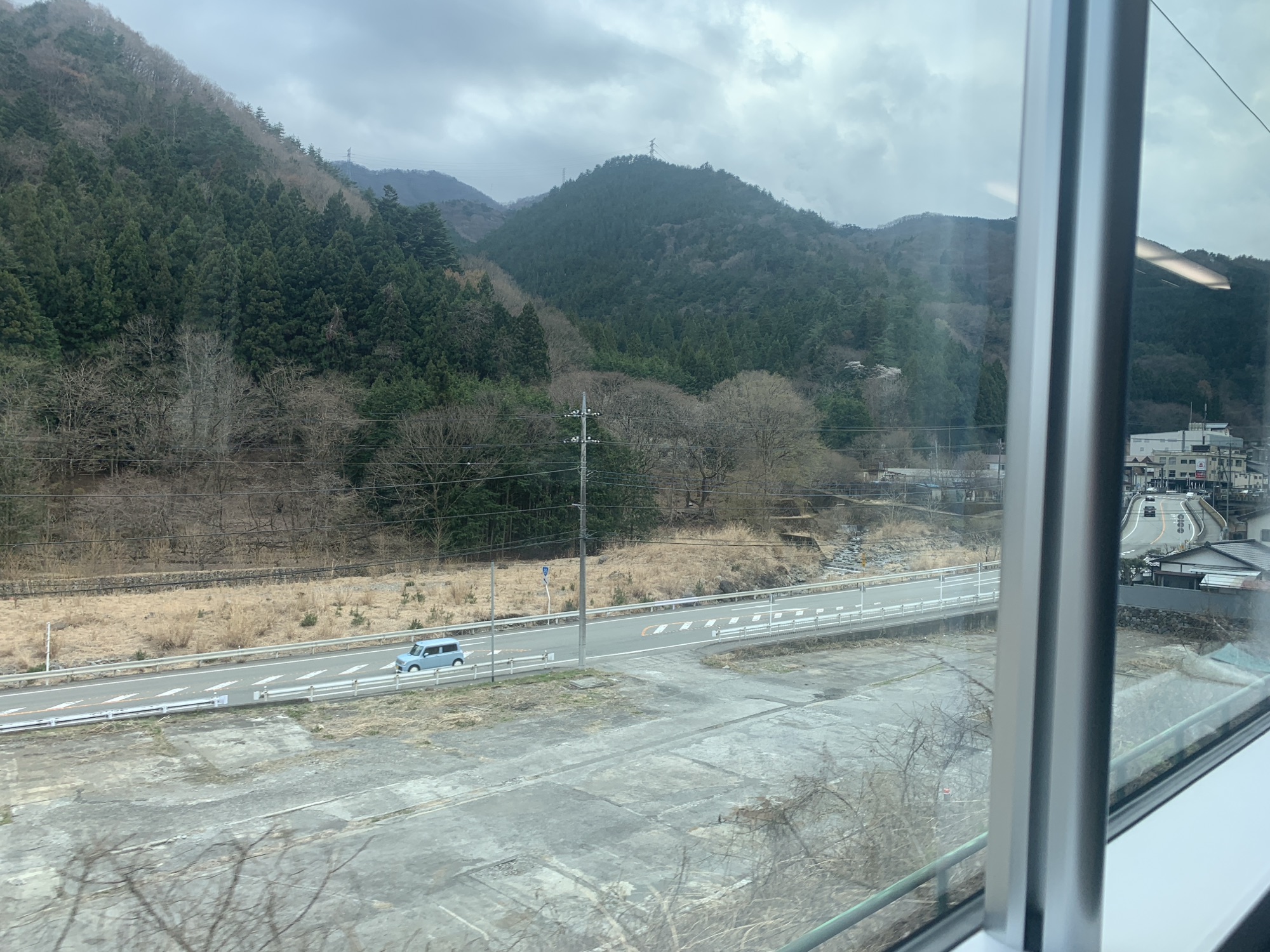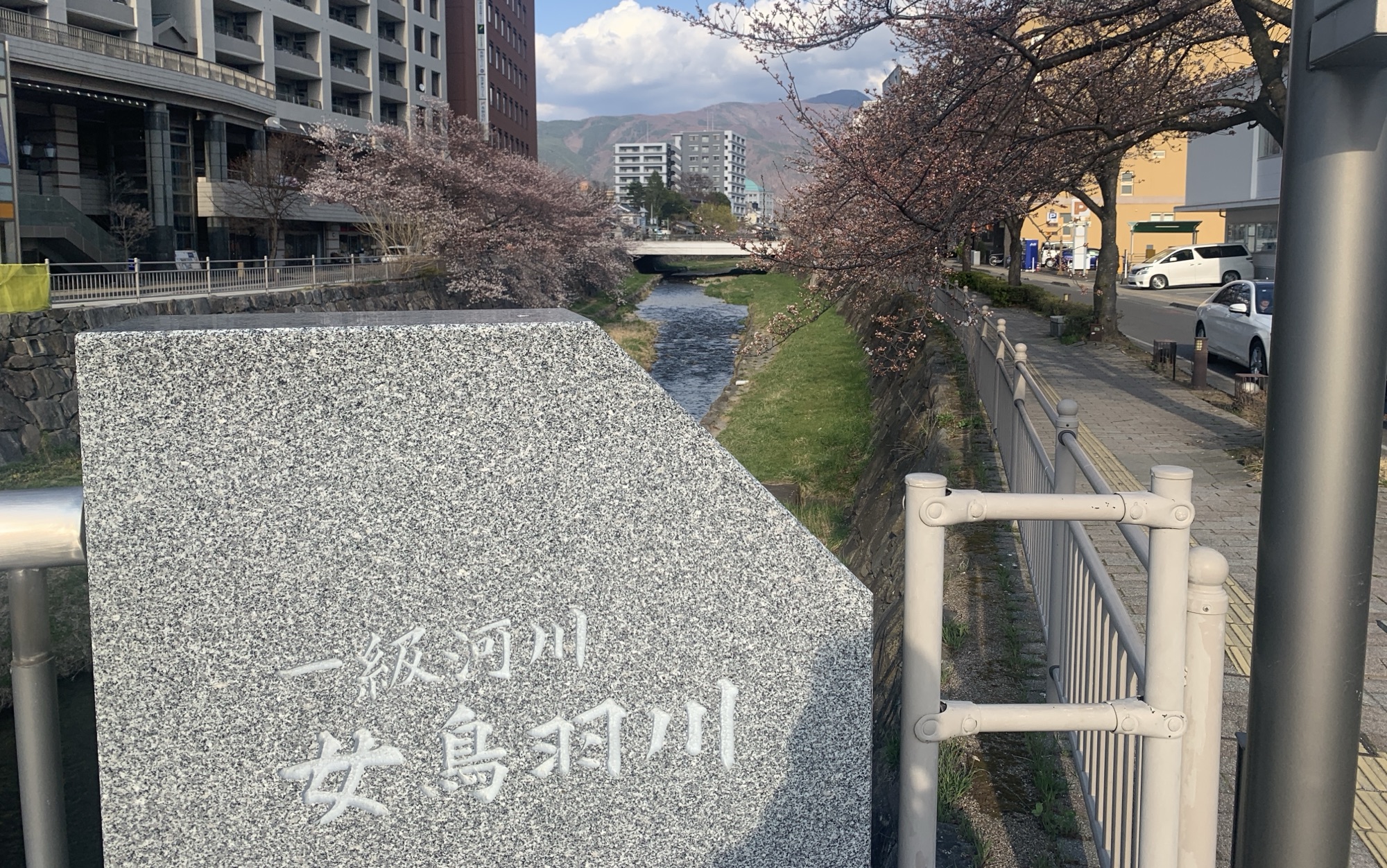今日は自治医大宝生会の新歓でした。
・
自治医大宝生会はこの3月に3人がめでたく卒業して、地元の秋田、群馬、鳥取でそれぞれ研修医として働き始めました。
・
残った現役は3人です。
新歓でできるだけ多くの新しい部員を獲得したいところです。
・
・
今日は寮内の和室に仕舞扇や能面を並べて、私がその前で謡をひたすら謡い、和室の前を通る関心を持っていそうな新入生を部員が勧誘する、という作戦でいきました。
・
すると謡い始めてすぐに、2人の新入生が和室に入ってきたのです。
これは幸先が良いです!
・
・
体育会系の男の子2人で、最初は能面に興味があるという話でした。
能面の解説から始めてなんとか型の体験に持っていき、「構えの手の握りは、小指に力を入れて親指は力を抜くようにします。これは剣道の竹刀を握る時も言われる事ですね」
と言ったら、ひとりの男の子の目がパッと輝いたのです。
・
「自分は野球をやるのですが、バットの握りも同じなのです!」
そこからは2人とも能楽に引き込まれたようで、私が高砂の仕舞を舞うと熱心に見入っていました。
・
・
新入生「今は色々本当に忙しくて、サークルを決める余裕がないのです。でも落ち着いたらまた見に来たいです!」
はい、是非是非!
・
今日は入部には至りませんでしたが、昨日の食事会にも何人か来てくれたようで、今年の新歓は良いスタートです。
・
自治医大宝生会は例年部員が入るのはゆっくりなので、焦らず着実に新歓活動を進めたいと思います。