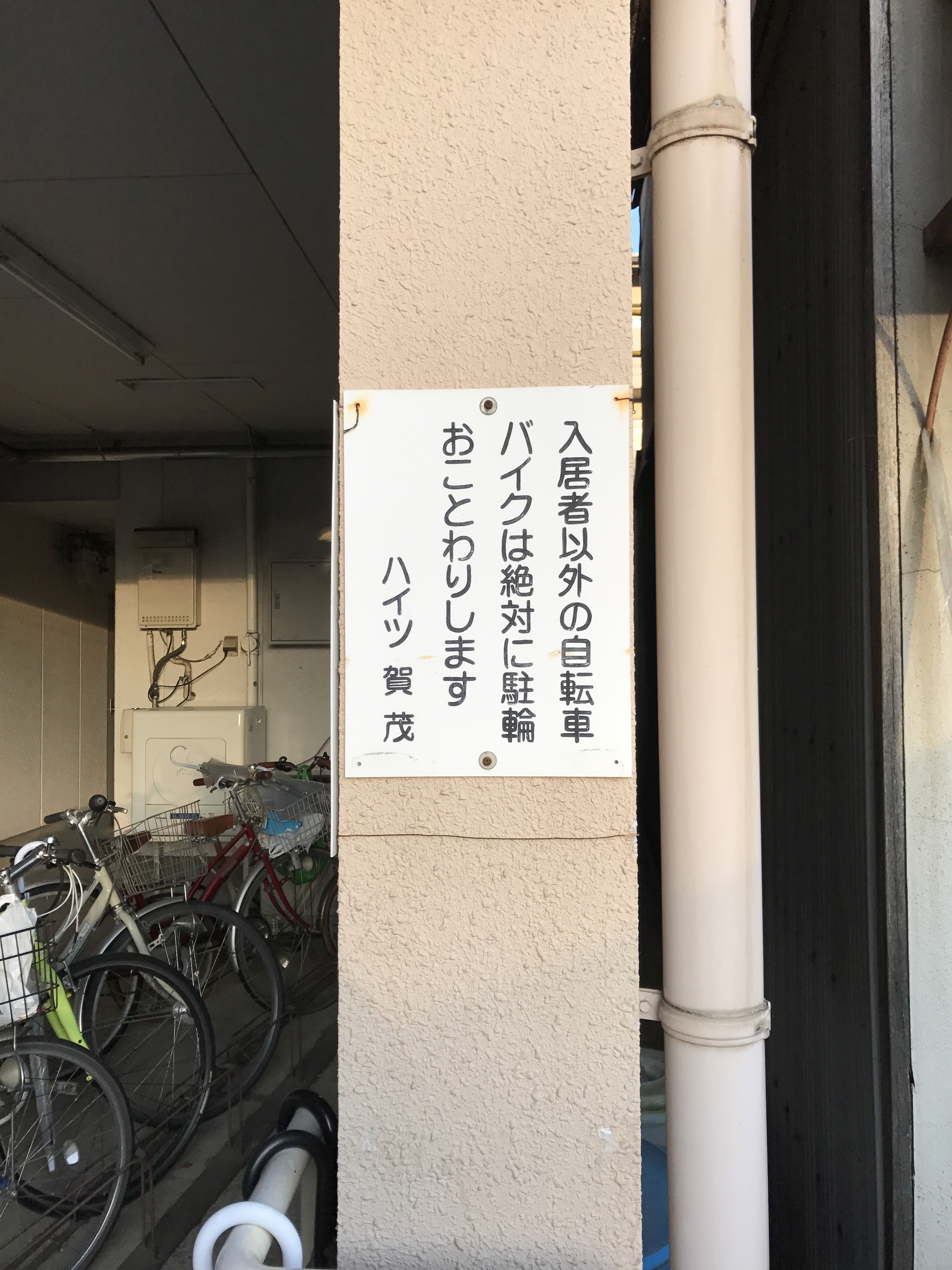世間はゴールデンウィーク真っ只中ですね。しかし昨日と今日は連休の谷間で、仕事や学校も普通にあるようです。
京大宝生会は結局連休前には1人だけの入部で、後は連休後に期待か…と思っていました。
ところが昨日の稽古にはなんと8人くらい見学に来て、1人新たに入部してくれたそうです。
この辺の新入生の動きの読めなさが、新歓の難しくまた不思議な所です。
不思議と言えば、何故か同時期に同じ苗字や似た苗字の人が入って来ることが多いのです。
「名前同志が引き合う」というのは非科学的な考えですが、例えば私の現役時代の3回生は「なかむらさん」が2人。私の同期は「たかはしさん」と「たかくわさん」。過去には他にも「なかむらさん」と「なかがわくん」、「よしだくん」と「よしださん」、「おおつきさん」と「おおたさん」などが同期でいました。
昨日入部した男の子も、実は現役4回生と同じ苗字らしいです。
ちなみに能においては、「夜討曽我」でシテの「曽我五郎時致」と戦う相手が「古屋五郎」と「御所の五郎丸」です。
こちらは名前ですが何故か「五郎」の相手は「五郎」ばかりなのです。
変わった所では、キンキキッズの2人が同じ苗字なのも全くの偶然だそうです。
苗字や名前で引かれ合う縁というのも確かに存在するような気がして、不思議なことですが大変興味深いです。