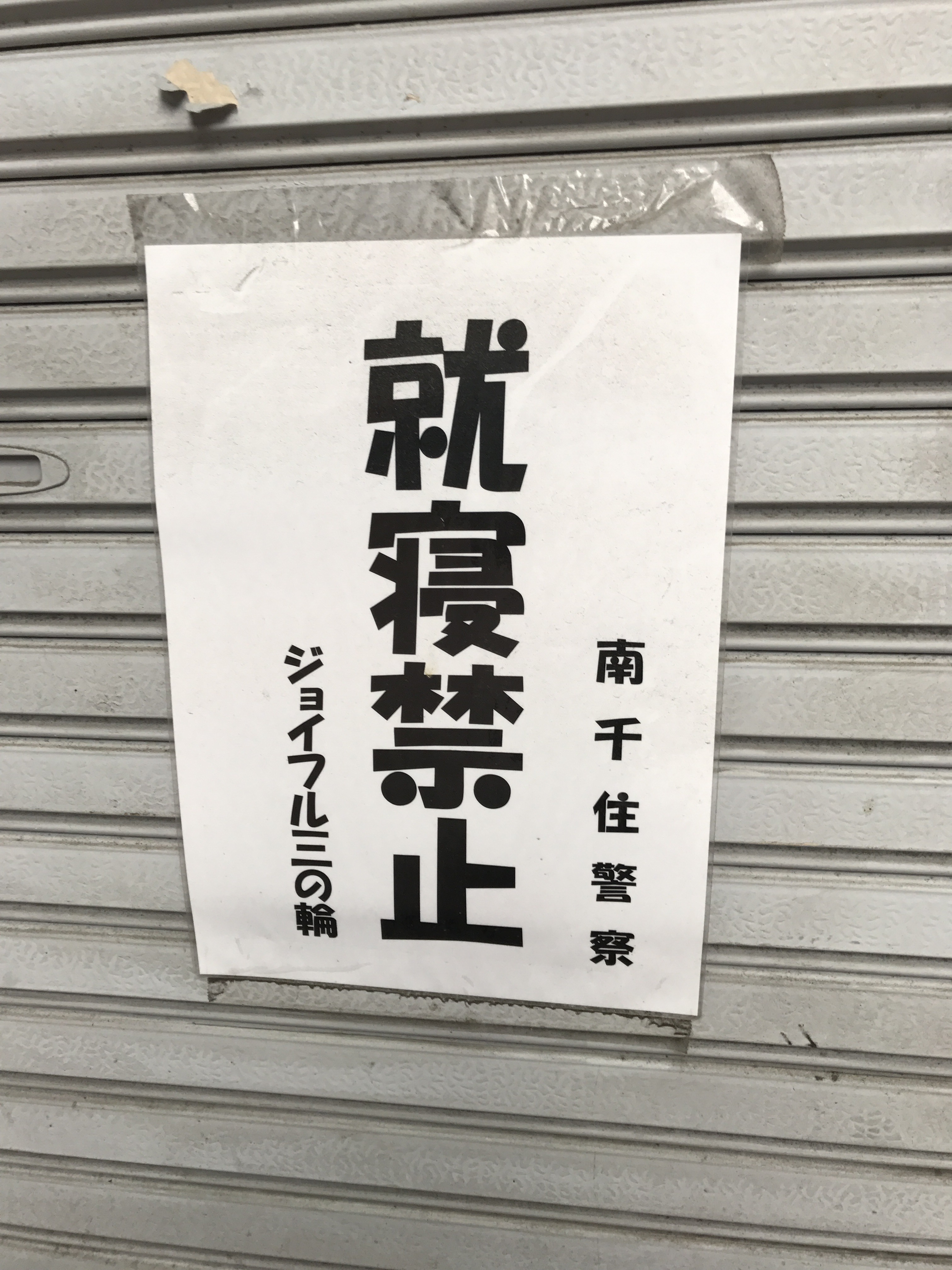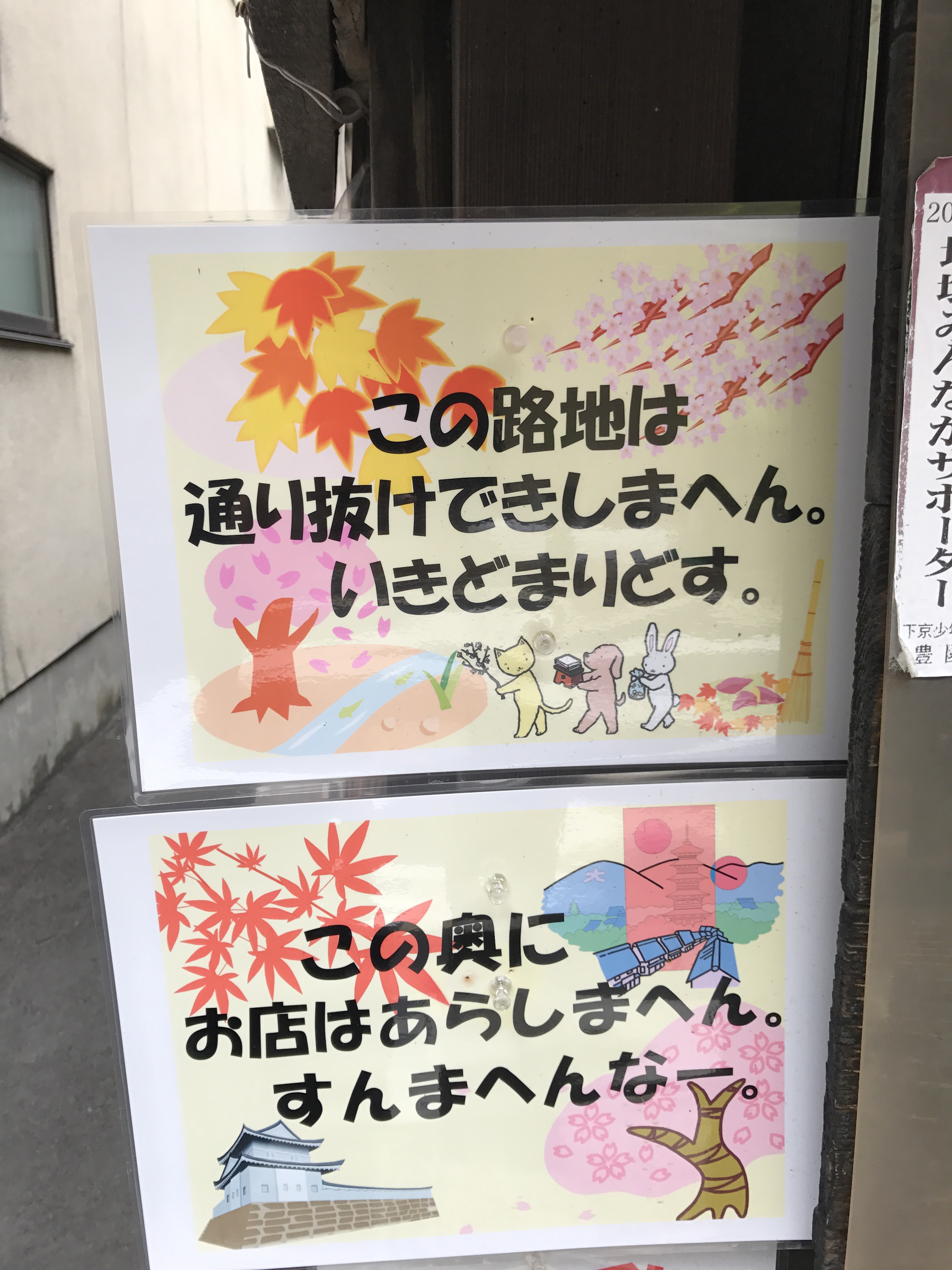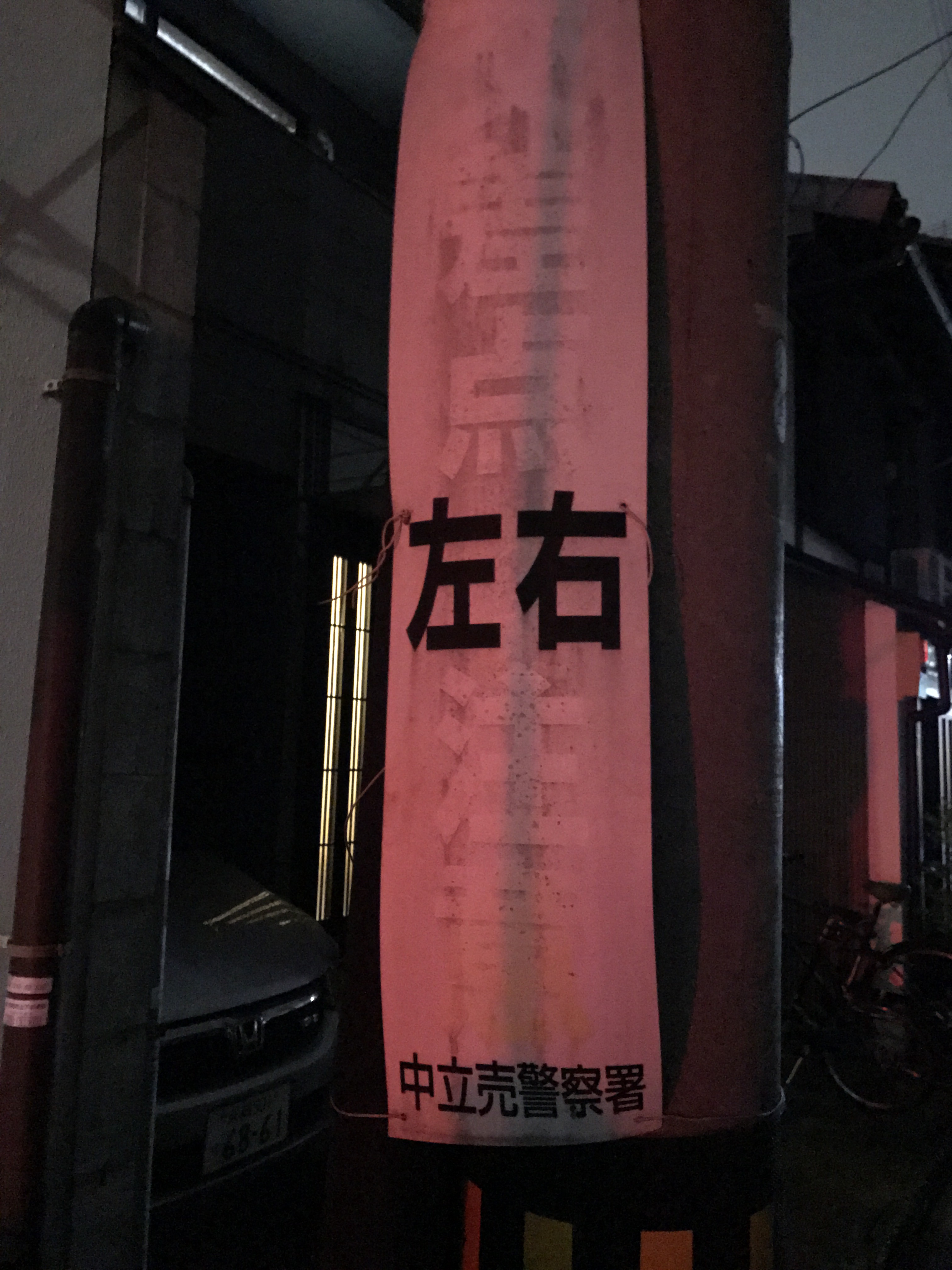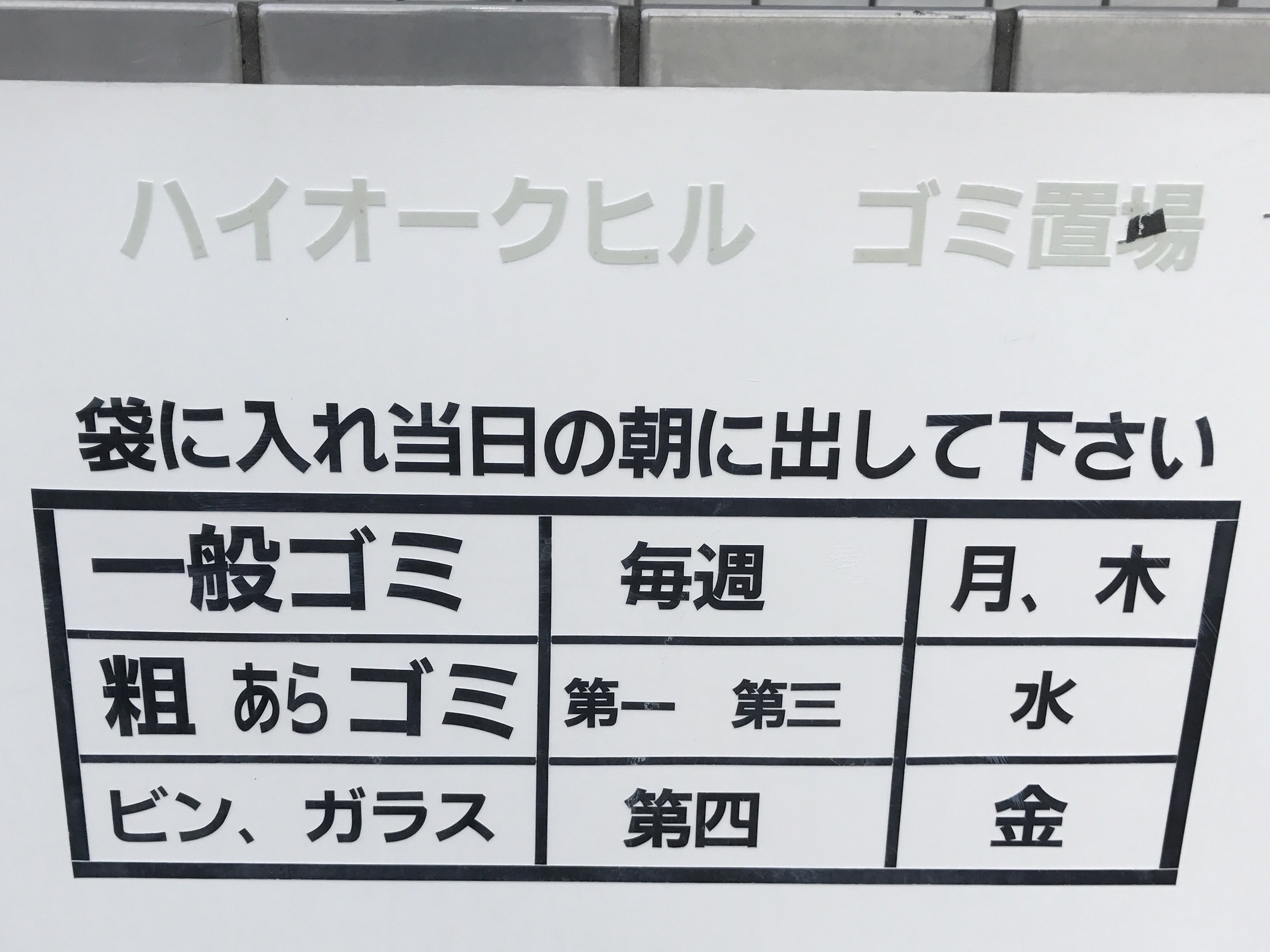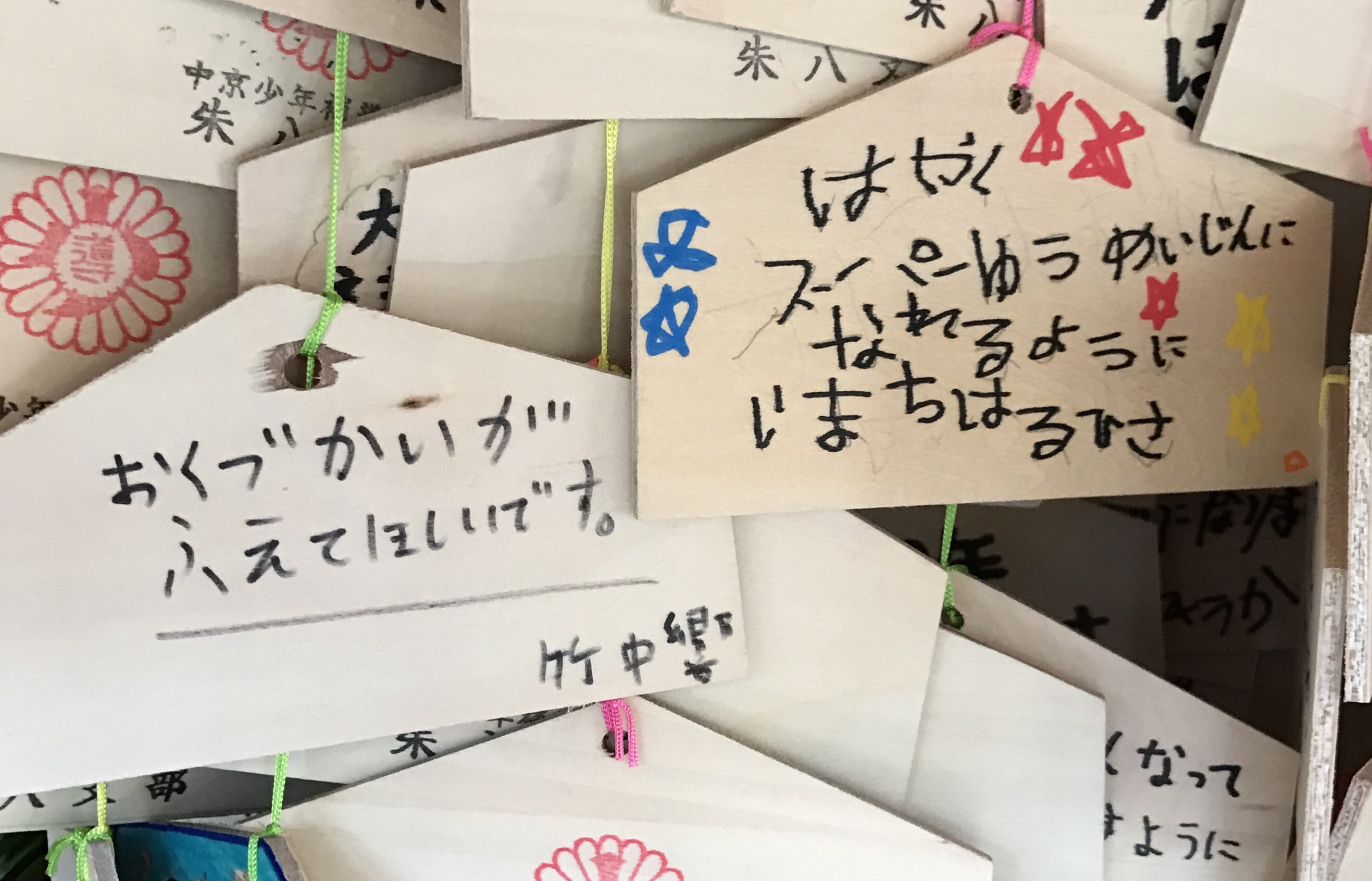10月1日の澤風会大会から始まって、10月は慌ただしく過ぎて行きました。
今日から11月です。
…とは言え、月が改まっても私の生活パターンは全く変わりありません。
今月は新作能の地が2番あり、そのうち「復活のキリスト」は全く初めて謡う曲です。
「復活のキリスト」という曲は、昭和32年に当時の家元宝生九郎先生のシテで初演され、今年6月にバチカン・カンチェレリア宮殿にて現宗家宝生和英先生が再演を果たされました。
私はこのバチカン公演には参加していないため、まだ曲の全貌が掴めていない状態です。
さてこのような新作を覚えるにあたって、私が何から始めるかと言いますと、先ずは「小本」を作るのです。
「小本」。正式には「袖珍一番本」と言われますが、通常の謡本の約4分の1サイズの小さな謡本のことです。
我々はこの小本を束にしていつも持ち歩き、電車の中などで広げて謡を浚う訳です。
余談ですが、以前この「小本」を見た女の子が「え〜何これ可愛い〜!」と言うのを聞いて驚いたことがあります。
我々にとっては単なる「謡記憶ツール」であり、可愛いさなど欠片も感じたことが無かったのです。。「小本」を表紙をもっと綺麗な柄にして、女性向けに売り出せば意外にヒットするかもしれません…。
それはさて置き、私の手元にある「復活のキリスト」の本はB5サイズで、電車で片手で広げるには大き過ぎます。
これをコンビニで縮小コピーして、「小本」と同じサイズにします。
帰って裁断して、ホチキスで留めて出来上がりです。
「小本」サイズに揃えるのは、覚え終わった後に小本と同じ棚に収容して、次の機会まで保管する為です。
さて無事に「復活のキリスト」の小本が出来ました。
ここですぐに覚えれば良いのですが、私の場合「よし!小本が出来たらもう大丈夫だ!」と根拠のない安心を感じてしまい、「覚えるのは明日からにしようかな…」などと独り言を呟き、鞄にしまって満足してしまうのでした。。