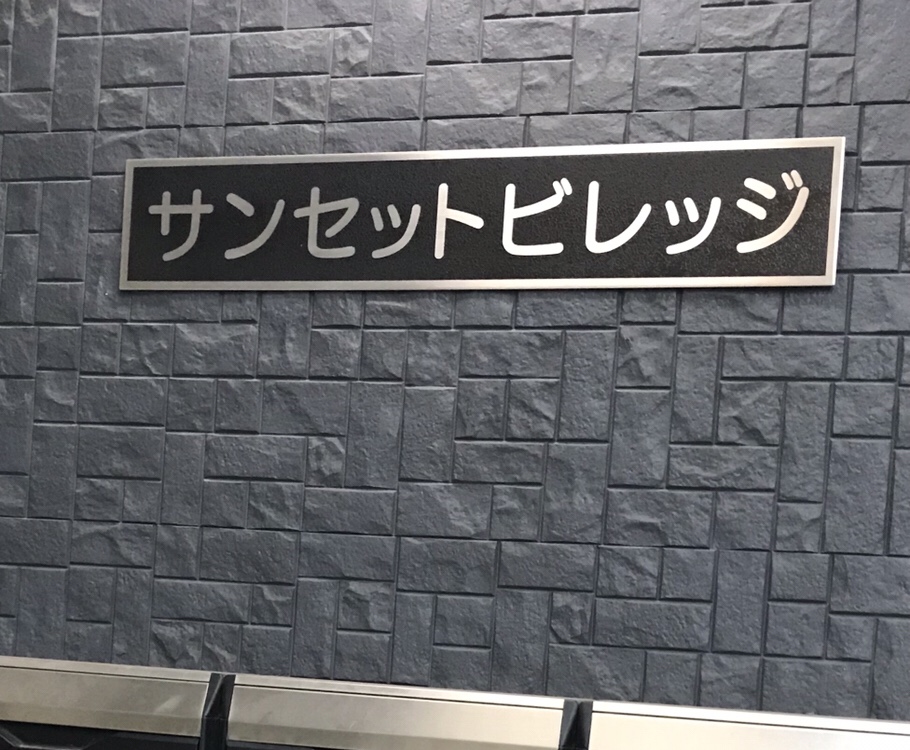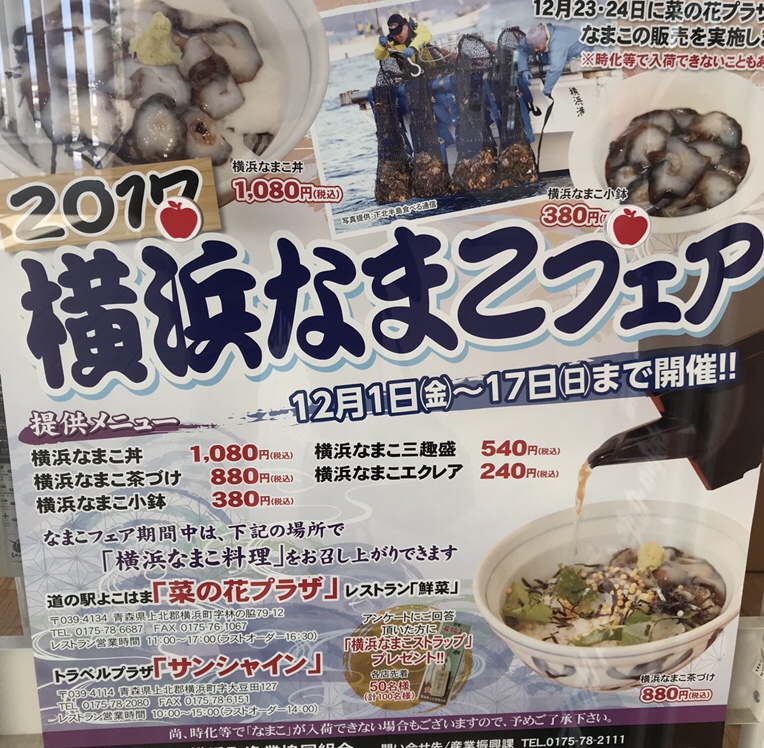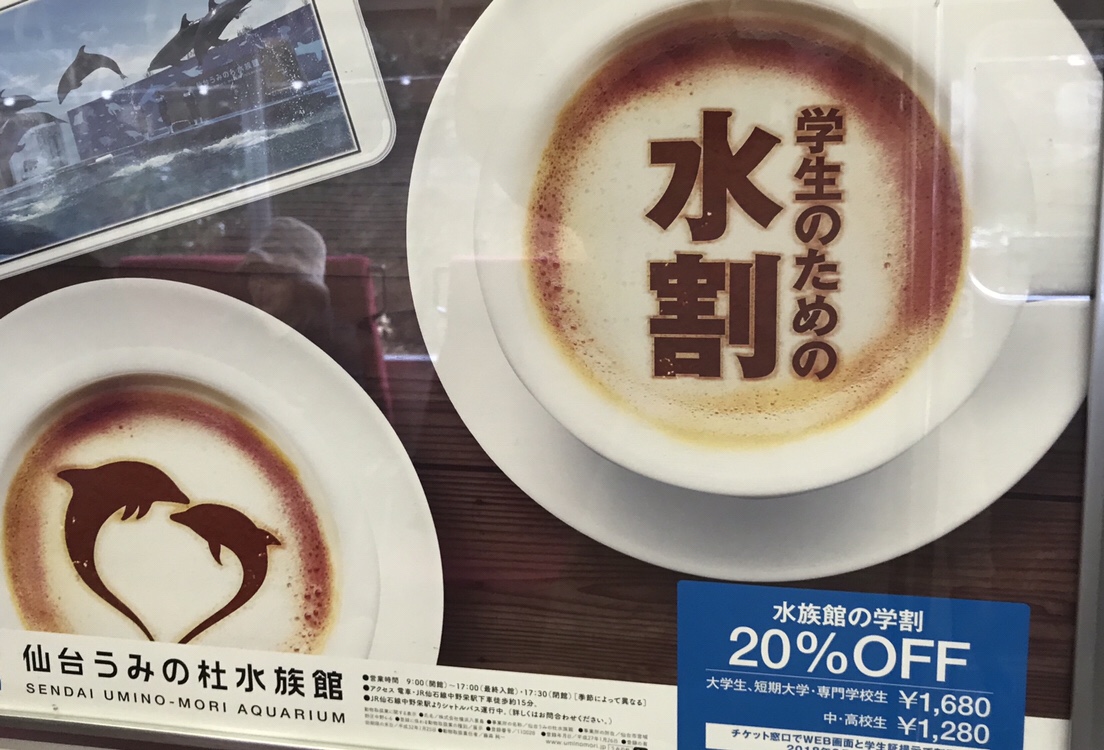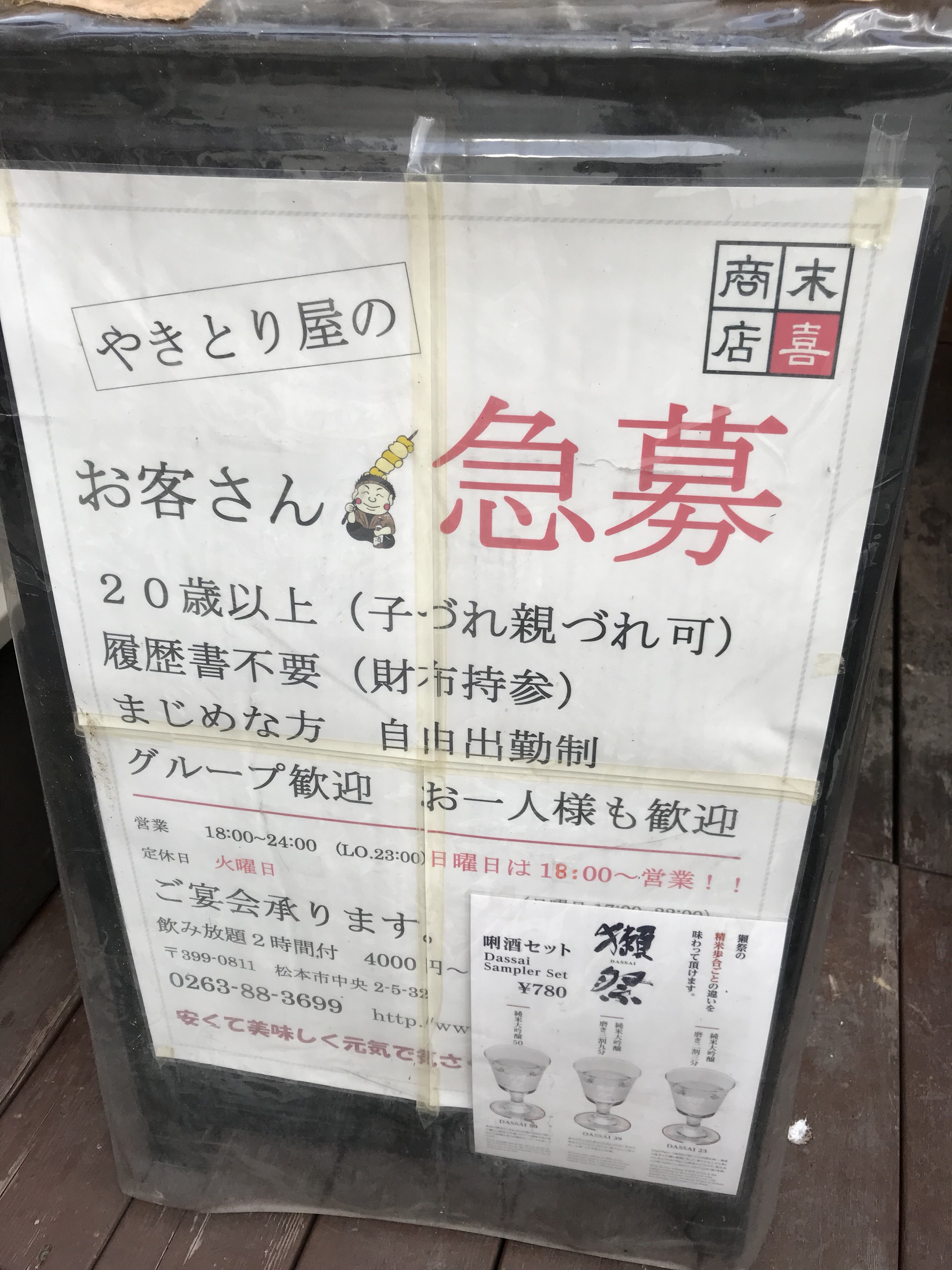数年前に公演で、インドネシアのウブドという伝統芸能の村に行った事があります。
そこでインドネシアの獅子舞である「バロン」という舞台を観た時のこと。
.
舞台でバロンが演じられているすぐ脇の舞台袖で、小さな子供達が懸命に舞台の真似をして演技をしていたのです。
おそらく演者の家族と思われ、私は「こうやって伝統が自然に次世代に伝わっていくのだろう」と感心しました。
.
また7月18日のブログでは、京都の祇園祭に積極的に関わって、自前の鉾を作って子供達に巡行までさせるという洛央小学校の事を書きました。
祇園祭に小さな頃から参加した小学生達は、やはり自然にその伝統を引き継いで将来は祇園祭を担っていくのだろうと、羨ましく思ったのです。
.
.
私の育った東京では、浅草などの一部の町を除いては、そのように子供の頃から地域の伝統に触れてそれを引き継ぐという経験は難しいと思っていました。
.
.
ところがつい昨日、家の近所でそのようなシーンを見ることができたのです。
.
家の近くに「素戔嗚(すさのお)神社」という大きな神社があります。
昨日その前を通りかかると、神社の中から元気な声と共に小学生達がぞろぞろと出て来ました。
.
何か遠足のような行事かと思ったら、どうも普通に学校帰りのようです。
素戔嗚神社の境内が通学路に指定されているようなのです。初めて気がつきました。
.
面白いなと思って境内に入ってみると、ちょっと驚く光景が見られました。
小学生達は皆、本殿の前を通る時にちゃんと立ち止まり、代わる代わる御辞儀をしてから通って行くのです。
中にはきちんと柏手を打ってお参りをしている子供もいます。
.
彼らは毎日登下校の度にこれを繰り返しているのでしょう。
.
調べてみたら、素戔嗚神社は1200年の歴史がある神社で、その例大祭の御神輿が有名だそうです。
こども神輿もあり、正にあの小学生達が担ぐようです。
.
彼らの小学校の名前も素戔嗚神社に深く関わる「瑞光小学校」という名前で、彼らはごく自然に地元の神社に毎日参り、その祭に参加してこども神輿を担ぐようになり、やがて大人になると本社神輿を勇壮に振りながら担ぐようになるのでしょう。
.
そうやって素戔嗚神社の「天王祭」は500年近くも続いて来たようなのです。
.
私の住む町で、このような形で地域の伝統が継承されていたとは、嬉しい驚きでした。
.
そして天王祭の3年に一度の大きな「本祭」が、来年2018年6月に開催されるそうです。
.
これは是非あの小学生達が御神輿を担ぐ勇姿を、そして昔小学生だった人達の担ぐ本社神輿を見に行きたいと思っております。