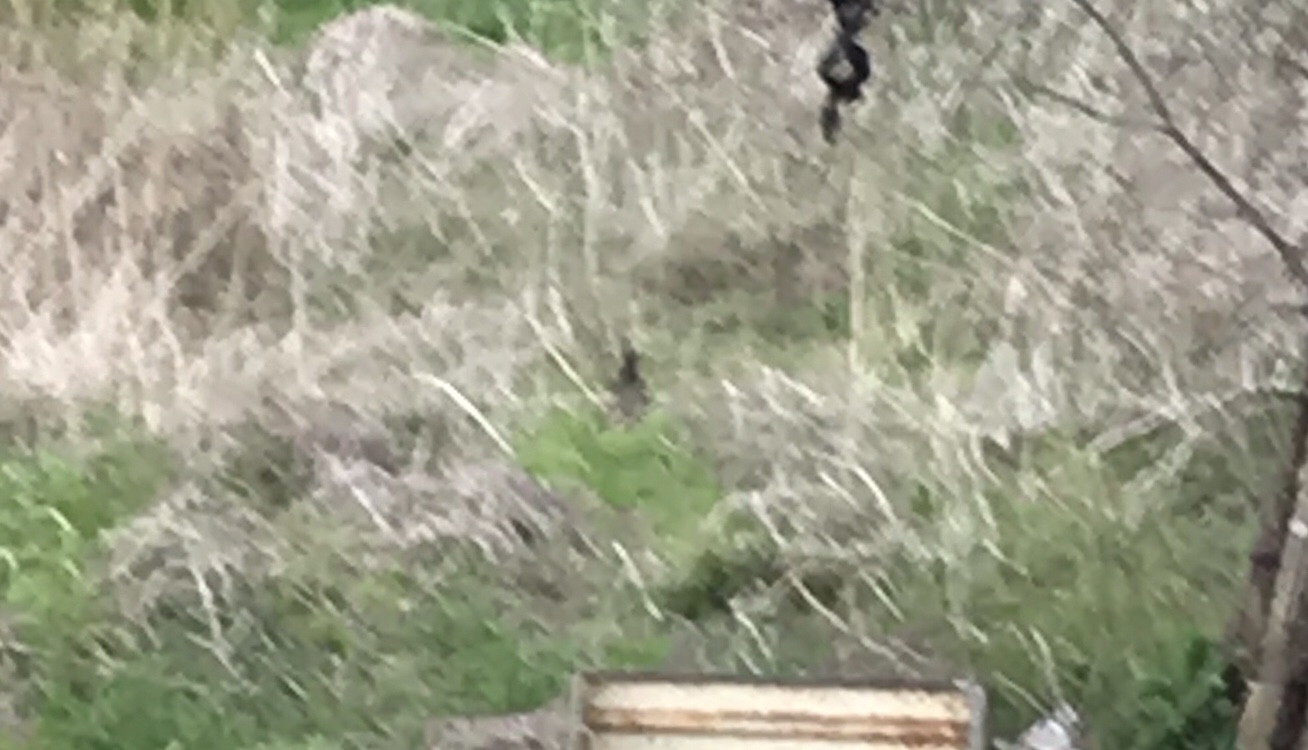今朝私は、夢の中に突然「嵐山」の謡が聞こえて来て、それで目が覚めました。
自分がどこにいるのか一瞬わからなくなったのですが、場所は京大宝生会合宿所2階の「ヤヲハの間」の布団の中であり、よく聴くと「嵐山」は合宿の応援に来てくれた若手OGの声なのでした。
.
なおも布団で暫く聞いていたのですが、難しい「渉り拍子」のところなどもきちんと正確に謡っていました。
流石OG、というより「こんなにハイレベルに謡えるのか」と驚くような謡でした。
これは正に4年間みっちり稽古した成果なのです。
.
京大宝生会は昔から、卒業しても京都近辺にいる若手OBOGが合宿や普段の稽古に頻繁に来てくれます。
前述のようなハイレベルなOBOG達が現役の稽古を手伝ってくれるというのは、大変有り難いことです。
今回も昨日などは6〜7人もの若手OBOGが合宿に来て鸚鵡返しをしてくれていました。
.
OBOGが現役の稽古に顔を出すというのは、場合によっては良くない影響を及ぼす恐れもあり、卒業後は一切現役の稽古には来ない、という学校もあるようです。
しかし京大宝生会に関しては、「クラブの中の事には口を出さず、経済的と技術的な援助だけをする」という不文律があり、現役と若手OBOGがとても良い関係を築いてくれています。
.
現役は今回も例えば、「たった2日で舞囃子を一通り稽古して、地謡と合わせる」というような普通考えると不可能な課題に、それぞれ果敢に挑戦してくれました。
彼らもまた4年間みっちり稽古して、その成果を次の世代に還元してくれることでしょう。
今回もまた、実り多い合宿だったと思います。
.
.
最後に昨夜遅くに開催された驚くほどハイレベルな「ピザ大会」の模様を。

.