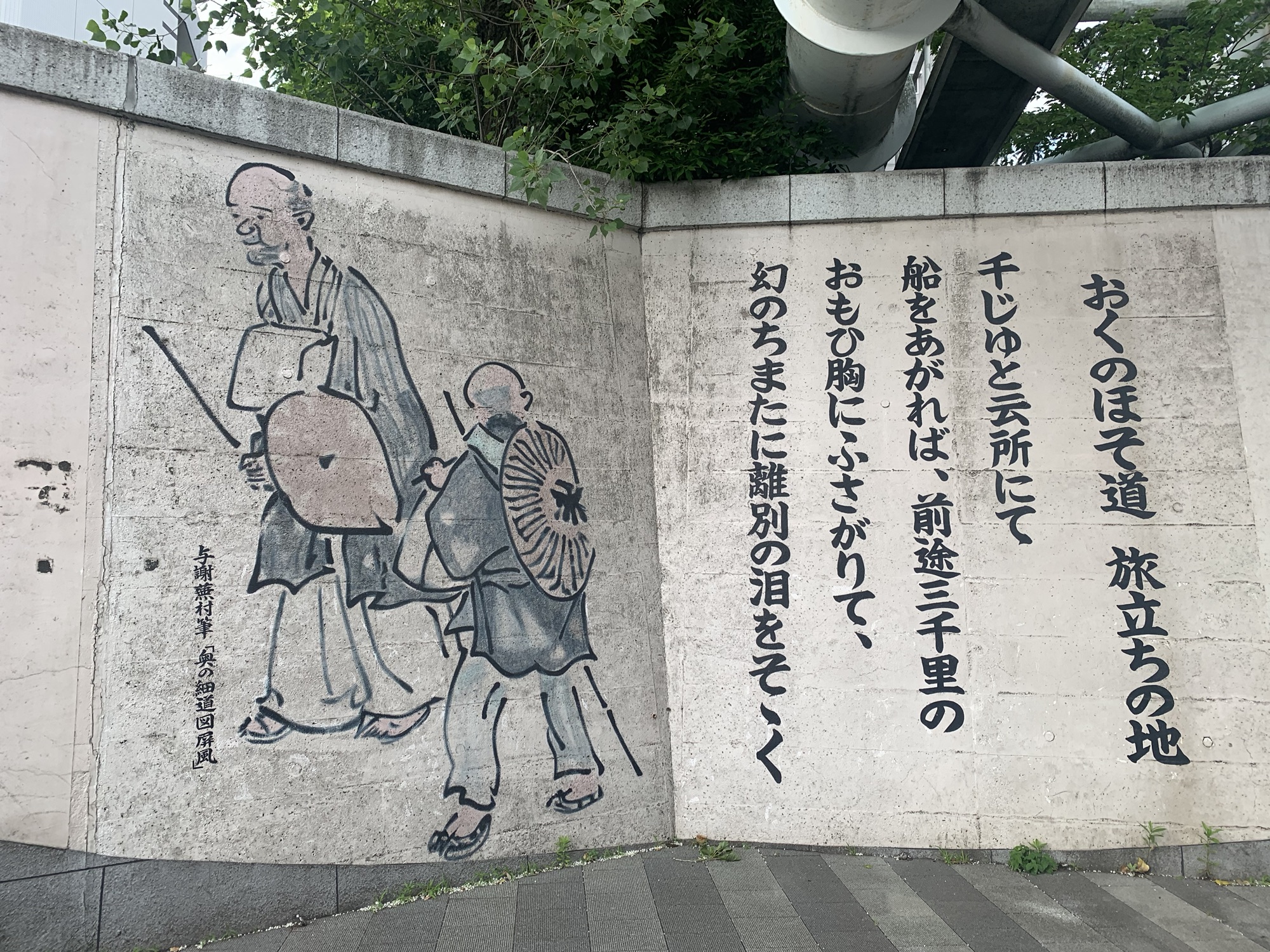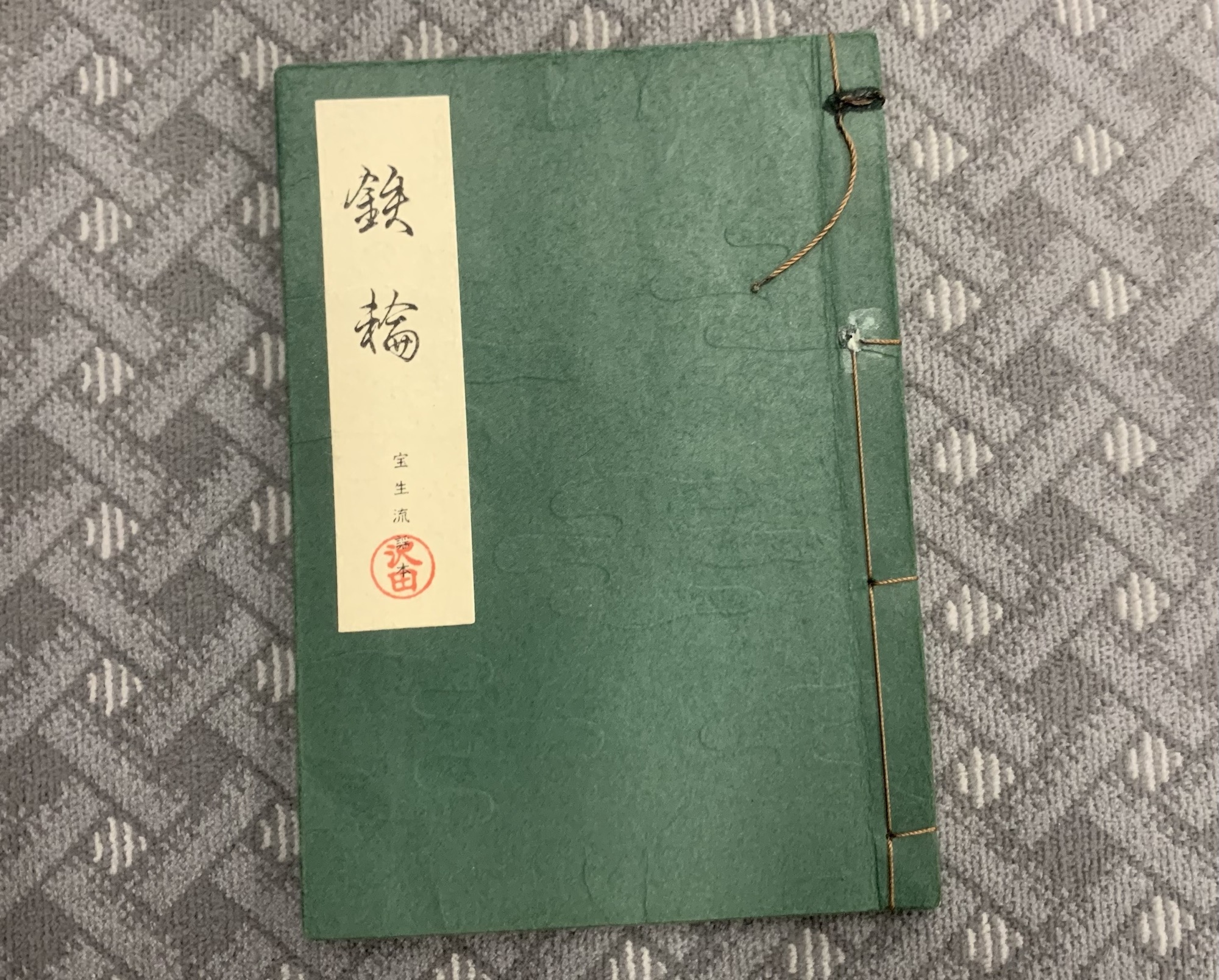今日は雨のパラつき出した東京を昼過ぎに出て、特急あずさで松本稽古に向かいました。
・
下諏訪あたりまでは降ったり止んだりだったのですが、トンネルをひとつ抜けて松本盆地に入ると雨は上がっていました。

水の入った田圃に空の薄青色が写って、瑞々しい初夏の風情があります。
・
松本は山に囲まれているので、雨も雪もその山々に遮られて、ひどくは降らないのです。
数年前の「松本城薪能」でも、台風の接近で舞台中止かと思いきや、ギリギリで天候が持って能「鵺」をなんとか舞えた記憶があります。
・
・
実は今年も8月8日に「松本城薪能」が開催予定です。
宝生和英御宗家がシテを勤められる能「紅葉狩」と、私がシテを勤めさせていただく能「経政」が出ます。
・
今回も天気だけが心配ですが、松本盆地を囲む山々に守ってもらい、なんとか舞いたいと思います。