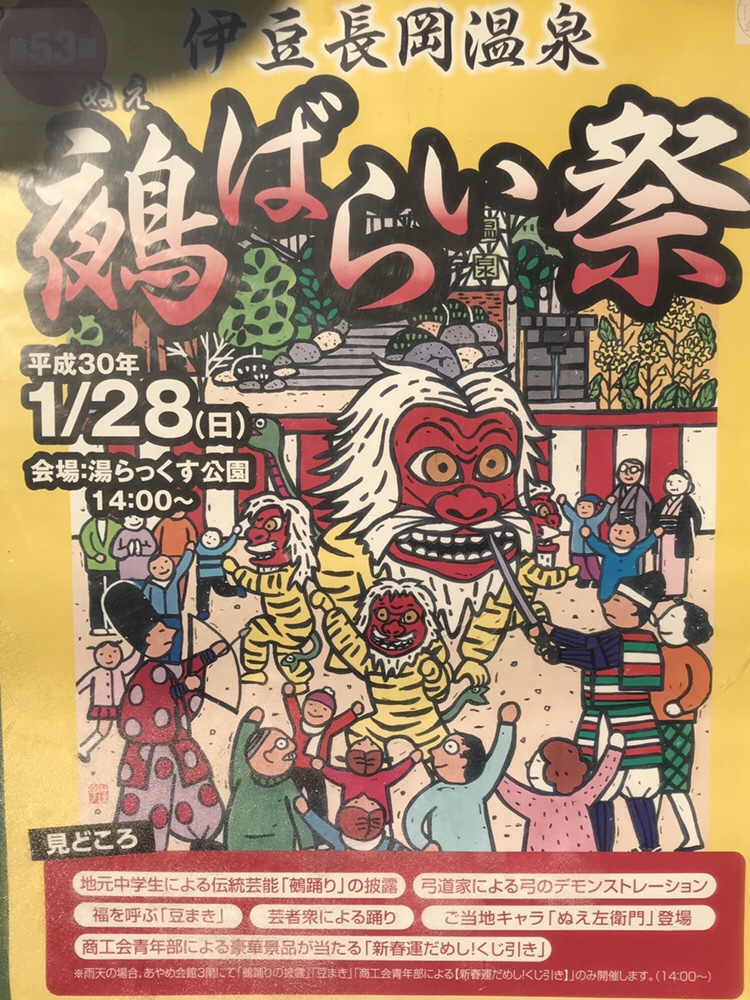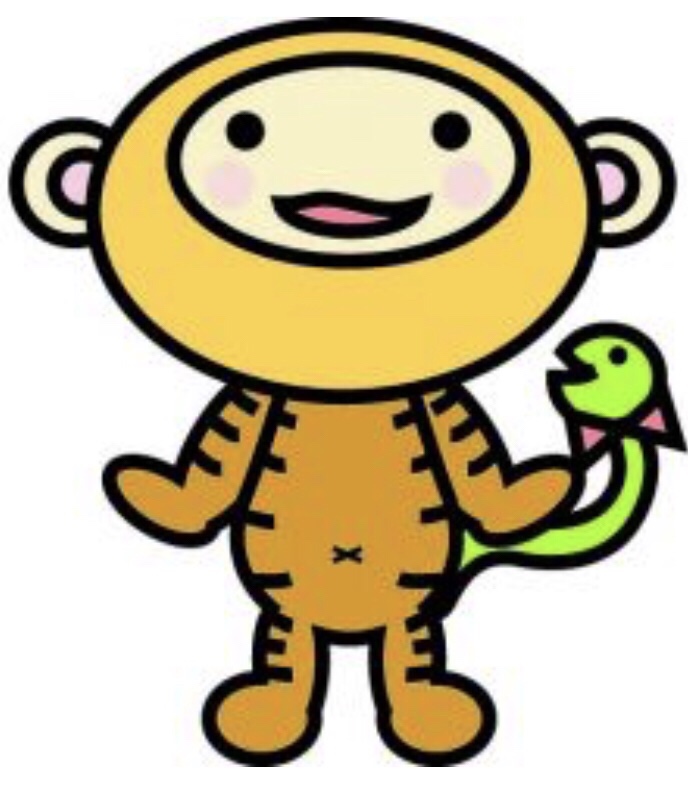今日は松本稽古場の今年初めての稽古でした。
例年初稽古の後に、会員さんのされているイタリアンのお店で新年会をします。
.
今年は珍しいパターンで、稽古の後に用事で何人か帰られて、逆に新年会から参加の方も何人かいらして、全体的にはこぢんまりとした食事会になりました。
しかし大きなテーブルをちょうど囲める人数で、皆さんそれぞれの興味深いお話を、等しく聞くことが出来ました。
.
松本稽古場には何故か様々な分野の職人さんが多くいらっしゃいます。
「独学で勉強を積んだ」という方、「体育会系の親方の元で厳しい日々を過ごした」という方。
バリエーションに富んだそれぞれのご経歴を伺うだけで大変面白かったのですが、今日のお話で共通していた意外なことがあります。
「その職の肝心なところは師匠からも誰からも教えてもらっておらず、自ら勉強して会得した」ということです。
.
一見理不尽なことと思われますが、これは能楽の世界にも当てはまることなのです。
楽屋の仕事や舞台上のことの大半は自分で見て覚えておくもので、ある日突然「やってみろ」と言われて、その仕事が出来ればOKで何もコメント無し。出来ないと「今まで何見てたんだ!」と怒られるのです。
.
一見不合理に見える修行のやり方の裏側に、大切な本質があるように思っていて、しかしその感覚は他人とは共有し難いと考えておりました。
なので今日は似た感覚を持つ方のお話を伺えて、大変嬉しく思いました。
.
他の稽古場でも本当は今日のように、私ではなく皆さんのお仕事のお話をもっと伺ってみたいと思いました。
.
もちろん今日は真面目な修行の話ばかりでなく、「鰻を食べた後にカラオケに行く会」の企画の話や、「羊のチーズ」が出たので「羊はあんなに毛がモコモコあるのにどうやってお乳を絞るのか?」といった話など、色々と楽しい時間を過ごしました。
.
松本の皆様どうもありがとうございました。
お料理もワインも大変美味しかったです。
.
本年も頑張って稽古して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。