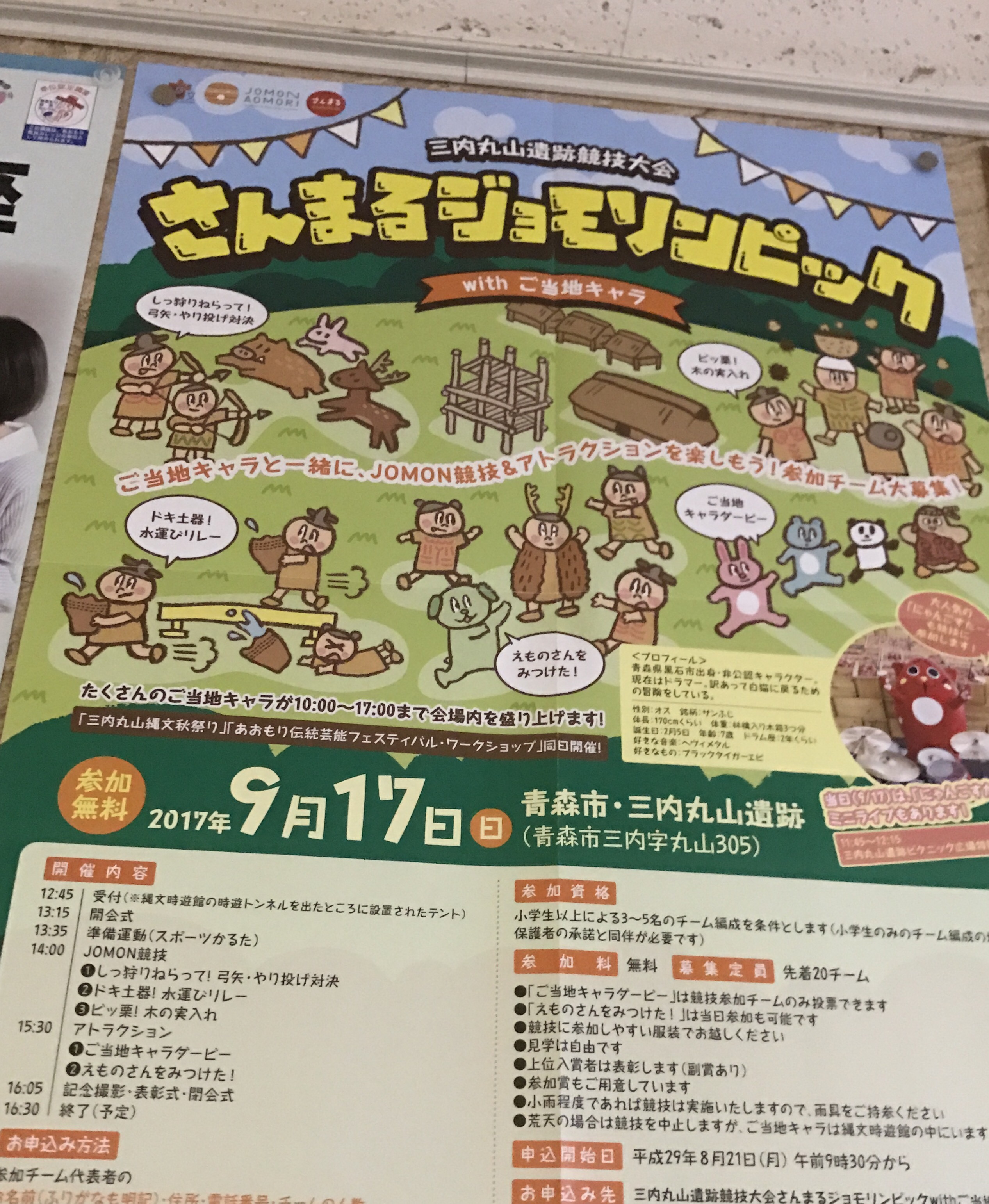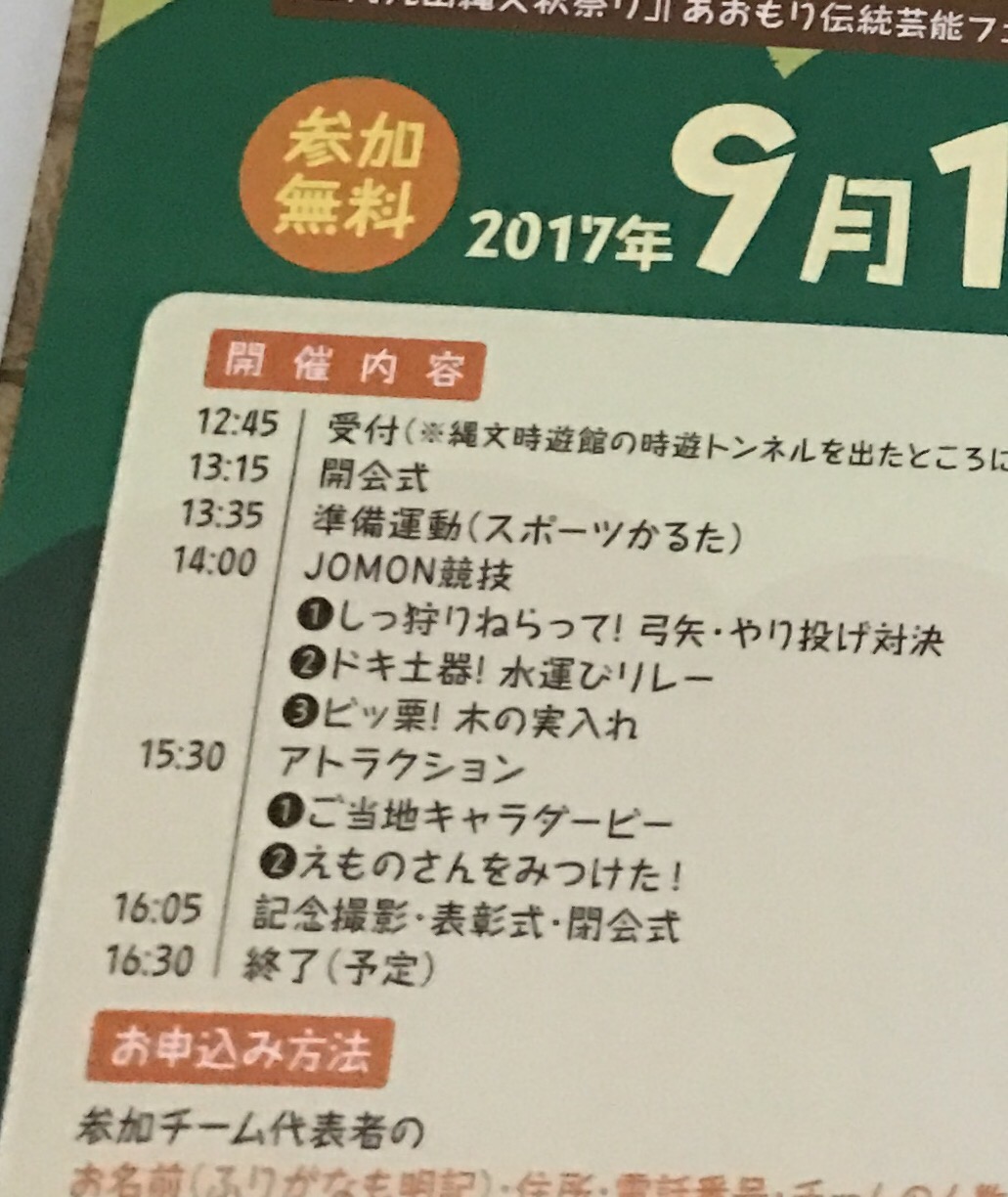昨日軽井沢であった大鼓の会「佳広会」は、葛野流家元の亀井広忠師のお社中会でした。
実は澤風会でも亀井師に大鼓を習っている人が何人かいらして、昨日は4人の澤風会会員(母親の郁雲会会員も含みます)が大鼓を打たれました。
皆さん熱演でしたが、中でも仕舞や謡では大ベテランの方が、なんと大鼓は昨日が初舞台ということで、緊張されながらも大変素晴らしい舞台でした。
謡仕舞に加えて大鼓のお稽古もされるのはすごいと思っていたら、昨日は更にすごいベテランの方々がおられました。
「大鼓は亀井先生、小鼓は○○先生、笛は○○先生、太鼓は○○先生で、謡仕舞は○○先生に習っています。」という方など、いったいお仕事との兼ね合いはどうされているのか、本当に大したものだと思いました。
しかし楽屋での話では、昔はそのような方がもっと沢山いらして、能楽界を支えてくださっていたとのことです。
一方澤風会には、最近になってお囃子の稽古を始める人が増えて来ました。
京大宝生会も近年稀に見るお囃子稽古ブームです。(笛3人、大鼓小鼓太鼓各1人。)
能楽関係で複数の種類のお稽古をしてもらえると、師匠同士の交流も増えて、能楽全体にとって非常に有意義なことなのです。
どうか複数の稽古をされている人達は、今後も順調に稽古を続けていただきたいものです。
そして昨日の佳広会のベテランの方々のように、能楽界を横に繋いで盛り上げていってもらえたらとても有り難いと思いました。