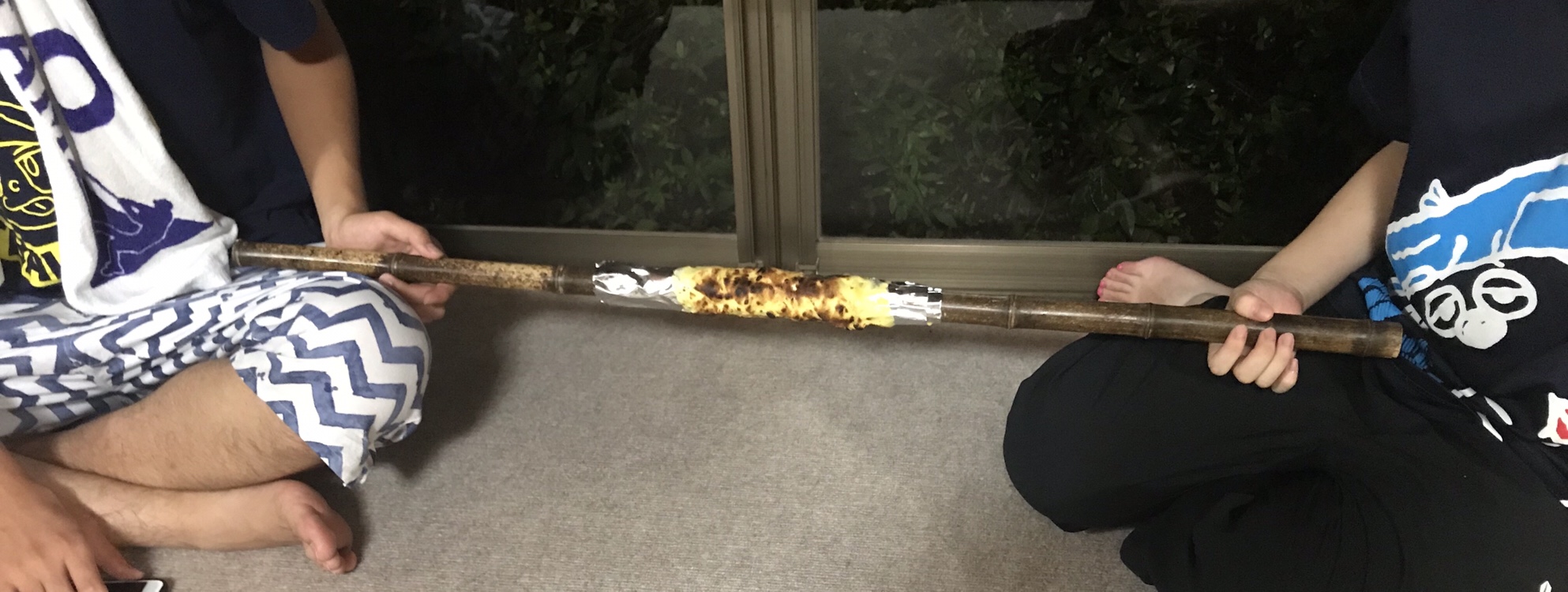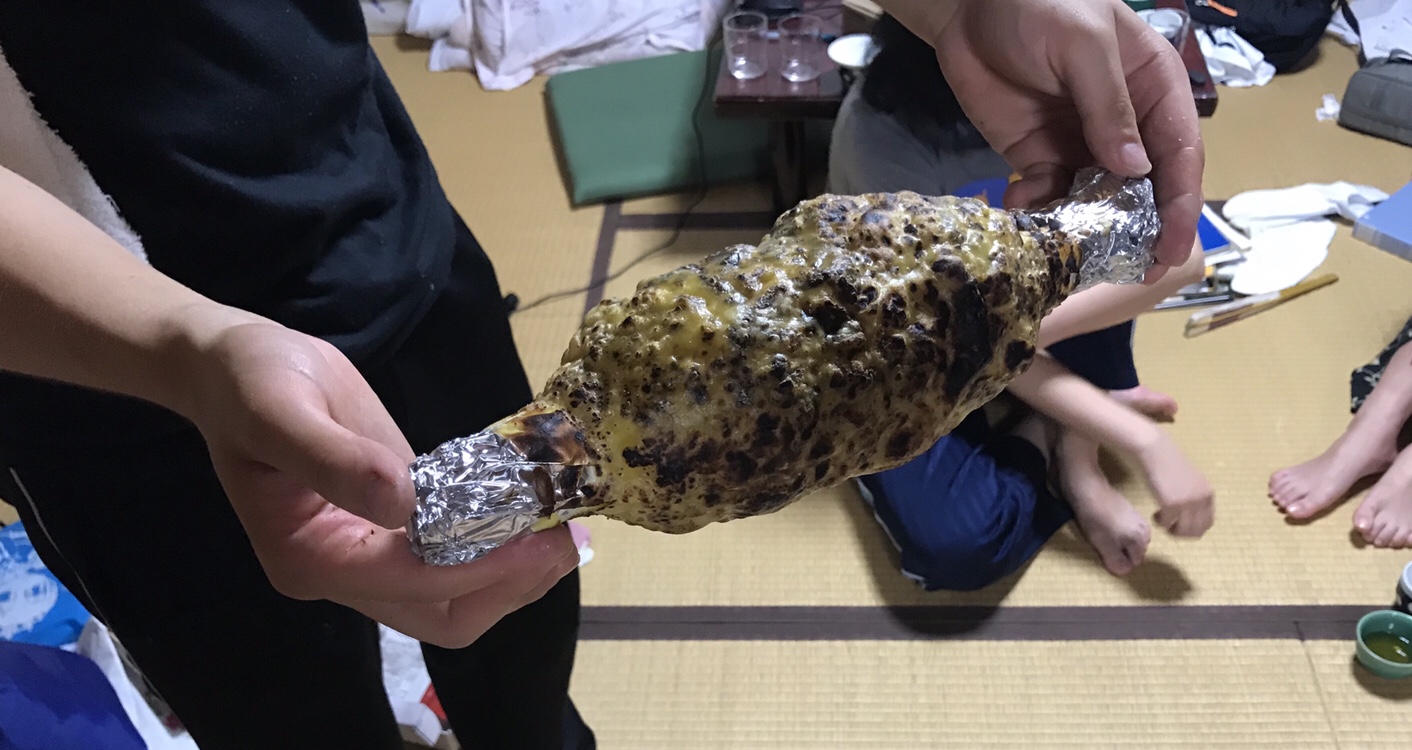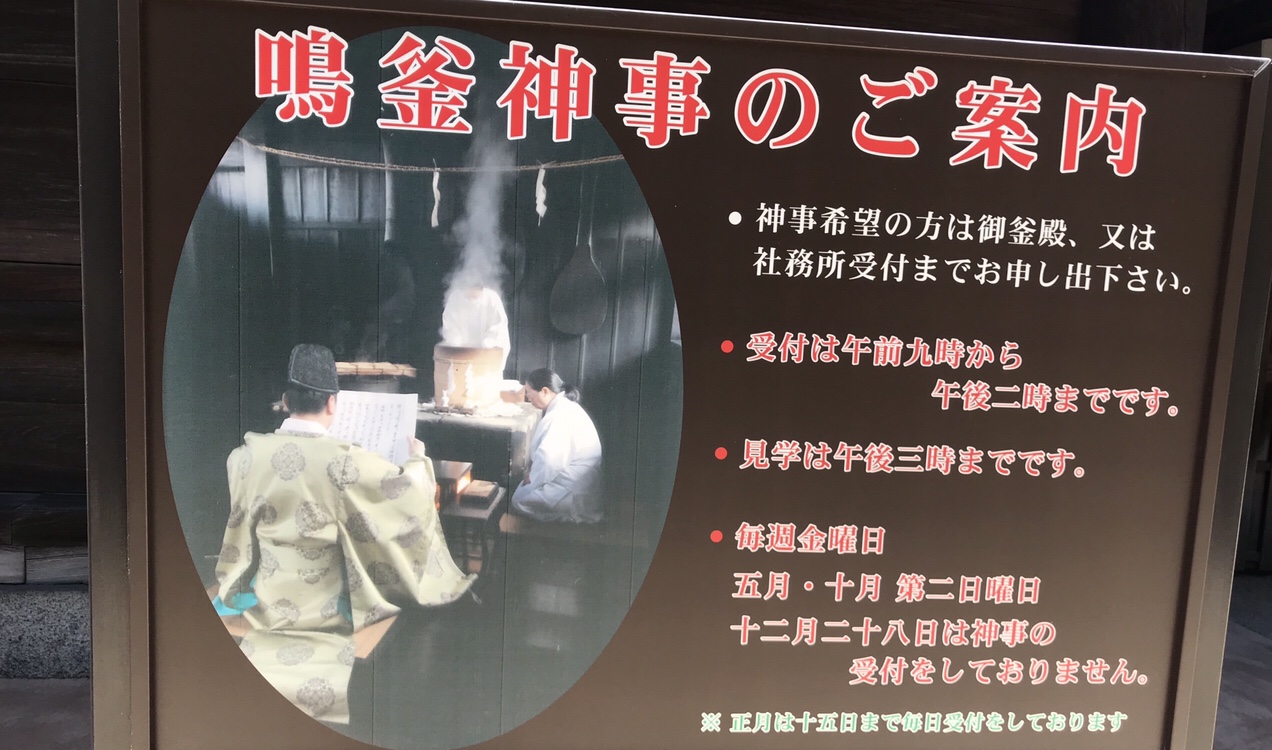今日は「岩手未来機構」の皆さんに招かれて、盛岡でとあるセミナーに参加しました。
「岩手県の伝統文化芸術活動の担い手が、今後より良い活動をしていくにはどうしたら良いか」というテーマのセミナーでした。
.
ユネスコ無形文化遺産にもなっている”大償神楽”の伝承者の方や、茶道、華道など、様々な分野の人達が集まりました。
私は能楽師の立場から、子供向けのワークショップや能楽教室の話、また大学での能楽部の話などをさせていただきました。
.
大償神楽の方は、「昔は地域ごとのまとまりが今より強く、神楽の後継者育成もやりやすかった。
顔見知りの子供達の中から、この子はいけると思う子供に声掛けして、神楽に参加してもらっていた。
しかし複数の地域の学校が統合されてしまい、昔からのやり方で子供達に神楽を教えるのが難しくなった」と仰いました。
.
また、「学校や幼稚園の先生のカリキュラムが忙し過ぎて、伝統芸能の体験まで手が回らない」
「担い手が高齢化して、助成金などの申請手続が困難である」
など、厳しい現状を憂う意見が相次ぎました。
.
私は子供達や大学生と言った将来を担う後継者に能楽を伝える為ならば、報酬は無くても構わないと、極端な話私自身が経済的負担を負っても良いと考えていました。
しかしその考えに対しても、「そのやり方では、あなたは一代では可能でも誰かに代替わりした後が続かなくなる。やはり担い手への金銭面の保証は不可欠である」
というお言葉をいただき、確かにその通りだと思いました。
.
今回は私の能楽師としての事例をお話しする為に呼ばれたのですが、結果的に私の方が色々勉強させていただきました。
.
岩手未来機構では、今回の趣旨のセミナーを今夏5回にわたって県内各地で開催して、其々の地域の文化芸術活動の担い手の声を集計して、県への働きかけなどをしていくということです。
これは大変に労力が必要で、また非常に意義深い活動だと思います。
.
日本中の伝統文化活動において、おそらく同様の問題が同時進行で起こっていると思われます。
この岩手未来機構のような積極的な活動が全国的に行われて、それが県を超えて連携していければ、日本の伝統文化の維持と発展に大きな力になるだろうと思いました。